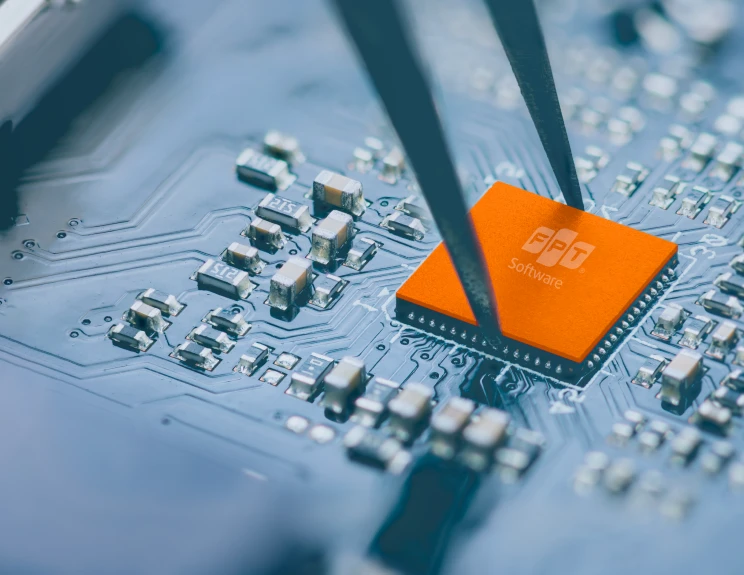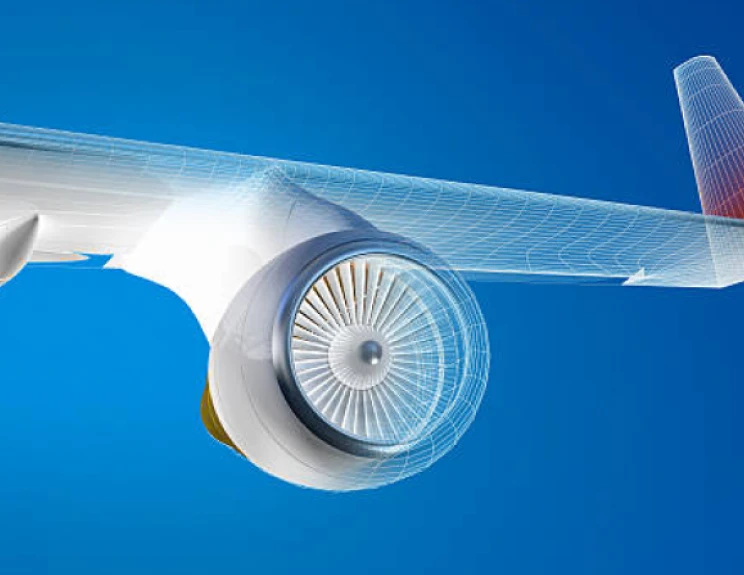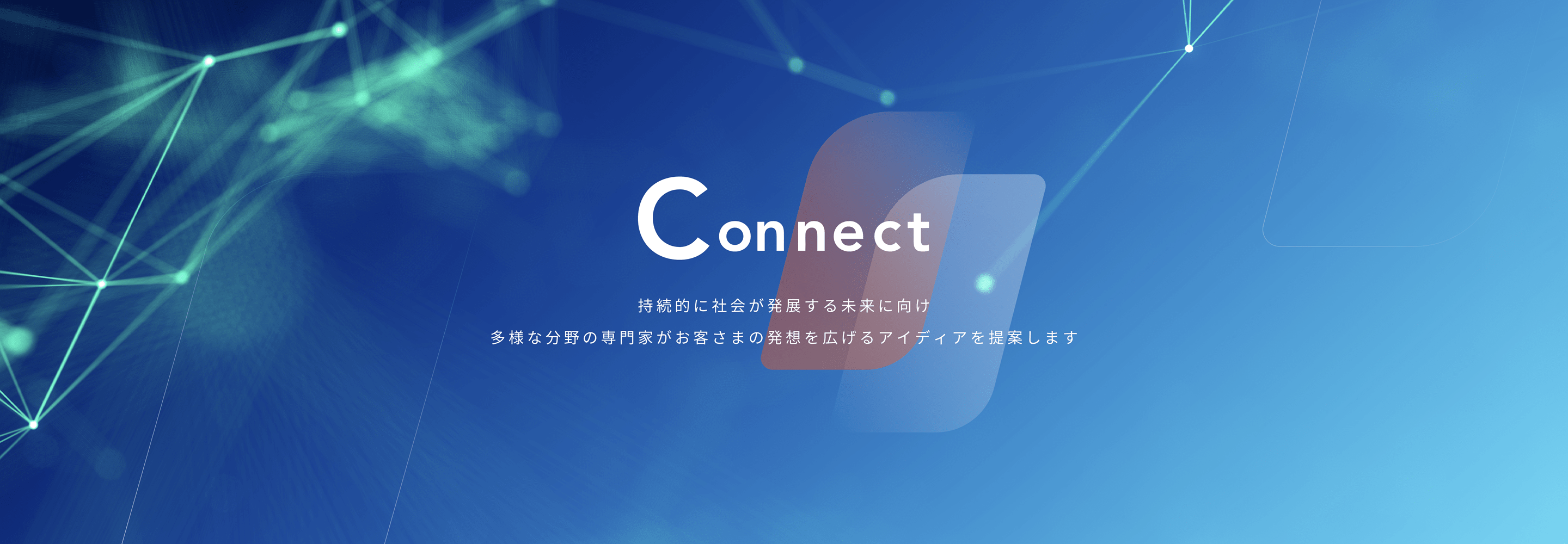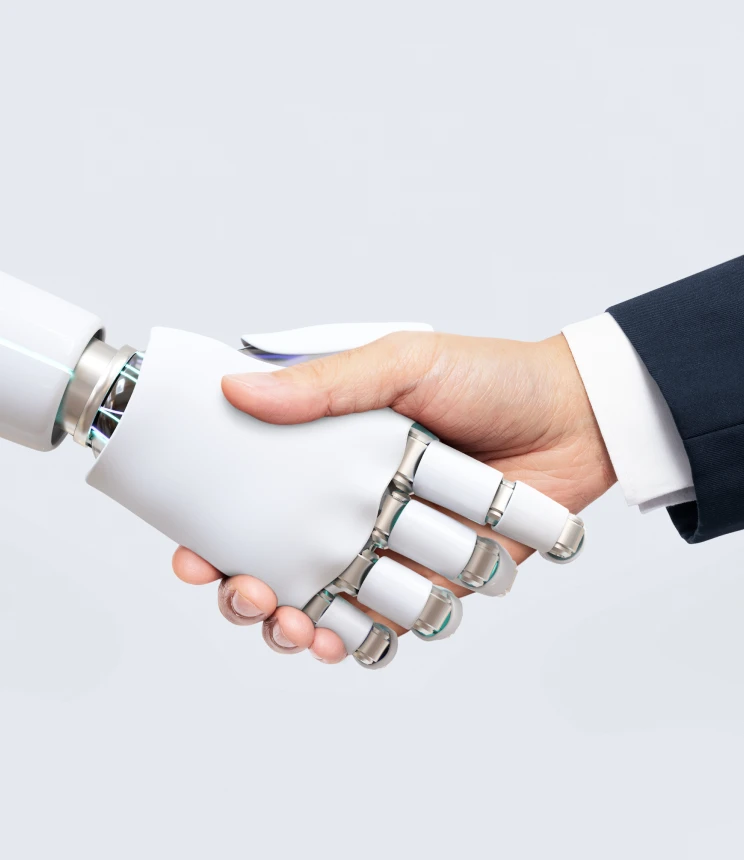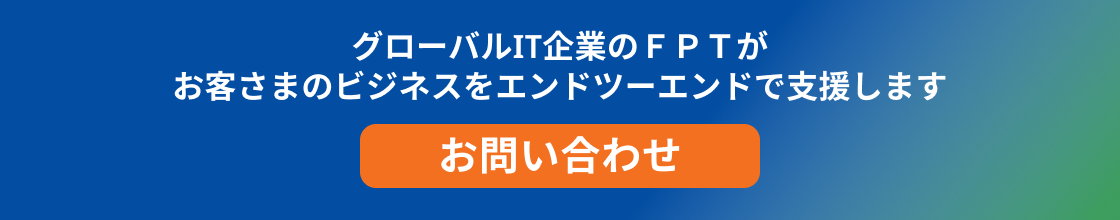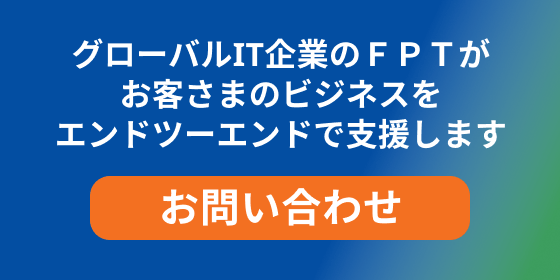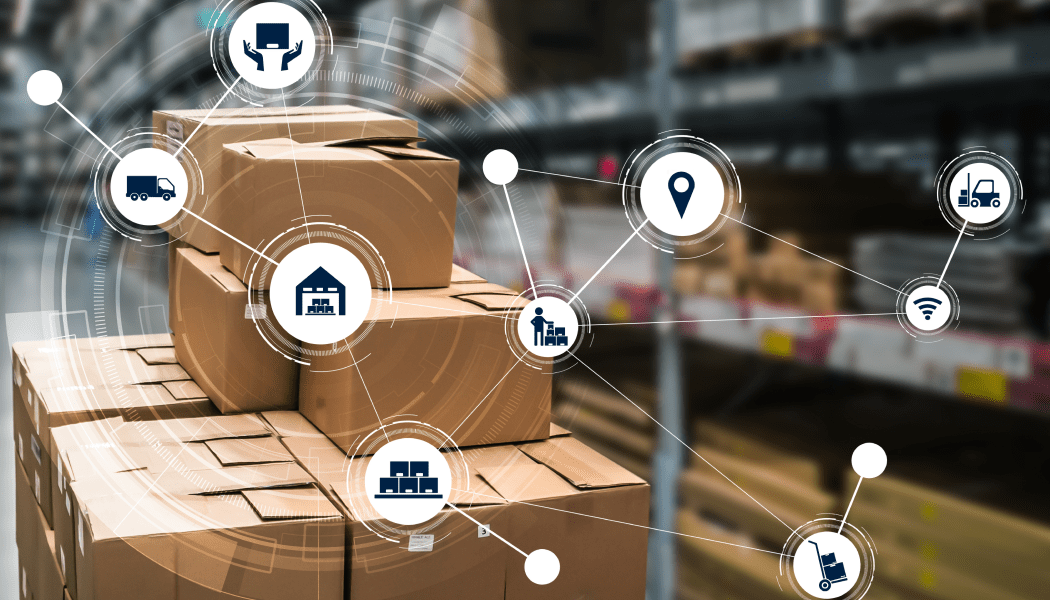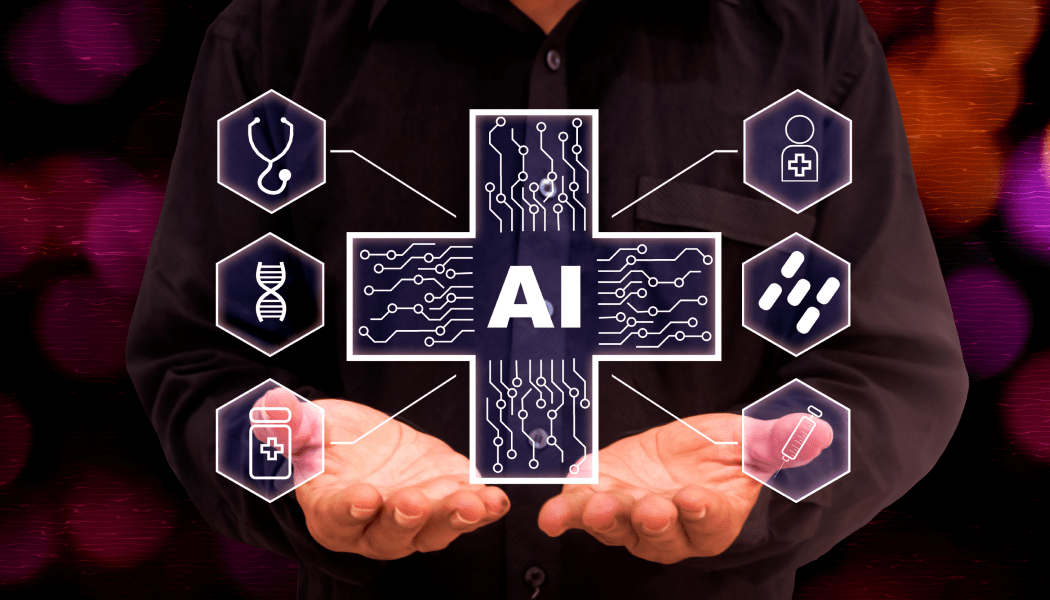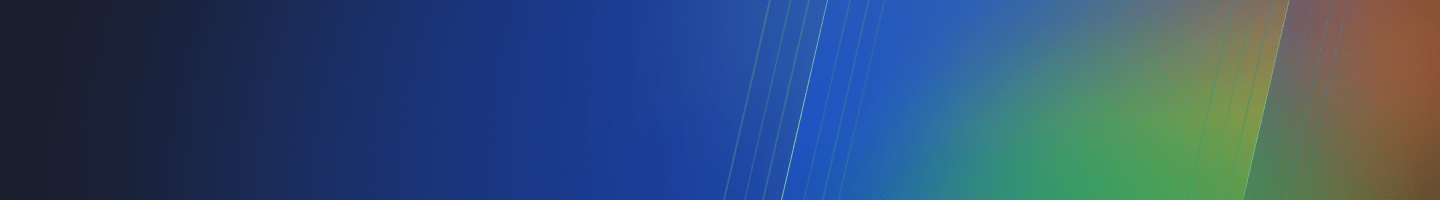目次
AIエージェントとは何か

AIエージェントとは、指示された目標を達成するために、状況に応じて判断し、必要な手段を選択して行動できる「自律型AIシステム」を指します。従来のAIが特定の作業に特化し、決められたコマンドでしか実行できなかったのに対し、AIエージェントは自らタスクを分解したり、計画を立てたりすることが可能です。ただし、「AIエージェント」という言葉は、複雑な業務に対応できるのか、あるいはあらかじめ設定された状況下でのみ動作するのかによって、その定義が異なる場合があります。基本機能を備えたChatGPTやGeminiを起点に、現在ではChatGPT AgentやDevinといった業務特化型の商用AIエージェントへと進化しています。さらに今後は、ERPやRPAと連携しながら業務を担うAIエージェントの活用が広がっていくでしょう。
AIエージェントの基本要素と仕組み
米国の研究者らは「From LLMs to LLM-based Agents for Software Engineering: A Survey of Current, Challenges and Future」で、次のようにAIエージェントの4つの基本要素を挙げました。
| 基本要素 | 概要 |
|---|---|
| 自律性 | ・自律的に判断・行動できる ・細かい指示を必要としない ・環境の変化に柔軟に対応できる ・優先順位を判断できる |
| 目標思考 | ・目標達成に向けて、最適なプロセスを構築する ・自ら軌道修正を行う能力がある |
| 外部連携 | ・センサーやAPI、他のAIエージェントと連携してデータを活用する ・複数タスクの効率的な管理が必要な場合でもスムーズに業務を遂行できる |
| 高度な推論 | ・複数のデータを活用し、状況に応じて最適な意思決定を行う ・効果的な行動方法を学習できる |
AIエージェントの仕組みは次の通りです。目標が設定されると、まず実行可能なタスクを分類し、実行するために必要な情報を検索します。方法を決めたら、計画を実行し、目標達成のための最適な行動を起こします。完了すると、リストからタスクを削除し、次のタスクへと移ります。このようにAIエージェントは自律的に動作するAIであり、状況に応じて柔軟にタスクを処理できるのが特徴です。

生成AIとの違い
ChatGPTやGeminiといった生成AIは、与えられたプロンプトに対し、質問に答えたり、画像を生成したり、文章を生成したりすることができます。つまり指示通りに作ることが得意なAIといえるでしょう。一方、AIエージェントはユーザーが設定した目標に基づき、自律的に計画を立てて実行し、PDCAサイクルを回すことが可能です。生成AIの場合、新しい知識を獲得するためには、モデルの再学習をする必要があります。一方、AIエージェントは自ら経験を活かして改善できるため、人が細かく指示を出さなくても、目標達成に向けて自律的に行動できます。さらに、インターネット検索やデータ分析、メール送信など、複雑なタスクをこなすこともできます。
他のAI技術との違い
• AIアシスタントとの違い
SiriやAlexaといったAIアシスタントは、ユーザーの音声やテキスト入力などの明確な指示がある場合にだけ、タスクを実行できるプログラムです。一度セッションを閉じてしまうとメモリはリセットされてしまいます。一方AIエージェントは、AIアシスタントと異なり、実行した行為を記憶し学習することができます。
• LLMとの違い
LLM(大規模言語モデル)はビッグデータとディープラーニングによって構築された自然言語処理のことです。パラメータ数やデータ量、計算量を強化することでテキスト分類やテキスト生成などに対応します。LLMが人の脳を模したものだとすれば、AIエージェントは脳に加えて目や手足を持った自律的なAIといえるでしょう。
• RPAとの違い
AIエージェントは目的達成までの状況を判断し、最適な方法を選びます。入力ミスや画面変更といった想定外のことが起きても、原因を推測し改善することが可能です。一方、RPAは定められた手順通りに処理を行うため、想定外の挙動を検知すると停止してしまう可能性があります。また、AIエージェントは自己学習によって品質を上げていきますが、プロセスがブラックボックス化しやすいのが特徴です。RPAはロジックが「見える化」されているものの、人によるメンテナンスが必要です。
RPAとAIの違いについては以下をご覧ください。
⇒RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは?ビジネス導入事例とともに解説
AIエージェントの実用化が進んでいる背景
AIエージェントの実用化が進んでいる背景には、以下の要因があります。
LLMの進化
LLMは従来のものと比較して、計画の精度が向上し、より確度の高い回答を生成できるようになりました。さらに、ツール使用の最適化やファインチューニング(追加学習による性能調整)、思考の連鎖(段階的な推論プロセス)などにより、複雑な問題についても対応できるようになりました。
AI利用の拡大と技術競争
2022年以降、ChatGPTの普及によって一般ユーザーもAIを使う機会が増えています。また、AI技術を提供する側の技術競争も激しくなり、より高度なタスクを実行できるAIエージェントに開発がシフトしています。
少子高齢化の影響と働き方改革を行う必要性
日本では、少子高齢化の進行により人材不足が深刻な課題となっている一方で、残業時間の増加も問題になっています。そのため、人材不足や長時間労働の是正にAI活用が有効だと考えられるようになりました。こうした課題を解決するためには、AIエージェントによる業務の自動化を通じた生産性向上が必要です。
AIエージェントの6つのタイプ

AIエージェントには次のように6つのタイプがあります。ここでは、各タイプについて詳しく解説します。
1. 単純反射エージェントタイプ
単純反射エージェントタイプは単純なルールに従うAIエージェントです。例えば、工場で製品の状態を読み取り、あらかじめ設定された合格基準に満たないものを製造ラインから外すといった作業が可能です。ただし、このタイプは複雑な業務には対応できないため、イレギュラーな事象にも対応できるような設計が必要です。
2. モデルベース反射エージェントタイプ
モデルベース反射エージェントタイプは、単純反射エージェントタイプに似ています。過去の経験を基に現在の状況を推論し、最適解を求めるAIエージェントです。このタイプを活用することで、需要予測による過剰在庫の防止やリスク管理が可能です。ただし、モデルが複雑になると、対応が難しくなる場合もあります。
3. 目標ベースのエージェントタイプ
目標ベースのエージェントタイプは、決められたルールに沿って動くのではなく、選択肢や行動パターンから最適解を導き出すAIエージェントです。例えば、交通事故を起こさずに運転し、目的地まで到着する自動運転システムがその一例です。ただし、単純反射エージェントタイプよりコストが高く、状況の変化に合わせて目標の見直しができるような運用体制を構築することが求められます。また、目標が自社の方針と合っているかどうかを考えることも必要です。
4. 効用ベースのエージェントタイプ
効用ベースのエージェントタイプは、個人が持つ選好を定量的に可視化して評価するタイプのAIエージェントで、目標ベースのエージェントタイプを進化させたタイプです。例えば、サービス品質の評価や契約の意思決定などに適しています。しかし、このタイプを導入するには、経営戦略や法律などの専門知識が必要になるため、難易度が高いという課題があります。
5. 学習エージェントタイプ
学習エージェントタイプは、過去の経験や環境に基づいて学習し、最適解を導き出すAIエージェントを指します。例えば、顧客の購買履歴からパーソナライズされた商品を展開する場合に有効です。このタイプは単純反射エージェントタイプや目標ベースのエージェントタイプより、イレギュラーな事象にも柔軟に対応できます。ただし、学習するための大量のデータが必要なことやブラックボックス化しやすいことが課題として挙げられます。
6. 階層エージェントタイプ
階層エージェントタイプは「全体的な目標設定」や「具体的なタスクの分割」、「実際に動作させるための制御」など、複数のレイヤーが連携して行うタイプのAIエージェントです。上位レイヤーは全体を把握し、下位レイヤーはそれぞれのタスクに専念できるため、複雑なシステムでも管理しやすいといった特徴があります。またトラブルが生じた場合でも、問題を把握しやすい点が利点です。
AIエージェント活用のメリット

AIエージェントを活用すると次のような3つのメリットがあります。ここでは、詳しく解説します。
1. パフォーマンスの向上
従来の自動化システムでは、業務要求が増えるたびに、手動での設定変更やシステムのアップグレードが必要でした。一方AIエージェントは作業を自動化し、業務効率を下げることなく、作業負担を軽減できます。さらに複数のAIエージェントを組み合わせることで、パフォーマンスをさらに向上させることができます。例えば、あるAIエージェントが顧客データを分析し、別のAIエージェントがスケジュール調整を行うといった使い方も可能です。
2. スピーディーな意思決定と適応能力
AIエージェントは、人間の介入なしにデータを分析・評価し、最適なアクションを実行できます。 スピーディーに応答し、自己学習で改善もできるため、合理的な意思決定ができます。 例えばサプライチェーンの現場においても、出荷遅延や需要予測に関するデータを分析し、配送スケジュールを調整・最適化できます。
3. 複雑なワークフローの自動化
AIエージェントは複雑なワークフローであっても自律的に行動できます。一例を挙げると、複数のデータから分析し、需要予測を立て、ボトルネックを把握し、課題を解決するといった対応が可能です。在庫管理においても、顧客の購入履歴や行動パターンからニーズを予測し、最適な補充を行うことで在庫を効率的に管理できます。
AIエージェントのビジネスでの活用事例
AIエージェントのビジネスでの活用について、次の2つの事例を紹介します。
1. トヨタ自動車の「O-Beyaシステム」
トヨタ自動車は定年退職するベテランエンジニアの知識を継承するため、Microsoft Azure OpenAI Serviceを活用したAIエージェントサービス「O-Beyaシステム」を構築しました。「O-Beyaシステム」では、ベクトル検索(文章の意味的な類似性を判定する技術)やサーバレスプラットフォーム、ハイブリッド検索を組み合わせ、文脈を理解した関連情報を検索することができます。また、複数のAIエージェントが実装され、さまざまな分野を担当しているため、24時間いつでもエンジニアが相談できる仕組みとなっており、約800人のエンジニアがシステムを利用しています。これにより、スピーディーな開発と知識の次世代への継承が可能になりました。
2. KDDIの「A-BOSS (本部長AI)」
KDDIは営業活動のサポートのため、「A-BOSS (本部長AI)」を導入しました。「A-BOSS (本部長AI)」は提案の質向上と抜け漏れチェック、情報収集と知識の補完を行います。また、 AIが事実と異なる情報や根拠のない内容をあたかも真実のように出力してしまうハルシネーションへの対策として、出典元を明記した信頼性の高い情報提供を行っています。これにより、顧客や業界にマッチした商材の提案や必要な情報提供が可能になりました。また、営業提案ストーリーの作成や、提案書の評価まで自動化できます。
今後は複数のAIエージェントを連携させることで、以下のように進化していくと予想されます。
| 種類 | 今後の進化 |
|---|---|
| 事務作業 | ・業務効率化の範囲の拡大 ・人間の関与が最小限に |
| 営業支援 | ・営業活動(データ分析~契約提案)の完全自動化 |
| カスタマーサポート | ・より高度でパーソナライズされた顧客対応 |
FPTは、AIエージェント活用を中心としたポストDXの新しい変革を「AIトランスフォーメーション(AIX)」と定義し、迅速にご支援するために、AI領域における先進的な取り組みを「FPT AIXサービス」として体系化いたしました
AIエージェントの欠点
まず、AIエージェントには倫理的な課題があります。AIエージェントは膨大な情報を分析し、意思決定を行いますが、そのプロセスがブラックボックス化されやすいという問題があります。実際に海外では、採用選考にAIエージェントを活用した結果、特定の属性を持つ人物が不当に候補から除外されたケースが報告されています。このような倫理的な課題を考慮する必要があるでしょう。
また、偏ったデータだけをモデルに学習させると、正確な成果が得られず、特定の情報にバイアスがかかった評価になってしまいます。さらに、AIエージェントの設計は高度な専門性と経験が必要なため、運用の難しさも課題です。こうした課題に対応するためには、社内で人材を育成・確保するだけではなく、外部ベンダーの協力を得ることも必要です。
AIエージェントと切り開くビジネスの未来

2025年はAIが本格的に実用化されると期待されています。しかし、専門家の間でも意見は分かれています。AIエージェントを「関数呼び出しをもつLLM」という現実的な範囲で定義する人々は、すでに日常業務の効率化が進んでいると評価しています。一方、真のAIエージェントは「推論能力と計画能力があり、自律的に行動できるもの」であるべきだと考える人々は、現在の技術はまだその水準に達していないと懐疑的です。
AIエージェントを導入するには、経営戦略やコンプライアンスなどを考慮する必要があります。人間の仕事を完全に代替するのではなく、仕事を補完する存在として位置づけ、責任体制を整備することが重要となります。
まとめ
AIエージェントとは、指示された目標を達成するため、環境の変化に柔軟に対応し、自律的に行動できる「自律型AIシステム」のことです。AIエージェントには6つのタイプがあり、単に指示された作業を行うだけのものから、設定された状況下で自律的に動作できるものまで、幅広い適応範囲があります。AIエージェントを活用することで、スピーディーな意思決定が可能になり、複雑なワークフローの自動化やパフォーマンスの向上が可能です。ただし、意思決定のプロセスはブラックボックス化されやすく、倫理面の問題があります。また、設計には高い専門性と豊富な経験が求められるため、自社で人材確保ができない場合、外部ベンダーへの依頼が有効です。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- AI(人工知能)サービス
- 事例紹介:実践で活きる生成AIソリューション
- FPTがAIプラットフォーム「FleziPT」を発表し、グローバルな企業変革を加速
- FPTは、企業のAIエージェント活用を支援する「FPT AIXサービス」の提供を開始
- 「FPT AI Factory」が世界の最速スーパーコンピュータTOP500に選出 商用クラウドプロバイダーとして日本第1位を獲得
関連ブログ:コラム
- SOCとは?ビジネスにおけるセキュリティ対策の重要性と導入ポイントを解説
- クラウド(Cloud)とは?種類やサービス例をIT初心者にわかりやすく解説
- CRMとは?機能や導入メリット、活用方法と導入事例まで解説
- ランサムウェアとは?被害事例や感染経路、被害防止対策を解説
- ICT(情報通信技術)とは何? IT、IoTとの違いや教育・介護・医療現場での活用例を徹底解説