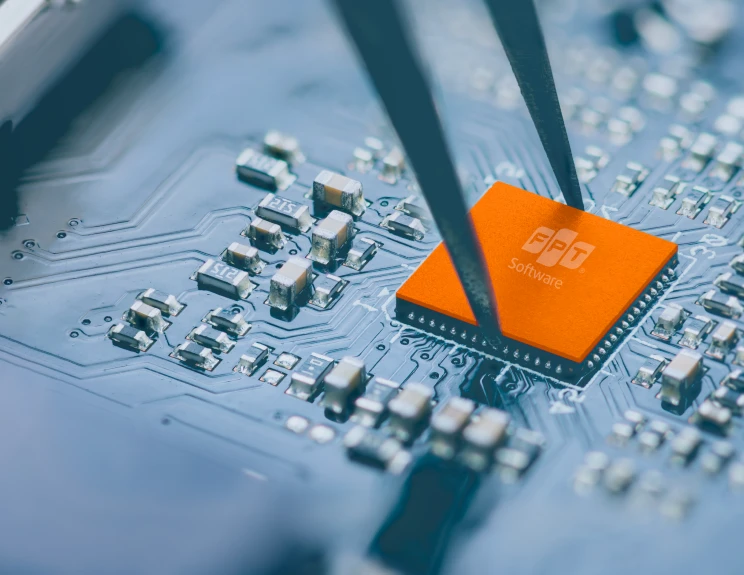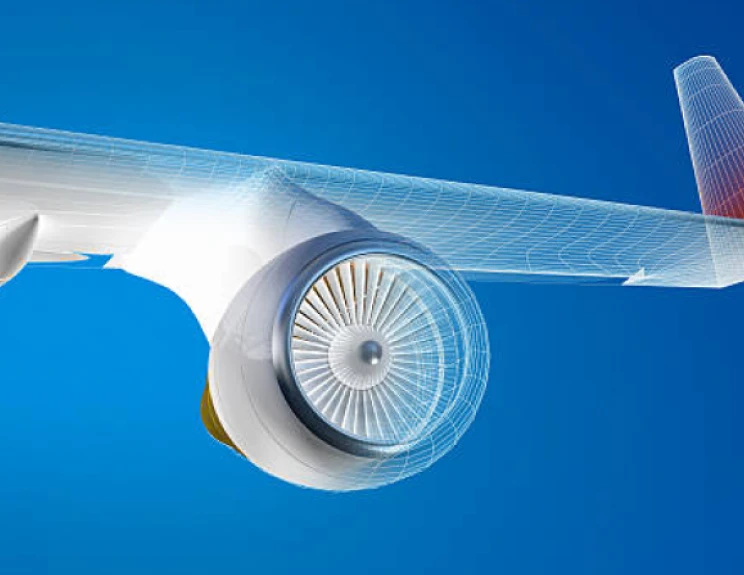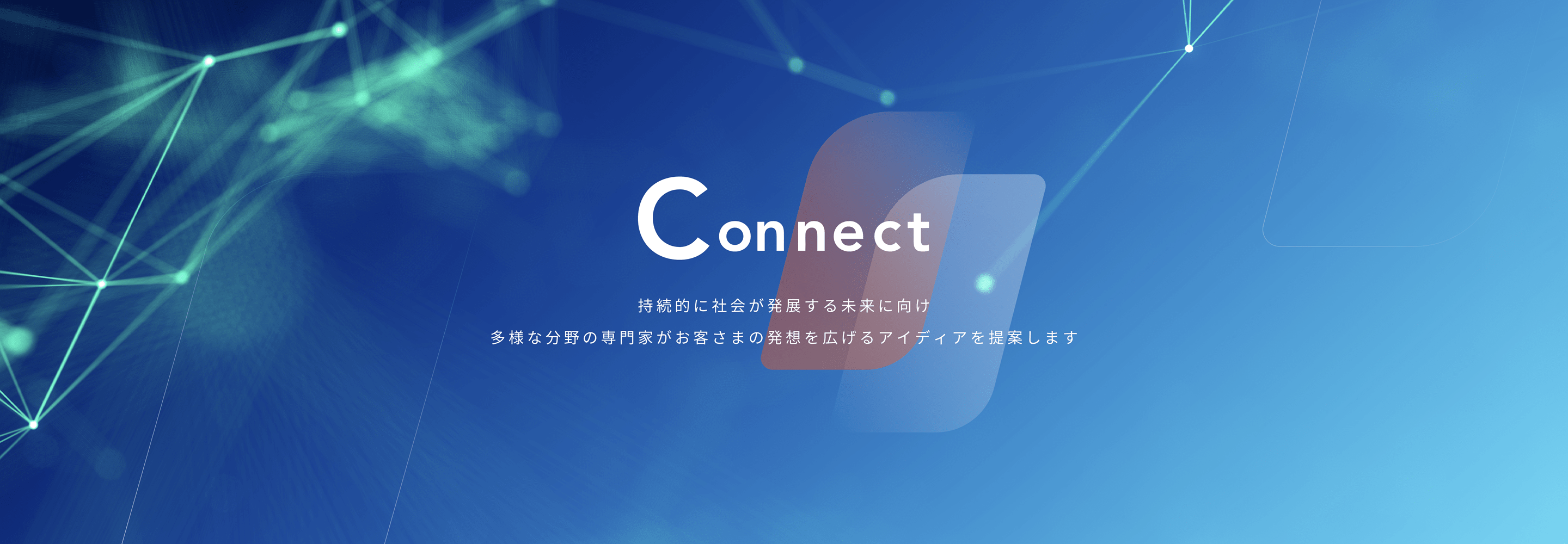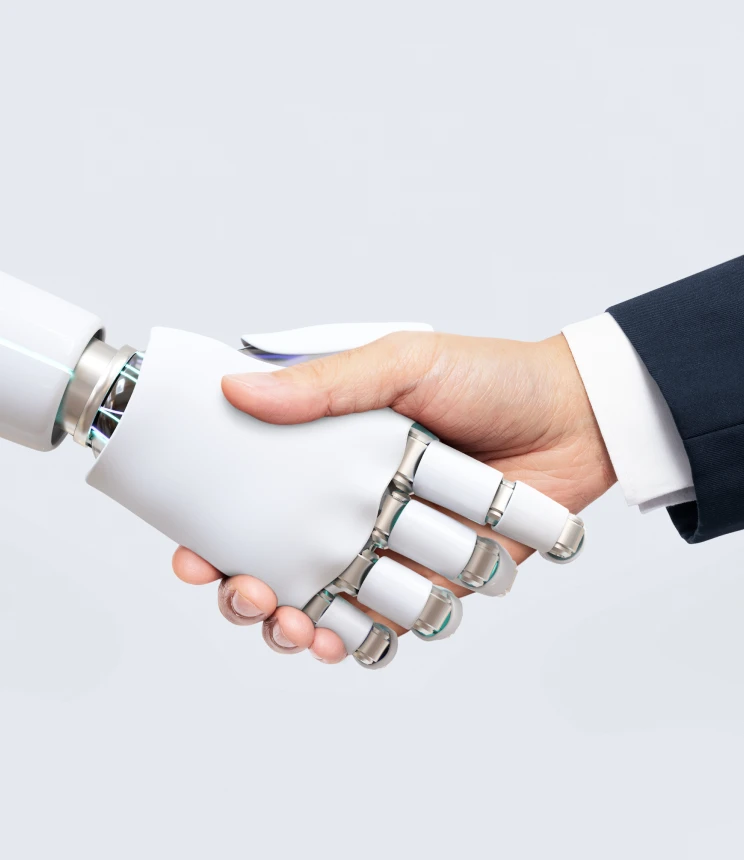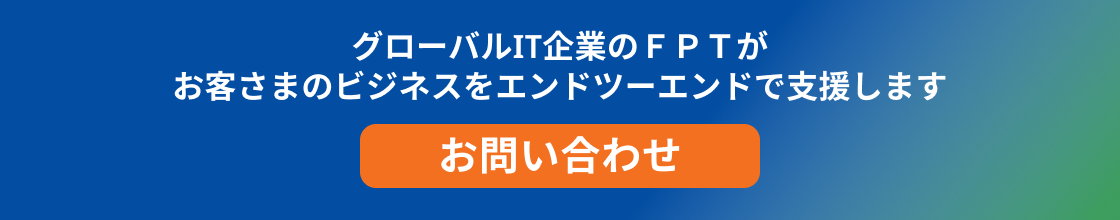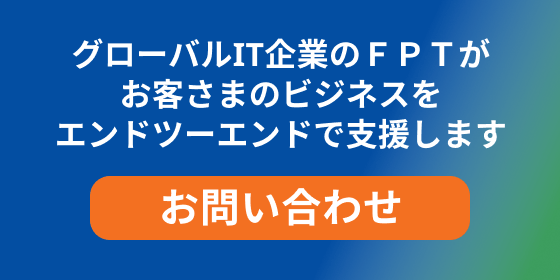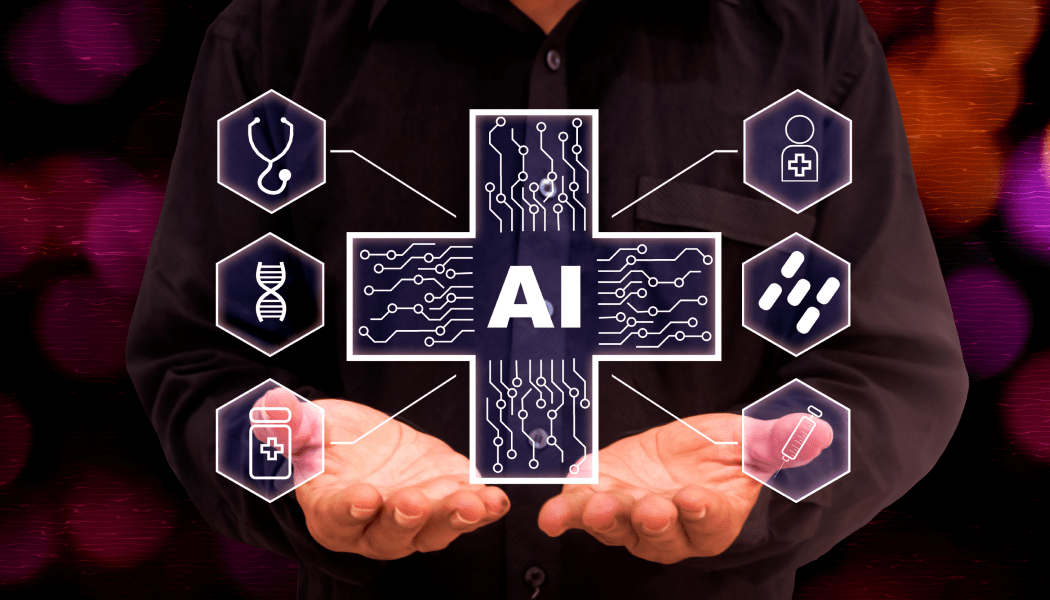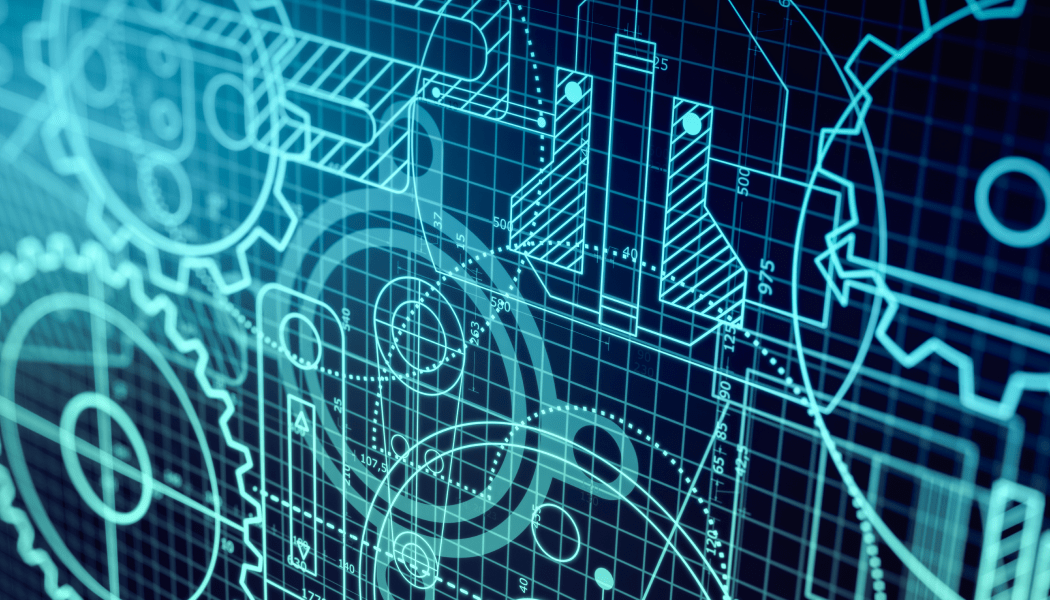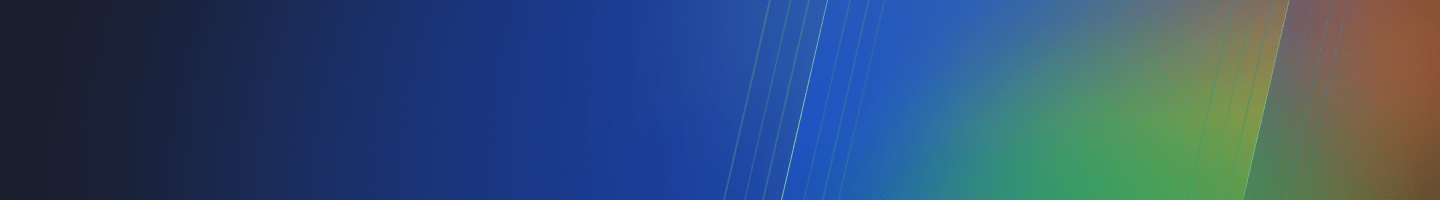生成AIとは
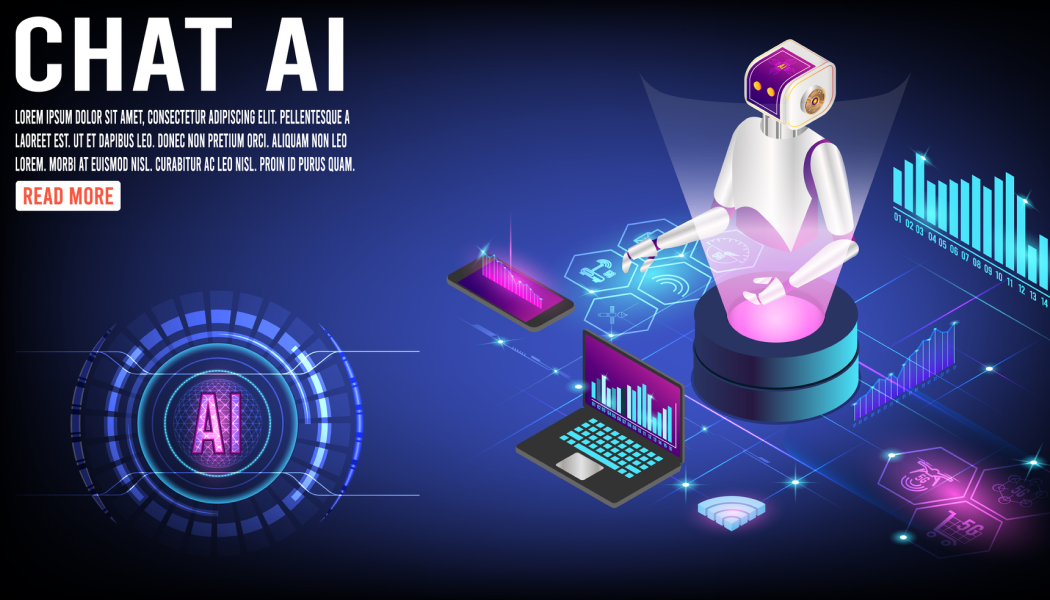
生成AIとは、学習した情報に基づいて、まったく新しいデータや表現を自ら創り出す人工知能のことです。「プロンプト」と呼ばれる、命令や指示を与えるテキスト入力に基づき、文章や画像を自律的に生成します。
分類や予測といったタスクが得意な深層学習(ディープラーニング)と異なり、生成AIは与えられた条件から言葉やイメージなど、有形の対象を“創造”することが可能です。
生成AIの基本的な仕組み
生成AIは、深層学習や強化学習といった従来のAIと同様に、大量のデータからパターンを学習し、新しいデータを出力する点は変わりません。多くの生成AIは、2段階のプロセスでデータを生成するという仕組みを持っています。たとえば敵対的生成ネットワーク(GAN)では、「生成器(Generator)」がデータを作り、「識別器(Discriminator)」が本物との違いを判定する対話的な構造が用いられます。
また拡散モデルは、ノイズを加えてデータを破壊する過程と、それを段階的に復元する過程が対を成しています。こうしたプロセスの相互作用が、高品質な生成を支えています。
生成AIが苦手なこと
生成AIの仕組みは曖昧さや多義性を含んだタスクには強い一方で、唯一の正解が求められるような問題や、厳密な因果関係の検証には現状不向きです。たとえば、数学の証明や精密設計などについては、信頼性の面で課題が残ります。
こうした課題は、生成AIの仕組みに起因しています。生成AIは、出来事が時間の経過とともにランダムに推移していくという「確率過程」を応用しています。たとえば、大規模言語モデル(LLM)では、文脈に応じて次に出る単語の確率分布を推定し、その中で最適と思われる語を順に並べて文章を作り上げます。こうした生成プロセスが、厳密な推論のプロセスとマッチしにくいのです。
生成AIが注目されている背景
生成AIが広く注目を集めるようになったきっかけは、ChatGPTやStable Diffusionといった具体的なツールが一般向けに公開され、誰もが手軽に使えるようになったことです。ChatGPTは、プログラミングの専門知識がなくても、「プロンプト」を通して、AIが文章を生成するという体験を直感的に理解できます。またStable Diffusionは、創作活動が苦手な人でも、アーティストのように高品質な画像を生成することを実感できるので人気があります。
生成AIの進化はビジネスへの応用可能性も広げています。コンテンツ制作や商品説明の自動化、プレゼン資料の下書き、チャットボットによる顧客対応など、幅広い分野での活用が進んでおり、業務効率化や人件費削減、迅速なアウトプットの実現が期待されています。
主な文章生成AIツール
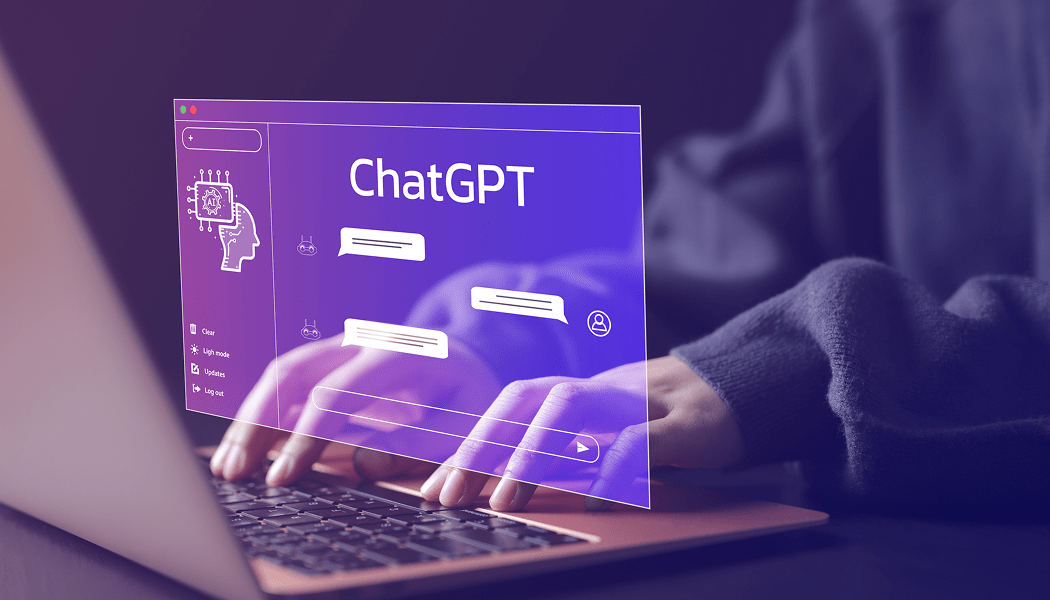
文章生成AIの分野では、ChatGPT、Gemini、Claudeをはじめとする主要なツールが広く利用されています。それぞれのAIには得意分野や操作性の違いがあり、目的や利用者のスキルに応じた選定が重要です。以下では、これらの代表的な生成AIツールの特徴を紹介します。
ChatGPT
ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型の生成AIで、GPTという大規模言語モデルを基にしています。ユーザーが入力するプロンプトに応じて、文章の生成・要約・翻訳・アイデア出しなど多様な出力が可能です。
たとえば「旅行ブログのタイトル案を10個ください」といった指示には箇条書きで提案を返し、「この文章を300字で要約してください」という依頼には要約文を返します。最新のモデルでは、テキストだけでなく画像や音声への対応など、マルチモーダルなツールとして進化し続けています。
Gemini
Geminiは、Googleが提供する生成AIで、従来の「Bard」を進化させた形で登場しました。最大の特徴は、Google検索との深い統合により、引用元のリンクや情報の出典を明示しながら回答できる点にあります。
ChatGPTが文章の自然さや対話の滑らかさに強みを持つのに対し、Geminiはファクトベースでの回答や最新情報の取得に優れ、学術調査や情報収集に適していると評価されています。また、Googleアカウントと連携することで、GmailやGoogleドキュメントなどのデータを活用した補助的な回答も可能です。
Claude
Claudeは、アメリカのスタートアップ企業であるAnthropicが開発した対話型生成AIです。Claudeの最新モデルでは、文脈を長く保持できる200,000トークン規模のコンテキストウィンドウと、多段階推論と豊富なツール連携可能なハイブリッド推論モードを備えていることです。
ハイブリッド推論モードでは、最新の情報に基づいたリアルタイム応答を可能にしています。また、コード生成に特化した「Claude Pro」や、業務現場での効率化を実現する「エージェント機能」なども提供しています。
主な画像生成AIツール
画像生成AIは、テキストからリアルなイラストや写真風の画像を自動で作り出す技術として注目を集めています。たとえば、MidjourneyやAdobe Fireflyなどのツールは高品質な画像を生成できるため、広告・デザイン・コンテンツ制作の現場で活用が進んでいます。以下では、代表的な画像生成AIツールを紹介します。
Stable Diffusion
Stable Diffusionは、Stability AIが開発した画像生成AIです。Stable Diffusionの特長として、オープンソースかつライセンスフリーで公開されている点が挙げられます。ローカル環境にインストールして動作させることができるため、プライバシーの確保やカスタマイズ性の高さを重視するクリエイターや技術者に強く支持されています。
その一方で、無料で商用可能である点が逆にマネタイズの失敗につながったため、MidjourneyやAdobe Fireflyといった商用利用可能な画像生成AIの後塵を拝すようになってきています。
Midjourney
Midjourneyは、2022年に登場した画像生成AIのなかでも、完成度の高いビジュアル表現で注目を集めるツールです。写実的な描写だけでなく、独自の芸術性や構図センスを備えた出力が得られる点で、Stable Diffusionなどの第1世代的な画像生成AIとは一線を画しています。
その品質の高さから、広告、出版、ブランディングといった商用分野でも実用に耐える出力が可能で、実際にプロの制作現場でも使われ始めています。その一方で、企業の規模に応じてライセンス料が高額になるというデメリットもあります。
FLUX.1 Kontext
FLUX.1 Kontext(Black Forest Labs)は、2025年5月にリリースされた生成・編集対応の画像生成AIで、Stable Diffusionの元開発メンバーによって立ち上げられたプロジェクトです。
最大の特徴は「インコンテキスト編集」と呼ばれる機能で、テキストと画像を同時にプロンプトとして指定し、画像中の特定の要素のみを自然に編集・再生成できます。また、従来のStable Diffusionがライセンスフリーで拡散された反省を活かし、FLUX.1は明確な商用ライセンスと料金体系を持つ有償モデルとして設計されました。
Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、Adobe Creative Cloudに統合された生成AIツールで、テキストから画像・動画・ベクターグラフィックを直感的に生成できるのが特長です。最新のモデルでは、より写実的で高解像度な画像出力が可能となっています。
PhotoshopやIllustrator、ExpressといったAdobe製品にシームレスに組み込まれており、従来のワークフローを壊すことなくAIによる補助が行える点が魅力です。また、商用利用を前提とした著作権対応であり、Fireflyで生成されたコンテンツはAdobeが権利面を保証しており、商業広告・商品デザインなどに安心して活用できます。
そのほかの生成AI
生成AIは文章や画像にとどまらず、動画や音声、さらにはプログラミングコードの自動生成といった分野にも広がりを見せています。ここでは、それぞれのジャンルで注目されている生成AIの概要や特長について紹介します。
動画生成AI
動画生成AIは、テキストや画像、音声などをもとに、数秒〜十数秒程度の短い映像を自動で生成する技術です。
たとえばRunwayは、「都市を歩く女性」、「夕暮れのビーチに立つ犬」といった短いテキストを入力するだけで、数秒ほどのアニメーション風の映像や音声、3Dなどを数分以内に生成できます。またPikaはシンプルなユーザーインタフェースで初心者でも活用可能なだけでなく、「Pikaffect」と呼ばれる特殊効果の付いた動画を画像から生成可能です。
音声生成AI
音声生成AIは、文章を入力するだけで、人間の声に近いナレーションや会話音声を自動生成できる技術です。たとえば Amazon Polly は、クラウドベースで利用可能な音声合成サービスで、多言語・多声種に対応し、感情表現や話速・抑揚の制御が可能です。
AWSとの親和性が高く、コールセンター音声やナビゲーション音声など、ビジネス用途での活用も進んでいます。また VALL-E X は、マイクロソフトが開発した次世代の音声生成AIです。わずか数秒の音声サンプルから話者の特徴を模倣し、イントネーションや話者固有の癖を再現する能力が高いという特長があります。
プログラミングコード生成AI
コード生成AIは、自然言語の指示やコメントに従って、プログラムコードを自動生成・補完するツール群です。たとえば GitHub Copilot は、Visual Studio Code などに統合でき、関数の自動補完やコメントからコードを提案するといった定型作業の高速化に優れています。そのため、初学者から中級者まで幅広く支持されています。
また Cursor は、チャット型プロンプトとコードエディタを統合したIDE(統合開発環境)として注目されており、コードの文脈を保持しながら、より高度なリファクタリングや構造設計の支援にも対応しています。
生成AIの効果的な使い方

生成AIを最大限に活用するには、目的に合ったツールの選定と、適切なプロンプト設計、そして人間によるチェックや編集のプロセスが重要です。以下では、具体的な活用事例を3つ紹介します。いずれも、AIの能力と人間の判断を組み合わせることで、高い成果を得ている点が共通しています。
企画・アイデア出しの補助
生成AIは、ブレインストーミングや企画立案の初期段階で有効に活用できます。たとえば、商品ネーミングや記事の構成案、広告コピーの案出しなど、人間の発想を広げるヒントとして役立ちます。多様な観点から提案を出してくれるため、思考の幅を広げたいときに重宝します。
マニュアル・報告書の自動作成
業務の定型文書やレポート作成には、文章生成AIが大きな効果を発揮します。たとえば、議事録の要約や操作マニュアルのドラフト作成など、時間のかかる業務を効率化できます。人間が内容を確認・修正する工程を追加することで、十分な品質を担保しつつ業務時間を短縮できます。
業務効率化の支援ツールとして活用
生成AIは、日常業務のなかで繰り返される定型作業や、資料作成・メール文面の下書きといった「頭を使うけれど単調な作業」を効率化する手段として有効です。たとえば、FAQの作成、営業メールの草案作成などを短時間で行えるため、業務スピードの向上に直結します。また、社内コミュニケーションをチャットボットで代用することで、省人化にも役立ちます。
高性能GPUクラウドと統合型AI開発プラットフォーム、そして即戦力となる20以上の生成AIアプリケーションを通じて、企業の生成AI導入と業務変革を支援します
生成AIの活用事例
1. 伊藤忠商事
伊藤忠商事は、ビジネスにおける生成AIの活用を推進しており、その一環としてFPTと多岐にわたる分野で協業しています。
同社のAIプロジェクトの成功には、アジリティ、拡張性、そして高度なセキュリティが重要な鍵となります。FPTは、AIのエキスパートによる技術支援体制と、これら3つの重要な要素を包括的に提供することで、同社のプロジェクトを強力にサポートしています。この協業により、実践で活きるAIソリューションの創出が加速し、伊藤忠商事のビジネス価値向上に貢献しています。
2. ベトナム金融機関
ベトナムの金融機関は、顧客体験の向上と業務効率化を実現するため、FPTの生成AIソリューションを導入しました。この仕組みでは、大規模言語モデル(LLM)などの高度なAI技術を活用し、情報照会やカードのロック・有効化、顧客調査といった、シンプルながらも重要なタスクをAIが担当します。これにより、担当者はより付加価値の高い顧客対応に注力できるようになりました。
その結果、運用コストを50%削減し、通話成功率は98%を達成。さらに、テレセールスによる収益が20%増加するなど、目覚ましい成果を上げています。この変革は、コールセンターを単なる「コストセンター」から、積極的に利益を生み出す「プロフィットセンター」への転換を可能にしました。
3. FPTソフトウェア
ソフトウェア開発におけるAI活用は世界的に拡大しており、このような背景のもと、FPTは開発者の生産性とワークエクスペリエンス向上を目的に、厳格なセキュリティ要件を満たす社内向け生成AIツール「CodeVista」を開発しました。
CodeVistaは、コードの構造や依存関係を正確に把握する機能や、検索・編集といったタスクを自律的に実行するAIエージェントを搭載しています。さらに、外部ドキュメントやオンラインリソースから関連情報を取り込むことで、文脈に即した高精度なサポートを実現します。
これらの多角的な機能により、ソフトウェア開発ライフサイクル全体の最適化とチームの意思決定を支援し、生産性の向上に貢献しています。
生成AIを正しく使うための注意点
生成AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると法的リスクや情報漏洩など重大なトラブルを招く恐れがあります。とくに、
- 著作権
- 機密データの取り扱い
- 使用しているAIモデルの特性や制限
など、利用者が事前に把握すべきポイントがいくつかあります。
著作権
生成AIの著作権に関しては、各ツールの提供元が利用規約やライセンスで明確な指針を示しており、たとえばChatGPTやStable Diffusionでは、ユーザーが生成したコンテンツを自由に使用できると明記されています。
ただし、学習に使われたデータに既存の著作物が含まれているケースもあり、元の作品に酷似した出力をそのまま使うと著作権侵害となる可能性があります。デジタル庁が「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」※を公表しているので、商用利用を行う際にはこうした指針を確認したうえで、リスクを把握した運用が求められます。
データ流出
生成AIの多くはクラウド上で動作し、ユーザーが入力したプロンプトはサービス提供者のサーバーに送信されます。とくに注意すべきなのは、入力内容が再学習に使われたり、生成物の形で第三者に類似情報が出力されたりする可能性がある点です。
たとえばChatGPTの有料プランでは入力データの利用を無効化できる仕組みが用意されています。業務での利用を考える場合は、利用する生成AIツールのプライバシーポリシーやプロンプトの取り扱いについて事前に確認しましょう。
モデルやツールの確認
生成AIツールを利用する際には、その背後にあるモデルや提供元の信頼性、そして用途との適合性を慎重に見極める必要があります。たとえば、無料プランでは簡易的なモデルしか使えず業務利用には不向きな一方、ChatGPT Proにように高性能すぎて軽い用途には過剰なケースもあります。
また、Deepseekのような中国系の一部サービスでは、利用者の入力内容が国内外の監視対象になるリスクも一部で指摘されており、セキュリティやデータ主権の観点でも慎重な選定が必要です。
生成AIの将来性

生成AIは、単なるツールから「共創のパートナー」へと進化しつつあります。教育、医療、ビジネス、ものづくりなど、さまざまな分野での活用が広がる一方で、技術的課題も依然として残されており、生成AIを適切に活用するための下地作りが重要な課題となっています。
生成AIの現状の課題とリスク
生成AIは一見便利なツールに見えますが、業務への本格的な導入を検討する際には、いくつもの課題に直面します。代表的なのが、事実に基づかない出力をもっともらしく生成してしまう「ハルシネーション」です。
AIは情報の正誤を判断する仕組みを持たないため、誤った情報が生成されてしまうことがあります。その結果、人間による事後修正が必要となり、かえって業務効率を低下させる場合があるのです。さらに、ユーザーが誤った前提を含むプロンプトを入力すると、出力全体が破綻する可能性もあり、AI自体の精度だけでなく、使い方の精度も重要な要素となります。
生成AIとの共創の未来に求められること
生成AIと共に価値を生み出す未来においては、技術そのものよりも、それをどう受け入れ、使いこなすかという人間側の姿勢と柔軟性が問われます。AIは月単位で進化しており、今日習得したツールや活用法が、すぐに通用しなくなることも珍しくありません。そのため、「変化に適応し続ける力」や「進化を前向きに試す姿勢」が今後の鍵となります。
生成AIを活用する組織の側面から見ると、生成AIの導入や活用を「一部の先進的な部署や個人に委ねる」のではなく、組織として学び合い、柔軟に使いこなす文化を醸成することが重要になってくるでしょう。
まとめ
生成AIは、文章・画像・音声・動画・コードなど、さまざまなコンテンツを自律的に生み出す画期的な技術として、私たちの暮らしや仕事に急速に入り込みつつあります。業務効率の向上や創作支援といった恩恵は大きい一方で、著作権や情報漏洩、誤情報といったリスクにも注意が必要です。
何より重要なのは、こうした強力なツールに振り回されることなく、主体的に使いこなす姿勢です。AIを過信せず、人間の判断を中心に据えた活用を心がけることが、生成AIと共にある社会の健全な発展につながります。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- AI(人工知能)サービス
- FPTがAIプラットフォーム「FleziPT」を発表し、グローバルな企業変革を加速
- FPTがデータブリックスとセレクトティアパートナーシップを締結し地域およびグローバルのデータとAI機能を強化
- 「FPT AI Factory」が世界の最速スーパーコンピュータTOP500に選出 商用クラウドプロバイダーとして日本第1位を獲得
関連ブログ:コラム
- CRMとは?機能や導入メリット、活用方法と導入事例まで解説
- ランサムウェアとは?被害事例や感染経路、被害防止対策を解説
- ICT(情報通信技術)とは何? IT、IoTとの違いや教育・介護・医療現場での活用例を徹底解説
- OutSystems(アウトシステムズ)とは?メリット・デメリットや将来性、導入方法まで解説
- AMSとは?メリットやサービス内容、具体的な活用事例を解説