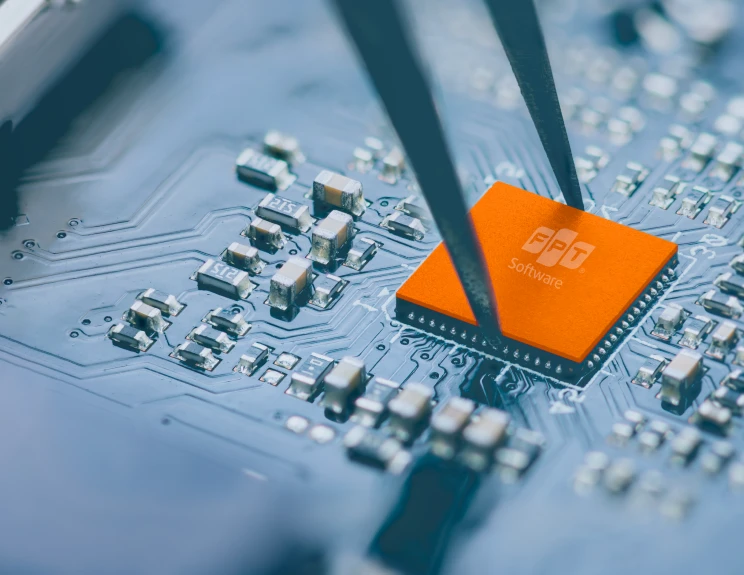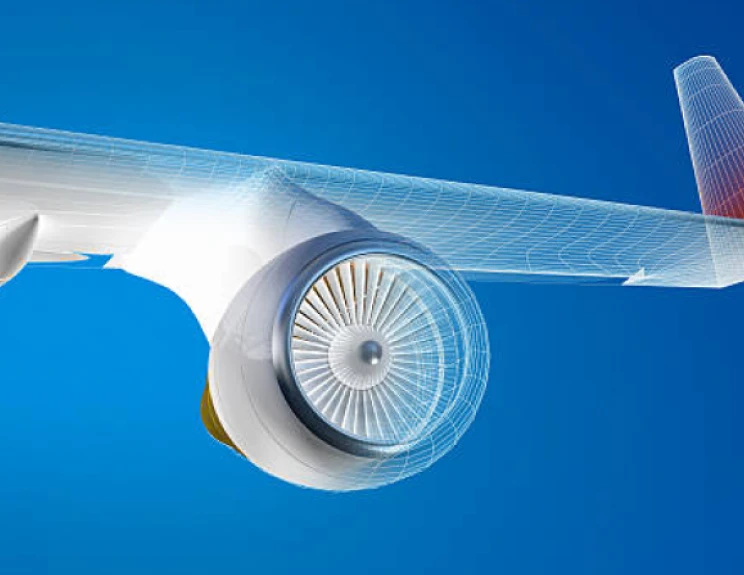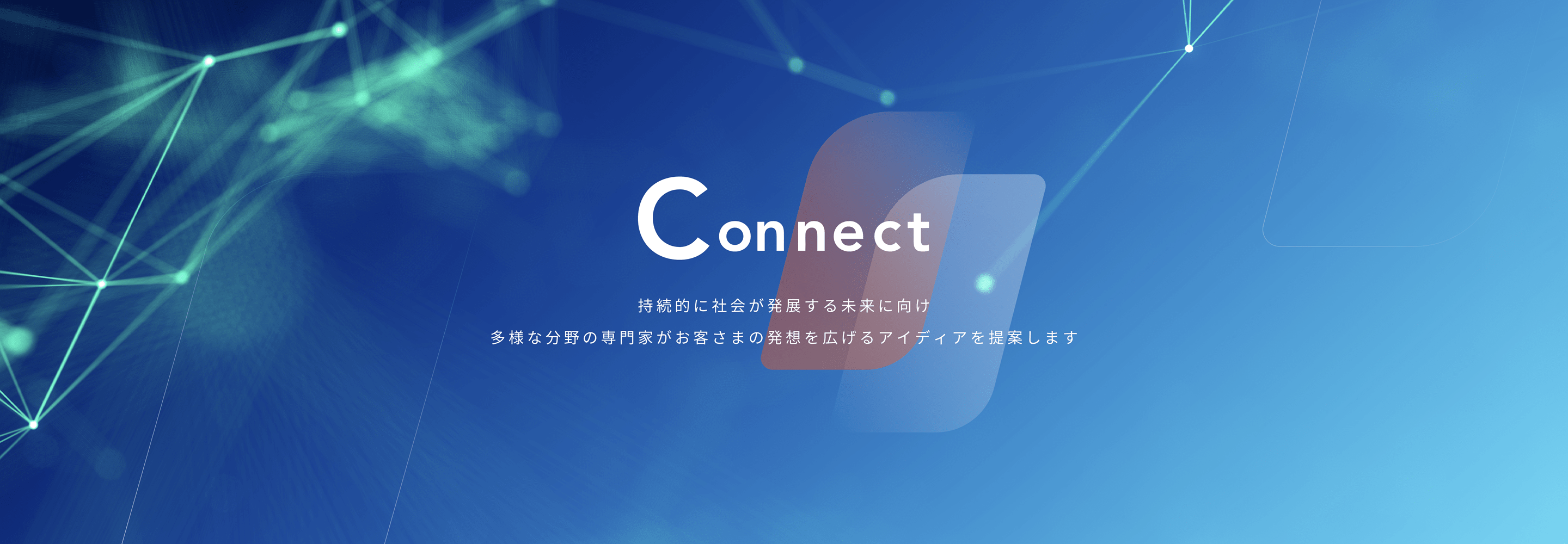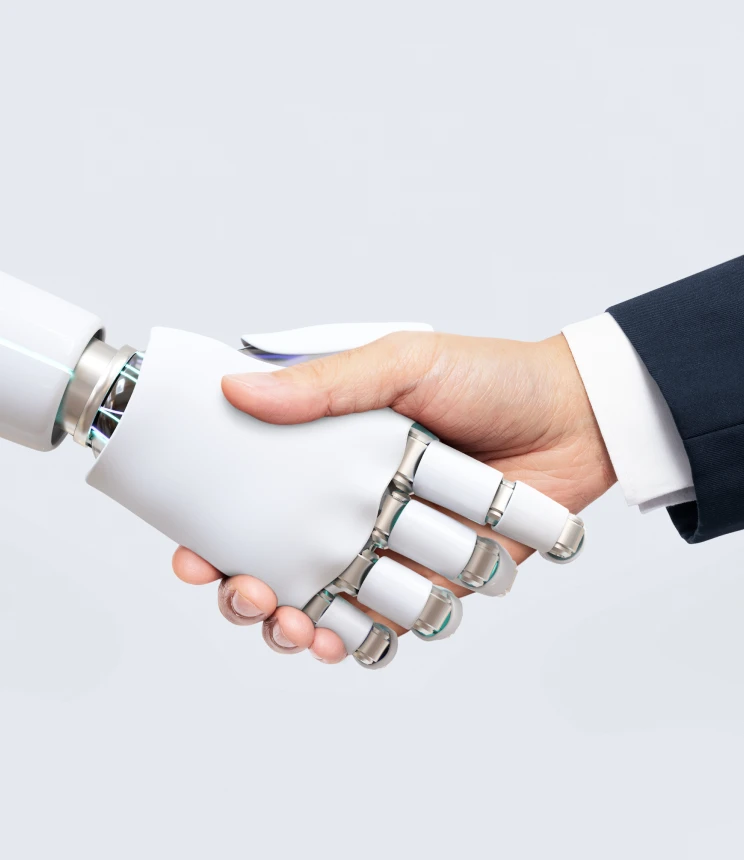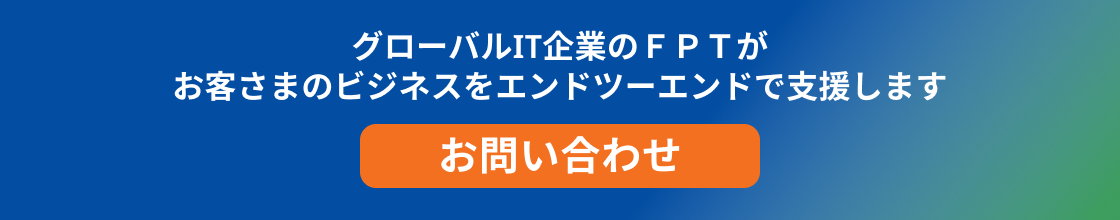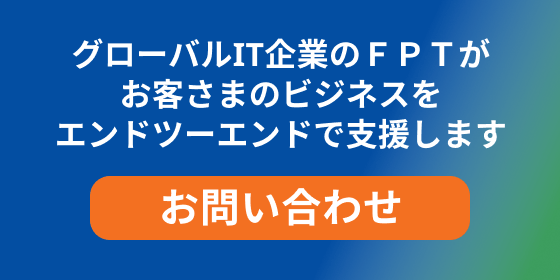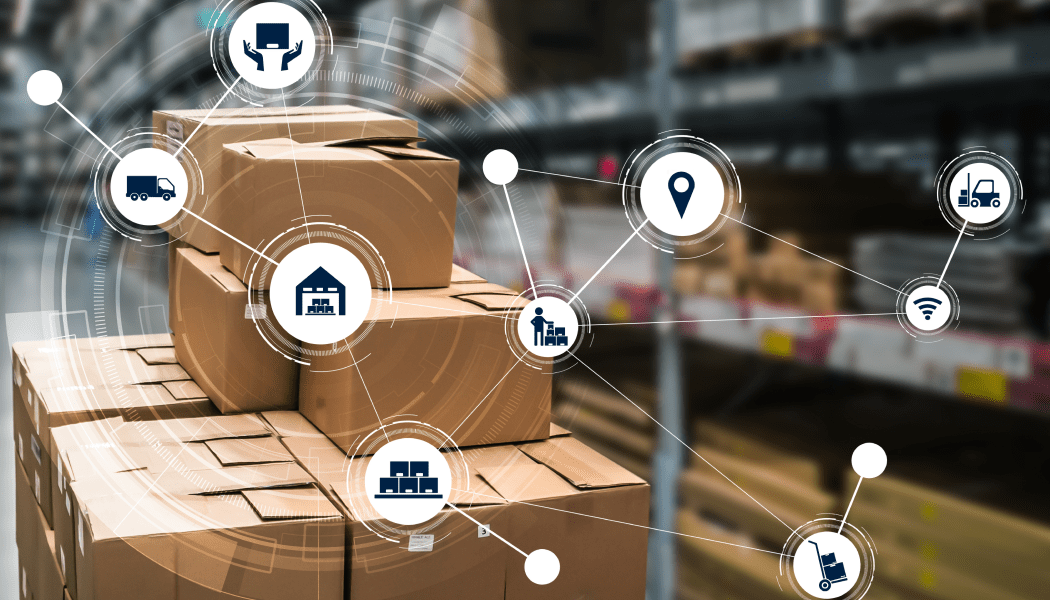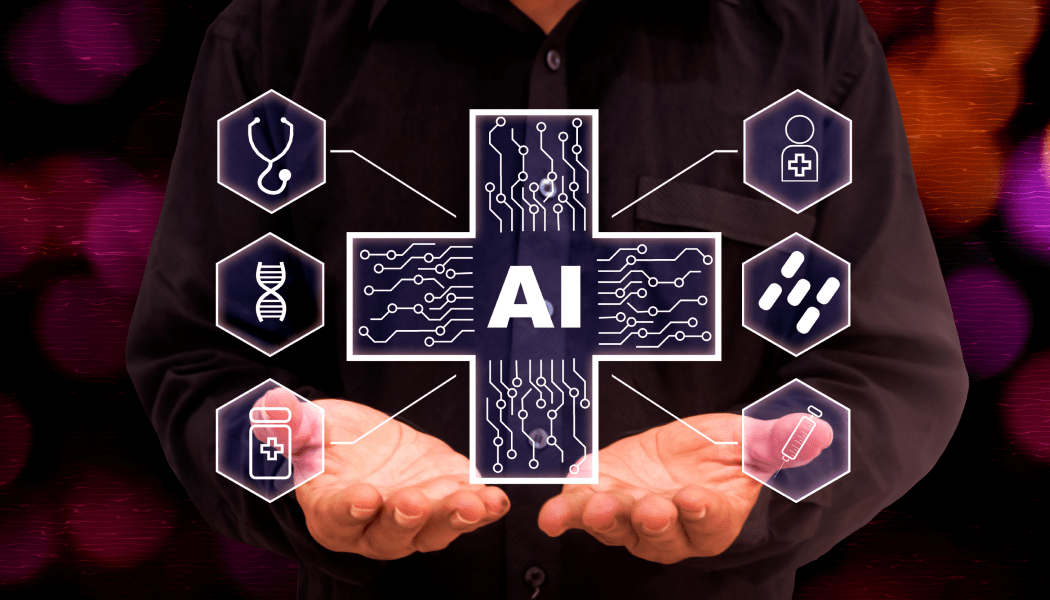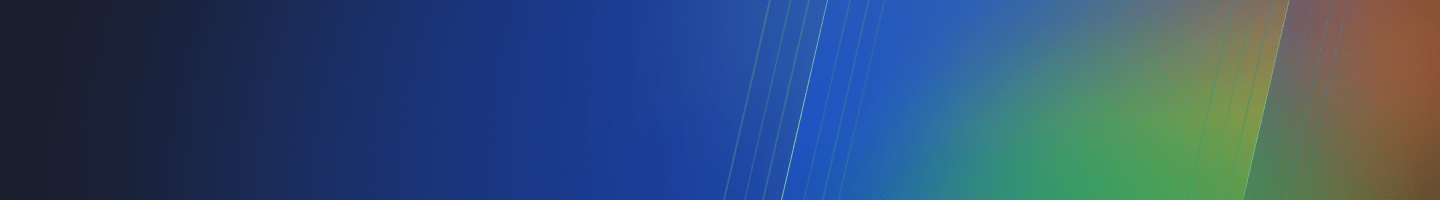目次
ICT(情報通信技術)とは

ICT(Information and Communication Technology)とは、「情報の処理」と「通信手段」を組み合わせた技術の総称です。総務省では以下のように定義されています。
“Information and Communication Technologyの略。
情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称。”
つまりICTとは、人や組織が情報をやり取りし、活用するための仕組みや技術全体を指します。代表的な例としては、パソコンやスマートフォン、インターネット、メール、クラウドサービスなどが挙げられます。例えば、遠くにいる相手と映像や音声で会話をしたり、業務データをネットワーク経由で共有したりする場面を思い浮かべると、ICTの活用イメージがつかみやすいでしょう。社会のデジタル化が進む今、ICTは日常生活やビジネスのあらゆるシーンで重要な役割を担っています。情報の伝達や管理だけではなく、効率化や新しい働き方の実現にも欠かせない存在となったのです。
ICT(情報通信技術)とIT、IoTの違い
ICTと似た用語としてITやIoTがあります。これらの用語にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、それぞれの意味と特徴について見ていきましょう。
ICTとITの違い
ICTとITはどちらも情報を扱う技術ですが、含まれる範囲に違いがあります。IT(Information Technology)は、コンピュータやソフトウェア、ハードウェアなど、情報処理や保存・分析などの技術全般を指す言葉です。例えば、データベースの活用や業務システムの活用などはITにあたります。
一方でICTは、ITで処理された情報を「通信」でつなぎ、活用の幅を広げる概念です。例えば、メールやチャット、Web会議やSNSのような双方向のコミュニケーションを可能にします。ICTは、ITよりもビジネスの現場や日常生活の中で直接活用される場面が多いと言えるでしょう。人と人、組織と組織のつながりや連携を強化する点において、ICTならではの特徴が発揮されます。
ICTという用語の定着について、総務省では以下のように述べています。
“日本では同様の言葉としてIT(Information Technology:情報技術)の方が普及していたが、国際的にはICTがよく用いられ、近年日本でも定着しつつある。”
ICTとIoTの違い
IoTは「Internet of Things」の略称で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。具体的には、身の回りの機器や家電、センサーなどがインターネットを通じてつながる仕組みです。これにより、機械や設備が自動でデータをやり取りし、人が直接機器を操作しなくても状況を把握したり、遠隔制御したりできるようになりました。IoTは主に、個々のモノがネットワークで結びつく点が特徴です。
一方、ICTはIoTの仕組みも含め、情報の伝達や活用を支える幅広い技術を指します。つまり、IoTはICTの一部であり、IoTが現場のデータ収集や制御を担い、ICTがそのデータを人や社会全体で活用する役割を果たしています。現代では両者が連動して使われる場面が増えており、ICTはより広い意味を持つ言葉となっています。
ICTが注目される背景
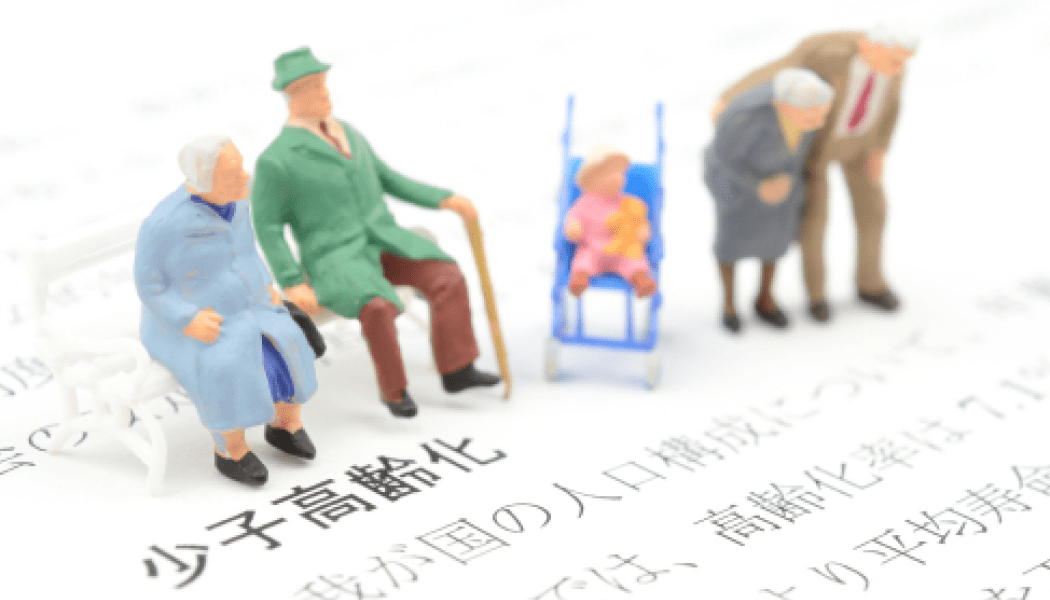
現代社会でICTが注目される背景には、社会構造や働き方の大きな変化があります。ここでは、特に日本でICTが求められている要因について見ていきましょう。
少子高齢化による労働力不足
日本では、少子高齢化が加速しています。総人口に占める65歳以上の割合は2025年で約30%、2060年には約40%に達すると見られており、若い世代の労働力が減少しています。人手不足が深刻化する中、企業は限られた人数で業務を維持・拡大していく必要があります。こうした課題に対し、ICTは大きな力を発揮します。例えば、遠隔地からの業務参加やデータの一元管理など、ICTの活用は人手不足対策として欠かせない存在となりました。今後も人口構造の変化に伴い、ICTの導入ニーズはさらに高まるでしょう。
働き方改革・生産性向上
働き方改革やコロナ禍により、企業や自治体では多様な働き方と業務効率化が加速しました。テレワークの普及により、場所や時間にとらわれない働き方が一般化し、こうした柔軟な働き方を支える基盤としてICTの重要性が高まっています。例えば、オンライン会議やグループウェアを活用すれば、物理的に離れたチームでも円滑なコミュニケーションができます。さらに、業務の自動化やデジタル文書の活用によって、繰り返し作業の負担を軽減することも可能です。ICTの導入は、単なる効率化だけではなく、従業員一人ひとりの働きやすさや企業の競争力強化に直結するのです。生産性を高める手段として、多くの現場でICTは広がっています。
企業がICTを強化することで期待できる効果・メリット
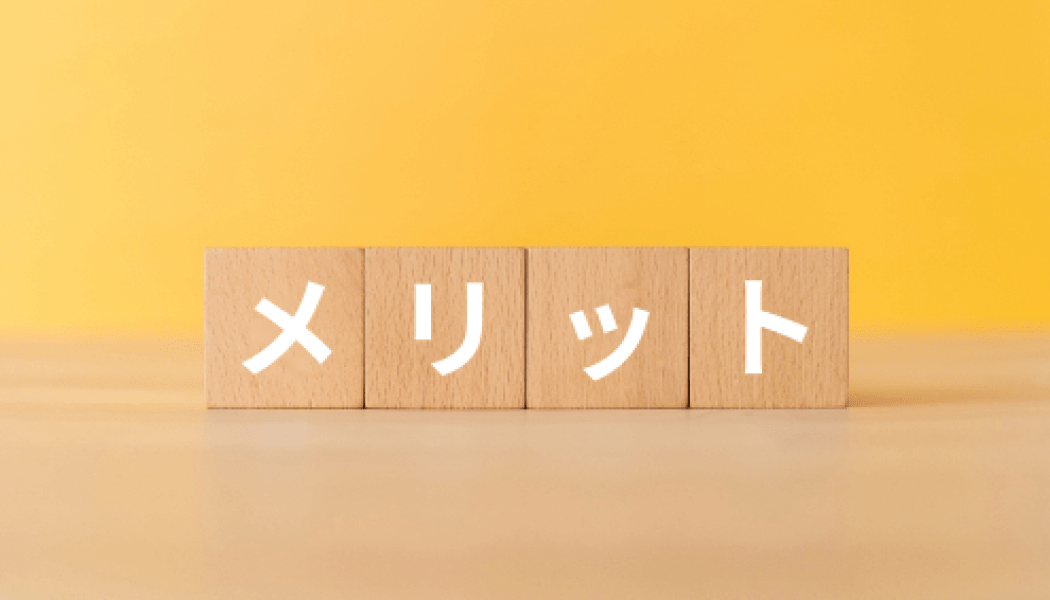
ICTの導入や強化は、企業にさまざまな変化をもたらします。ここでは、現場の課題解決や新たな価値創出など、具体的な効果やメリットを見ていきましょう。
業務効率の向上
ICTの導入により、日々の定型作業の負担を大幅に軽減できます。例えば、スマートデバイスの活用や業務の自動化です。業務日報や経費精算をスマートフォンで撮影するだけで自動登録できる仕組みを導入すれば、これまで1時間かかっていた作業が10分程度で完了することもあります。最近では、タブレットやスマートフォンだけで勤怠管理や会議スケジュールの調整を行える職場も増えています。このように、身近なデバイスを活用して情報共有を自動化する仕組みは、業務効率の向上と正確な情報伝達を両立させる手段となっています。
新たなサービス・ビジネスの創出
ICTは、今ある仕事の負担を軽減するだけではなく、組織の事業そのものを新しくする力をもっています。例えば、健康診断の予約をWebで受け付ける仕組みを導入すれば、クリニックの受付業務の負担を減らせるだけでなく、新たな顧客の獲得にもつながる可能性があります。POSデータを分析して、商品の仕入れや販促方法を地域ごとに変化させた小売業が、売上増加に成功する可能性もあります。また、ICTで顧客データや業務履歴を蓄積すれば、AIによる自動分析や新サービスの土台作りにも結びつきます。変化のスピードが速い現代こそ、ICTの活用が「新しい稼ぐ力」になるのです。
人材育成・働きやすい環境の実現
「研修を受けたくても現地まで行けない」「新しい業務を教えてくれる人が近くにいない」などの悩みは、多くの職場に共通しています。ICTの活用は、このような状況の改善にもつながるものです。例えば、全国に事業所を展開する企業がオンライン研修を導入すれば、場所に関係なく平等にスキルアップの機会を提供でき、同時に出張費の削減にもつながります。テレワークと研修を組み合わせれば、子育てや介護をしながら研修を受けて業務を遂行できる環境を整えられます。ICTは効率化だけではなく、人が成長しやすい職場を実現する後押しになるのです。
ICTの活用例
ICTは業種を問わず幅広い現場で活用されています。特に、教育や医療、介護といった分野では、現場特有の課題解決に役立てられているのです。ここでは、それぞれの現場でどのようにICTが使われているのかを見ていきましょう。
教育現場:オンライン授業と個別学習支援
ICTは教育現場でも効果的に活用されています。従来の授業は、全員が同じ教材を使い、同じペースで進めるスタイルでしたが、学力差や得意・不得意が浮き彫りになりやすいという課題がありました。そこで、ICTを導入することで、遠隔地からのオンライン授業への参加や、生徒一人ひとりの理解度に応じた学習の進行が可能になります。
具体的には、タブレット端末を活用した教材配信、リアルタイムの小テスト、課題の難易度を調整する仕組みなどが導入されつつあります。また、保護者との連絡もアプリを通じてスムーズに行えるようになり、ICTは教育現場のインフラを大きく変えつつあります。
医療現場:遠隔診療と電子カルテ管理
高齢化や都市部への人口集中が進む現代、通院が困難な患者の増加や医師不足に悩む地域があります。こうした状況では、ICTを活用した遠隔診療が重要な選択肢となっています。例えば、医師と患者が画面越しにやり取りできる仕組みは、診療までの待ち時間や交通費の負担も削減します。また、紙カルテから電子カルテへの移行も進み、検査結果や処方履歴を院内外で共有しやすくなると、医療スタッフが端末からすぐに情報を確認できます。ICT導入は、医療現場の働き方や患者サービスの質を大きく変えることが可能なのです。
介護現場:見守りシステムと記録の電子化
介護の現場では、利用者の安全確保とスタッフの負担軽減の両立が大きな課題の一つです。この課題を解決するのが、ICTを用いた見守りシステムの導入です。施設内の各部屋の状況をリアルタイムで把握して、利用者の転倒や体調異変を早期に発見します。例えば、センサーが異常を検知すると、担当者のスマートフォンに通知が届き、夜間も利用者から目が離せないといったスタッフの業務負担を軽減できます。また、介護記録やケアプランの電子化が進めば、手書き作業による記入ミスや書き込み時間を削減できます。ICTは、利用者の安心とスタッフの働きやすさを向上させる手段になるのです。
ICTの活用は幅広い
ICTの活用は、ほかにも土木・農業・観光など幅広い分野で進んでいます。土木では、ドローンや3D測量機器を使った「ICT施工」により、作業効率と安全性が向上。農業では、ICTやロボット技術の導入で省力化や自動化を進め、高品質な生産を目指す「スマート農業」が広がっています。さらに観光では、AR・VR・AI・IoTなどの技術を活用し、観光地の魅力を効果的に引き出すことで、顧客満足度の向上につながっています。
FPTのインフラ管理サービスは、数多くの企業とのパートナーシップを通じて、豊富なエンジニアリソースと実績に基づき、幅広いインフラニーズにお応えします
ICTを推進・強化する際のポイント
ICTを現場に根付かせ、最大の効果を生み出すにはシステム導入だけでは不十分です。導入前後の準備や運用の工夫をしっかりと考えておかなければなりません。ここでは、ICTを推進・強化する際のポイントについて見ていきましょう。
現場の声を生かす体制づくり
ICT導入を成功させるには、現場視点の反映が不可欠です。トップダウンで導入を進めると、現場の実情とのズレにより、形だけの仕組みになってしまうことがあります。現場スタッフが「使いにくい」「役に立たない」と感じれば、ICTは活用されず、成果も得られません。
そのため、導入にあたっては現場の課題や困りごとを丁寧にヒアリングし、利用者の視点に立ったシステム設計や運用ルールを整えることが重要です。あわせて、現場にリーダーやICT担当者を置き、問い合わせや改善要望を受け付ける体制を整えることで、運用開始後の混乱を最小限に抑えることができます。
ICTリテラシー格差への対応
ICTを導入した現場では、スタッフのスキルや慣れにばらつきが生じます。例えば、デジタル操作に慣れている若手と、紙の伝票や電話が中心だったベテランの間でICTリテラシーの格差が広がってしまうケースも少なくありません。せっかくICTを導入しても「できる人しか使いこなせない仕組み」になりかねないのです。そのため、ICT導入には実践的な研修の機会が不可欠です。また、日常的なフォロー体制を整え、「一人で悩まなくてもよい」「いつでも質問できる」といった安心感のある雰囲気を醸成することで、スタッフ間にも信頼と安心が広がります。
セキュリティ対策と運用管理
ICTを使う場合、どうしても情報漏えいや外部からの不正アクセスといったリスクが生じます。そのため、ICTの活用においては、厳重なセキュリティ対策と適切な運用管理が欠かせません。システム導入時には、アクセス権限の設定やデータの暗号化といった基本対策に加え、業務端末やネットワークの定期的な見直し、不正ログインの監視など、複数の防御策を組み合わせて対処することが重要です。また、従業員向けのセキュリティ研修を定期的に実施し、仮にトラブルが起こった際に迅速に対応するためのマニュアルを整えておくことが大切です。ICTの利便性を保ちながらリスクに対応しましょう。
開発体制の強化と外部リソース活用
ICTの導入・推進には、十分な開発リソースの確保が欠かせません。自社だけで人材や知見をまかなうのが難しい場合は、外部パートナーとの連携や委託を検討しましょう。オフショア開発も選択肢の一つです。海外拠点の専門人材を活用することで、効率的なシステム開発や運用が可能となり、コストの最適化も検討できます。自社の状況に応じて外部リソースを柔軟に取り入れることで、現場の課題解決やICT推進を着実に進めることができます。
ICTに関するよくある質問

ICTとDXの違いは?
ICTとDX(デジタルトランスフォーメーション)は、どちらも業務のデジタル化を支える要素ですが、「目的」と「活用範囲」が異なります。ICTはパソコンやインターネットを活用して、業務の効率化や情報共有を進めるための技術・仕組みのことを指します。これに対してDXは、事業や働き方そのもののインフラを変革することを意味する用語です。例えば、従来の対面販売をやめて、オンライン上で新たなサービスを展開するなど、ビジネスモデル自体を刷新する動きがDXの代表例になります。ICTは道具であり、DXは変革するプロセスだと捉えると違いがわかりやすいでしょう。
身近なICTの例は何?
ICTは、私たちの日常生活のあらゆる場面で活用されています。スマートフォンは最も身近なICTの例で、電話やアプリによる情報取得、SNSでのコミュニケーションなど、日常の行動はすべてICT技術によって支えられています。また、銀行のATMやスーパーのセルフレジにもICT技術が欠かせません。役所や医療機関の予約、申請手続きなどをWeb上で完結できるのもICTの力です。生活の中で意識をすることはありませんが、私たちは知らないうちに毎日ICT技術を活用しているのです。
まとめ
ICTを本当に活用するためには、人や現場の声に耳を傾け、リテラシーの差や運用上の課題と丁寧に向き合うことが重要です。業務効率化や新たなサービスの創出といった成果は、現場での小さな変化を積み重ねる中で少しずつ実感できるものです。導入にあたっては、セキュリティや運用管理への十分な配慮が欠かせないため、専門家や信頼できるパートナーに相談しやすい体制を整えることも大切です。自社の実情に合ったICTの活用方法を、現場とともに模索していきましょう。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
関連ブログ:コラム
- OutSystems(アウトシステムズ)とは?メリット・デメリットや将来性、導入方法まで解説
- AMSとは?メリットやサービス内容、具体的な活用事例を解説
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) - 増加背景と導入の注意点
- ITにおけるロールアウト、システム展開を成功させるためのポイントを解説
- BPOの意義・アウトソーシングとの違い・対象業務例について