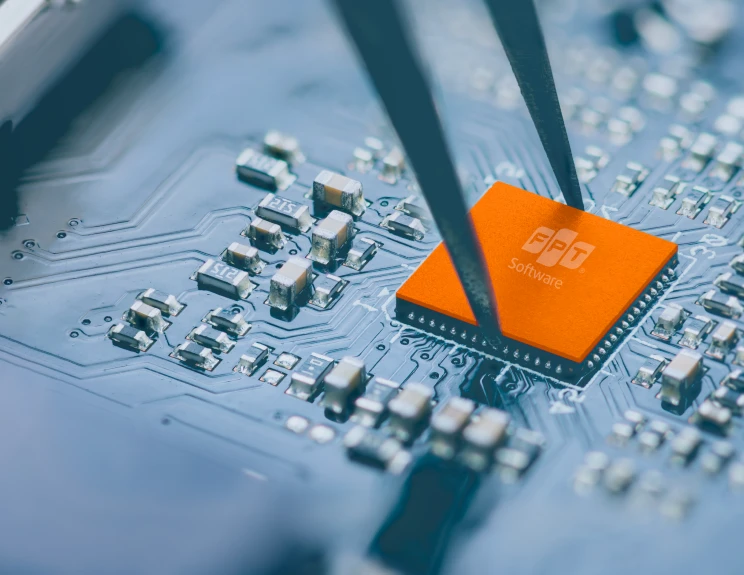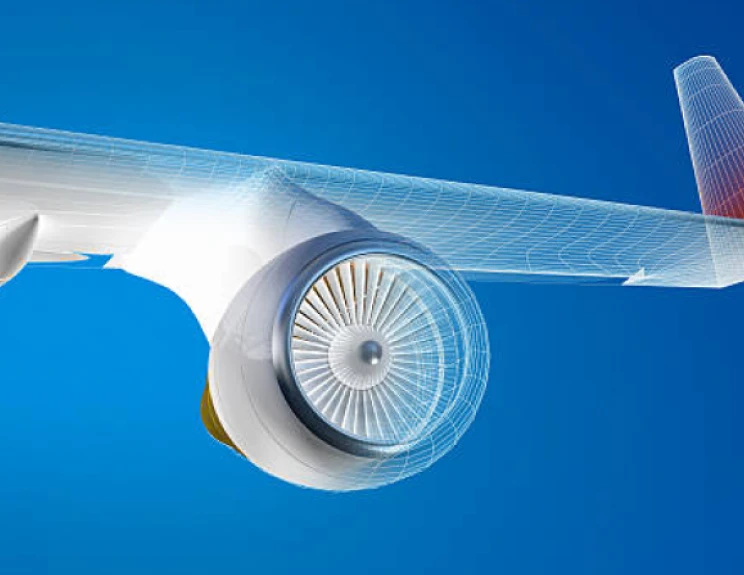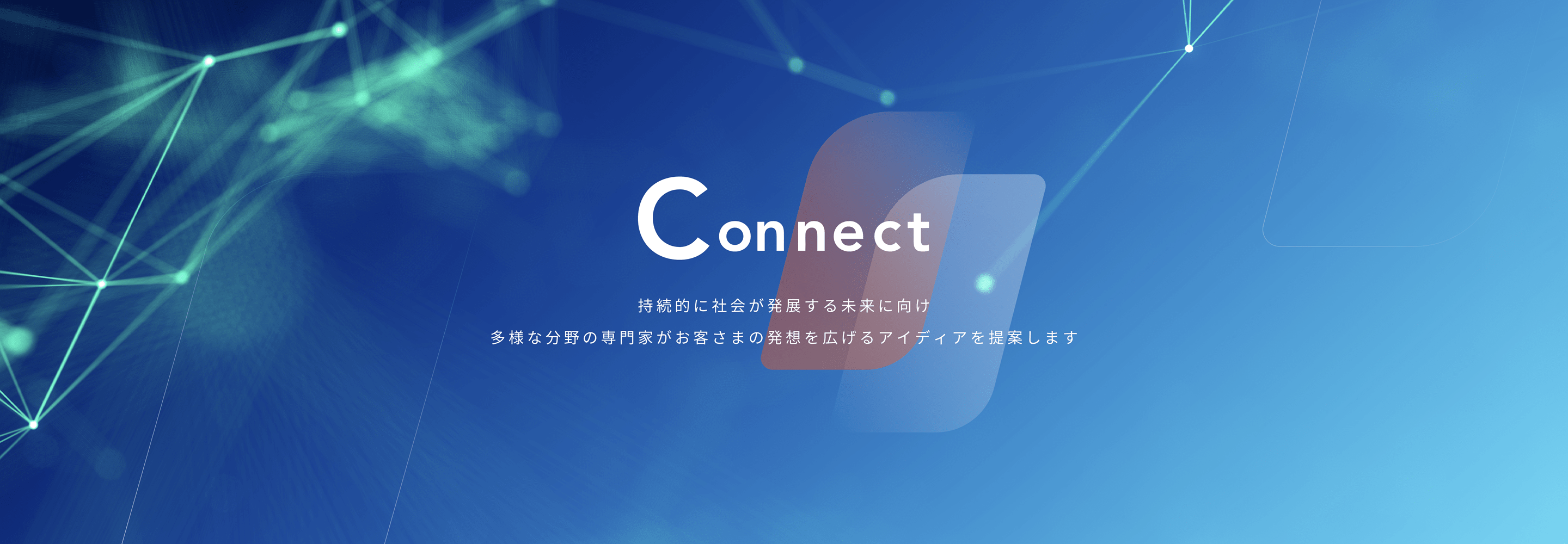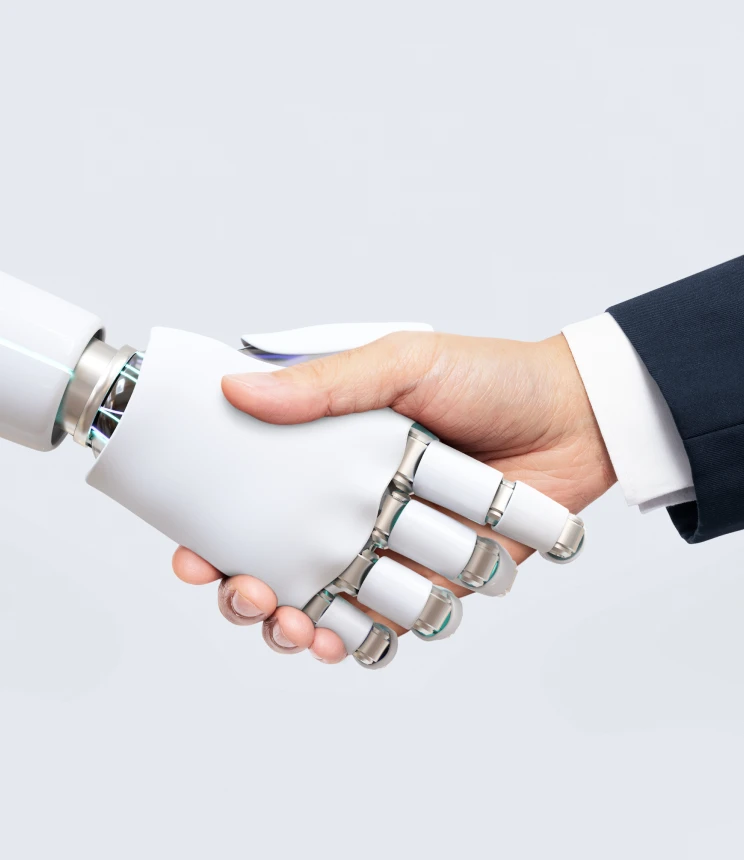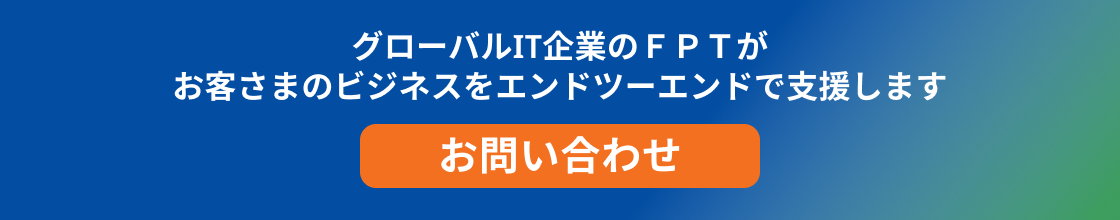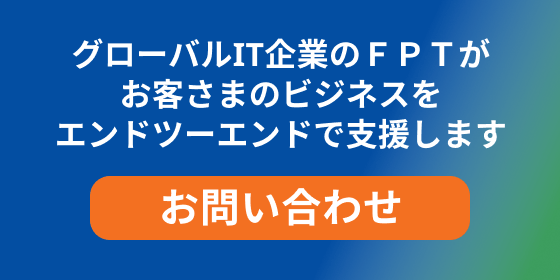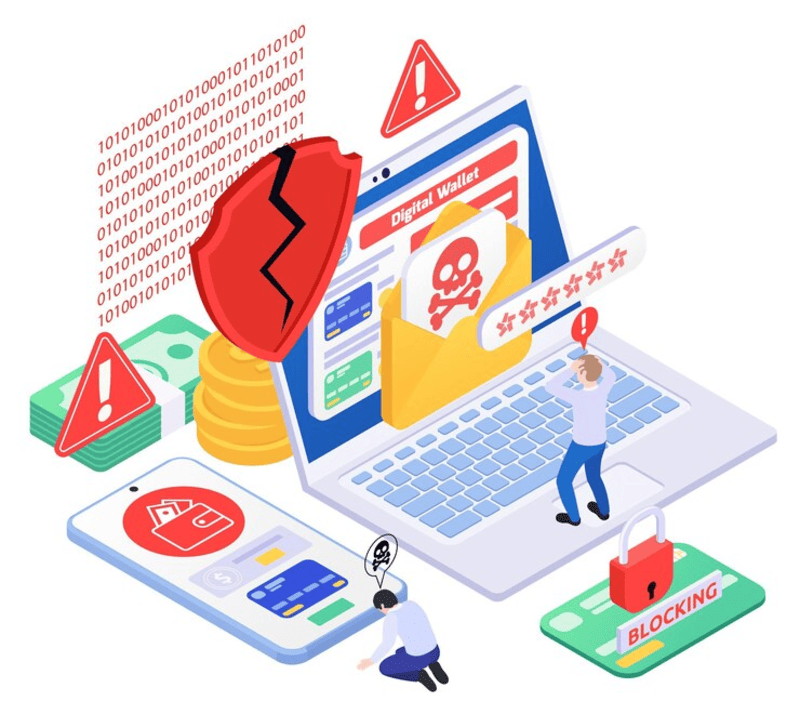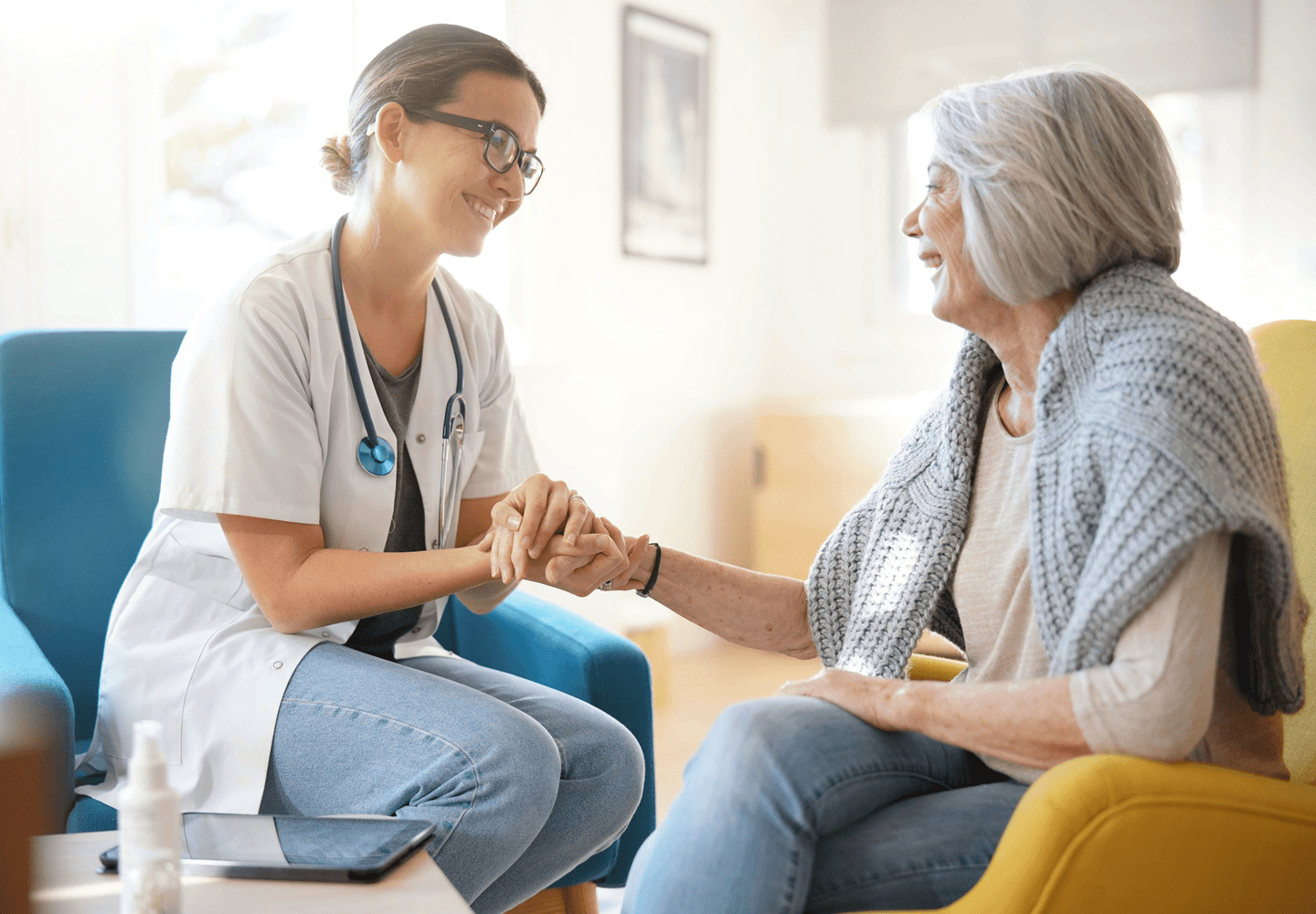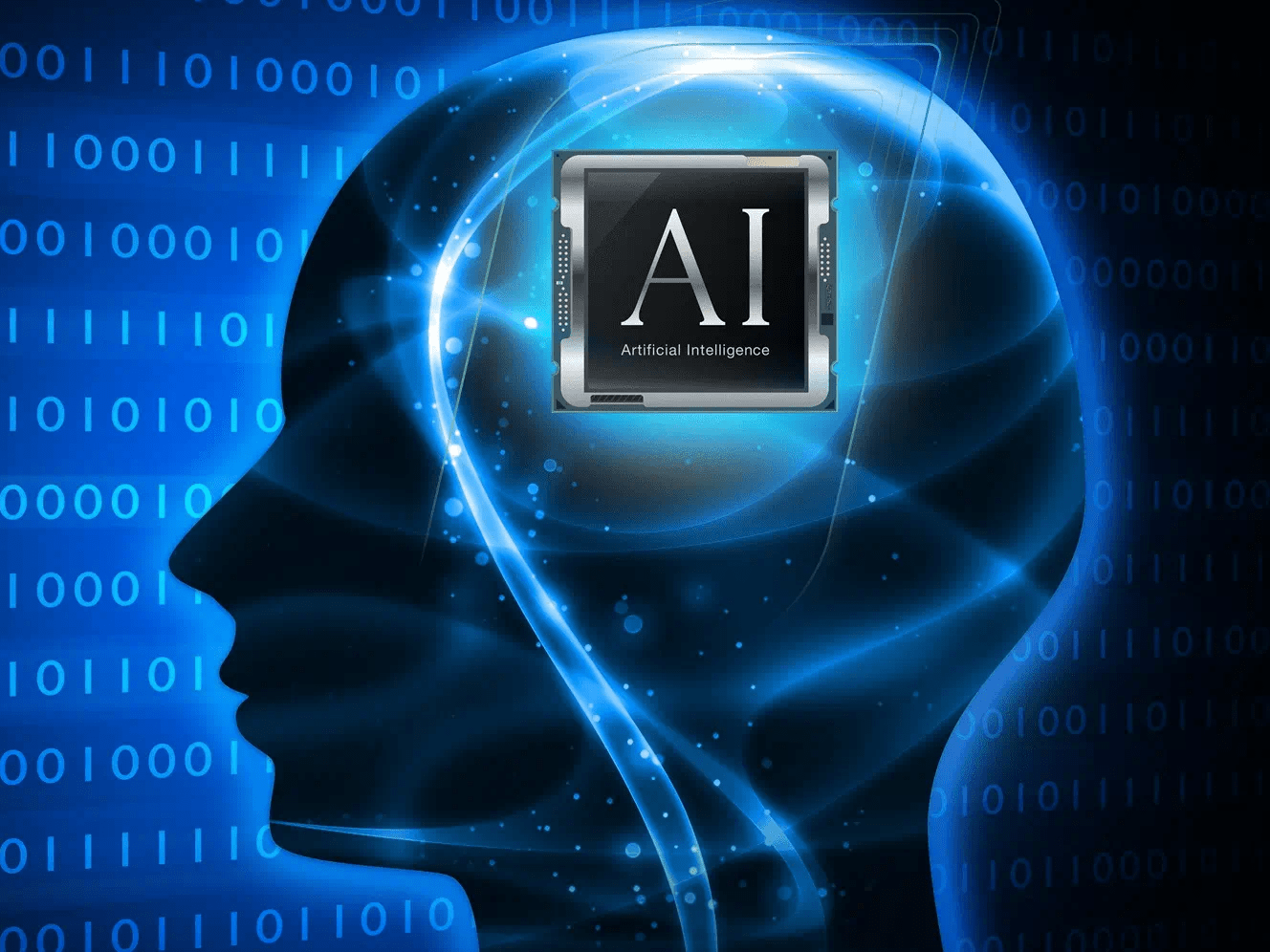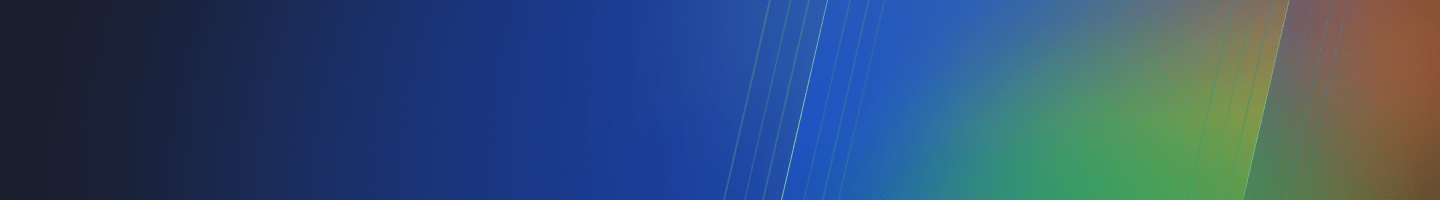RPAとは?
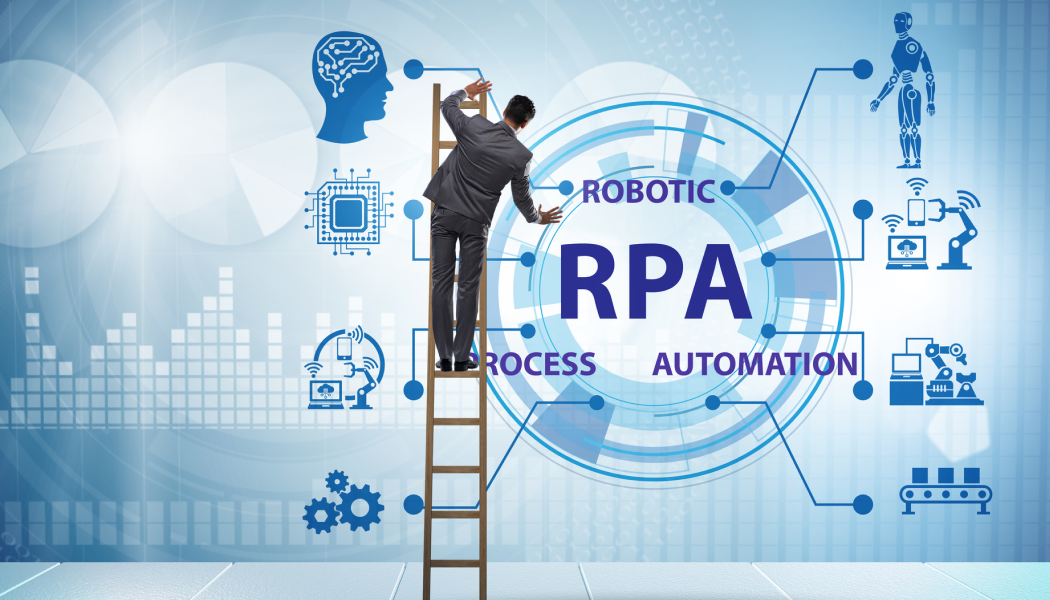
RPAは「Robotic Process Automation」を略した言葉で、PCなどを用いてホワイトワーカーが行う定型的で反復性の高い事務作業を自動化するソフトウェアロボットを指します。企業のDX推進に不可欠なツールとして注目されており、人間が手作業で行っていたデータ入力や転記、システム間の連携といった業務を代行することで、大幅な業務効率の向上と生産性向上を実現します。RPAの導入によって、より高度な業務に集中できるため、企業全体の競争力を強化することが可能です。
RPAが提供する代表的な機能
RPAの主な機能は、人間がPC上で行う作業を、まるで人が操作するかのように自動化することです。具体的には、ユーザーインターフェースを介して複数のシステムやアプリケーションを操作し、あらかじめ設定された手順に従って処理を自動で実行します。多くのRPAソリューションは、画面操作の記録やドラッグ&ドロップといった直感的な設定機能を備えているため、プログラミング知識がない人でも簡単に自動化プロセスを構築できます。そのため、既存システムの大規模な改修や業務フローの見直しをせずに、手軽に業務効率化を図れるのがRPAの大きなメリットです。
RPAを活用した例は以下の通りです。
•マーケティング業務の自動化
競合他社の価格やSNS上の口コミを定期的に収集し、Excelにまとめることで、最新の市場データを効率的に把握し、自社製品戦略に活用できます。
•ECサイト運営業務の自動化
売上データや広告効果を自動で収集し、日次レポートを作成することで、担当者がすぐに分析や次のアクションに移ることが可能になります。
RPAとVBAの違い
VBAとは「Visual Basic for Applications」を略した言葉で、ExcelやWordなどのOfficeソフト内で、繰り返し作業や処理を自動化できるプログラミング言語です。Office製品に特化し、複雑なデータ処理や統計加工を得意とします。一方、RPAはPC上で行われる幅広い作業を自動化するソフトウェアロボットです。
VBAが特定のアプリケーション内での自動化に限定されるのに対し、RPAは複数のアプリケーションを横断して操作できます。また、VBAがプログラミング知識を必要とするのに対し、RPAは操作を記録するだけで自動化設定が可能なものが多く、プログラミングの専門知識がなくても導入しやすい点が大きな違いです。
RPAとAIの違い
AI(人工知能)は、人間の知能をコンピュータ上で再現する技術全般を指します。学習・推論・判断など、人間が行うような知的処理を機械が行うのが特徴です。一方、RPAは、ロボットがPC上での定型的な繰り返し作業を自動化するツールです。例えばデータ入力やレポート作成など、あらかじめ決められた手順を正確に実行します。AIとRPAの大きな違いは、AIが自律的な「判断」を伴うのに対し、RPAは決められた「作業」を忠実に実行する点です。AIは「頭脳」、RPAは「手足」に例えられ、両者を組み合わせることで、より高度な業務自動化が可能になるでしょう。
RPAの導入が増えている背景

RPA導入が急速に拡大している背景には、人手不足の解消、技術進歩による利便性の向上、そして多くの成功事例による導入促進という3つの大きな要因があります。
人材不足
RPA導入が加速する背景は、欧米と日本で異なります。欧米では、金融危機後のガバナンス強化や、オフショア拠点における人件費の高騰に直面し、業務品質を維持しながらコストを削減するために、RPAのような効率化ツールの活用が不可欠となりました。これにより、従来のオペレーションモデルを見直す動きが活発化したのです。
一方、日本では長時間労働の是正や働き方改革への取り組みが本格化しており、さらに長期的な生産年齢人口の減少という深刻な課題を抱えています。このような状況の中で、企業は限られた優秀な人材をより有効に活用するために、定型業務をRPAで自動化し、社員がより高付加価値な業務に専念できる環境づくりを進めています。これらの複合的な要因が相まって、日本におけるRPAの急速な浸透と導入拡大を後押ししています。
技術向上による利便性の向上
RPA導入が進んでいるのは、技術の進化により操作性や導入のしやすさが大きく改善されたためです。その要因の一つは、RPAが操作できる情報やシステムの種類が拡大し、Webアプリケーションや仮想環境など、多岐にわたる環境に対応可能になったことにあります。もう一つの大きな要因は、RPAの設定が画面操作の記録やドラッグ&ドロップといった直感的な方法で行えるようになった点です。
そのため、プログラミングに関する専門知識を持たない現場部門の担当者でも、比較的容易にRPAを導入し自動化プロセスを構築できるようになりました。さらに、2010年頃からは、初期費用を抑えた導入しやすいビジネスモデルや、機械学習機能を搭載した高度なRPAソリューションも登場しました。これらの進化は、RPAの適用可能な業務領域を大幅に広げ、結果として、より多くの企業にとってRPA導入のメリットを一層高めることにつながっています。
多くの企業が導入している
RPA導入が加速している理由の一つは、その圧倒的な導入スピードと即効性にあります。従来のシステム開発と比べて、RPAは導入期間が格段に短く、早期に業務効率化の効果を実感できる点が大きな特徴です。このような迅速な効果の発現により、他社の成功事例が瞬く間に広まりやすく、RPA導入を検討する企業にとっては、強力な説得材料や具体的な参考情報となっています。
さらに、RPAのこの特性は、企業内での導入推進にも有利に働きます。例えば、まずは特定部門で小規模かつ短期間の導入を試み、その明確な成果を示すことで、全社展開に向けた予算獲得につなげるといったアプローチが可能です。このように、導入の手軽さと即効性の高さが、多くの企業においてRPAの採用を後押しする大きな要因となっているのです。
RPAが得意な分野・苦手な分野
RPAは定型業務の自動化で真価を発揮しますが、万能ではありません。その得意分野と苦手分野を理解することが、導入成功の鍵となります。ここでは、RPAの得意分野と苦手分野を解説します。
得意分野
RPAは、判断を必要としない定型業務においてその真価を発揮します。例えば、請求書や発注・納品処理、電話・メール対応のサポート、データの収集・分析、SNS口コミの収集など、手順が定まっている反復作業で特に効果を発揮します。さらに、日報・月次レポートの作成、勤怠管理、在庫管理といったバックオフィス業務から、メール配信などのマーケティング業務、異なるシステム間のデータ連携まで、幅広い分野での活用が可能です。
これらの業務をRPAによって自動化することで、大幅な業務効率化が実現されます。結果、従業員は定型作業から解放され、より高度な判断や創造的な業務に集中できるようになります。ひいては、企業全体の生産性向上にも大きく貢献するでしょう。
苦手分野
RPAは、自律的な判断や複雑な例外処理には不向きです。あらかじめ指示された手順しか実行できないため、予期せぬ事態に直面すると処理が停止してしまうことがあります。例えば、電話番号欄に誤って全角ハイフンが入力されていた場合など、些細な入力ミスでもエラーが発生し、作業が中断される可能性があります。
しかし、「エラー発生時は次のデータに進む」「担当者にアラートを通知する」といった対応ルールをあらかじめ設定しておけば、一定の範囲で例外処理に対応することもできます。RPAはすべての業務に適しているわけではありません。複雑な判断や状況に応じた柔軟な対応は人間が担い、RPAはあくまで定型作業を正確かつ迅速に実行する役割を担います。このような人間とRPAの協働こそが、業務効率化を実現する鍵です。
【実例解説】どこまでRPA化するべきか

RPAには得意・不得意があり、自動化が必ずしも有効でない業務も存在します。そのため、単に「できるか」だけでなく、「すべきか」の判断が重要です。具体的な業務において、RPAでどこまで自動化を進めるべきか、その見極めが成功の鍵となります。ここでは、「RPAにどこまでまかせるか」について、事例を解説します。
発注業務におけるRPA活用とリスク管理
製品発注プロセスは、見積書取得からマスターデータ照合、システム連携、発注書作成・送信まで、RPAで大部分を自動化できます。これにより、大幅な効率化が期待できるでしょう。しかしながら、プロセス全体をRPAに任せることで、万が一の入力ミスや例外処理の不備が誤発注につながるリスクを伴います。特に金銭が関わる業務では、最後の「発注書の送信」部分をRPA化せず、必ず人が最終チェックを行うのがよいでしょう。RPAで効率を高めつつも、人の確認を組み合わせることで、リスクを最小限に抑え、安全に運用できます。
交通費精算の効率化とRPAの役割
従業員からの交通費精算は、ルートや金額の適正性を経理担当者が一件ずつ確認する必要があり、大きな手間がかかります。ここにRPAを導入すれば、申請内容に基づいて最適な経路や金額を自動でチェックでき、業務の効率化を図れます。
ただし、RPAは当日の交通事情や営業判断によってあえて最安ルートを選ばないケースなどを判断することはできません。そのため、RPAには一次チェックを任せ、異常が検出された精算については経理担当者が詳細を確認し、申請者に問い合わせるといった手動での対応が求められます。人とRPAが協働する運用フローこそが、正確性と効率性を両立する鍵となります。
RPAやAIにより業務プロセスを自動化、ビジネス効率を最大化FPTのハイパーオートメーションサービスについて詳しくはこちら
FPTのRPA導入支援事例
バックオフィス業務の自動化
日本の大手システムインテグレーターでは、月末や四半期末に業務負荷が高くなり、バックオフィス業務の効率化が課題となっていました。FPTは、RPAソリューション「akaBot」を活用して、6つの業務を自動化しました。導入後は、月末レポート作成の工数が75%、処理時間が85%削減され、業務精度も向上しました。社員からも好意的な反応が得られ、単調な作業から解放されたことで、より重要な業務に集中できるようになりました。
物流業務の自動化
欧州最大級の鉄道貨物事業者では、Excelからのデータ転記や出荷状況の更新など、手作業による業務が多く、作業負荷やミスが課題となっていました。FPTはRPAを活用し、データ転送や確認メールの送信などを自動化する5つのステップからなるソリューションを提供しました。導入後は、出荷追跡業務の工数が90%削減され、応答時間も2時間から12分に短縮されました。社員の満足度も向上し、業務効率が大幅に改善されています。
CITAD決済業務の自動化
ベトナムの大手銀行では、CITAD決済業務が手作業で行われており、処理に時間がかかることや顧客の待ち時間が課題でした。FPTはRPA「akaBot」を導入し、送金指示の作成から確認、レポート生成までの一連の業務を自動化しました。導入後は、月間約3万件の取引が自動化され、銀行員の生産性が向上したことで、より多様な業務に労力を費やすことができるようになりました。送金の待ち時間も最小限に抑えられ、顧客体験もスムーズになりました。
RPA導入時の注意点
RPAの導入を成功させるには、以下の2つが重要な鍵となります。
- 部門間の連携
- 管理体制の構築
RPAは現場業務の自動化に効果を発揮するため、現場部門が主導してプロセスの洗い出しや効果測定を行うことが重要です。ただし、将来的な拡張やツール選定にはシステム部門の知見が欠かせません。現場とシステム部門が協力し、それぞれの専門性を活かすことが導入成功のポイントです。
また、RPAは既存システムの変更に影響を受けやすく、管理が不十分だとブラックボックス化し、トラブルを招く恐れがあります。これを防ぐには、全社的にRPAの稼働状況を把握し、各プロセスの内容を可視化して管理する体制が必要です。導入後もシステム部門が関与し、継続的にモニタリングすることで、RPAを安定的かつ長期的に活用できる環境が整います。
さらに、RPAを定着させるには、担当者間のナレッジ共有やマニュアルの整備も欠かせません。属人化を防ぎ、継続的な改善と保守を可能にする体制が、RPAの持続的な価値を支える基盤となります。加えて、経営層の理解と支援を得ることも重要であり、トップダウンでの推進体制が導入の成功率を高める要素となります。RPAは導入して終わりではなく、継続的な改善活動が不可欠な仕組みです。
RPA導入が抱える課題とは
RPA導入において多くの企業が直面する課題のひとつが、過剰な期待と理解不足です。多くの人がRPAを万能だと誤解しがちです。しかし、RPAは基本的に判断を伴わない定型業務や反復作業に特化しており、高度な意思決定はできません。この特性を十分に理解しないまま導入を進めると、期待との乖離が生じ、期待外れの結果に終わる可能性があります。
また、RPAは導入して終わりではなく、その後の運用・修正フェーズが極めて重要です。現場のニーズに合わせてトライ&エラーを繰り返し、継続的にRPAをブラッシュアップしていく過程で、当初見えなかった課題が顕在化することもあります。導入後もPDCAサイクルを適切に実践しなければ、現場の満足度や生産性の向上といった本来の効果を十分に引き出すことはできません。
そのため、RPAの特性を理解し、社内へのRPA浸透から運用、修正までを一貫して担える「RPA人材」の確保が不可欠です。RPA人材には、以下3つのスキルが求められます。
- 業務を構造化し、シナリオに落とし込める論理的思考力
- RPAの操作・制作・修正ができるITリテラシー
- RPAの必要性を組織に説明し、現場から課題や要望を的確に引き出すコミュニケーション能力
RPA人材は、費用対効果や緊急時の対応を考慮すると、外部に依存するのではなく社内の人材を育成することが望ましいでしょう。
まとめ

本記事では、RPAの概要や得意・不得意分野、導入成功の鍵となる注意点について解説しました。RPAは、人手不足の解消や技術進化を背景に導入が進んでいます。しかし、得意・不得意な分野を理解せずに導入すると、期待とのギャップや課題が生じやすくなります。成功させるためには、現場とシステム部門の密な連携、適切な管理体制の構築が不可欠です。さらに、RPA導入後の運用や修正を担う専門人材の育成も重要になります。RPAの特性を正しく理解し、計画的に導入を進めることで、企業の生産性向上や競争力の強化につながるでしょう。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
関連ブログ:コラム
- OutSystems - ローコード開発プラットフォームの機能と導入方法を解説
- FPGAとは? メリットや関連知識を解説
- AMS(アプリケーションマネージドサービス)-メリットや提供の具体的な例を解説
- ITにおけるロールアウト、システム展開を成功させるためのポイントを解説
- BPOの意義・アウトソーシングとの違い・対象業務例について