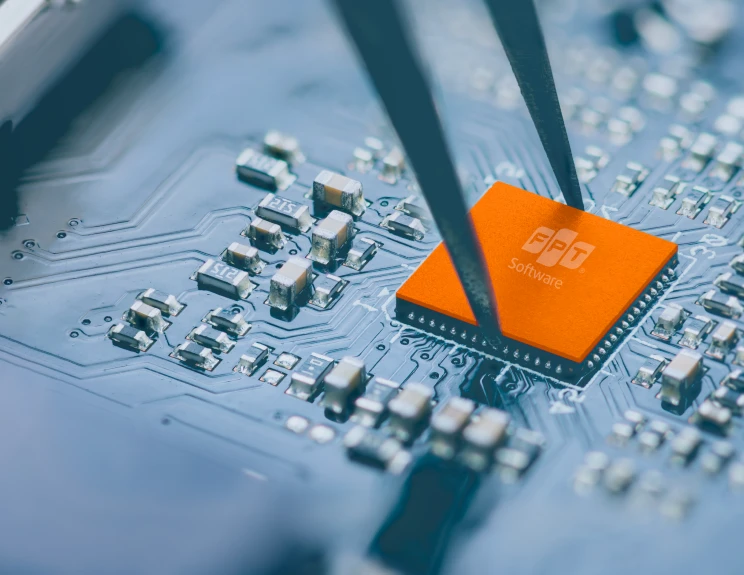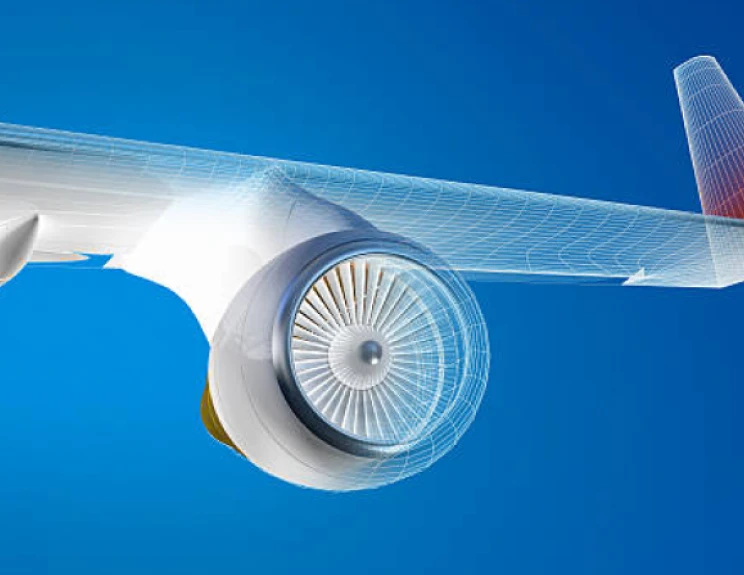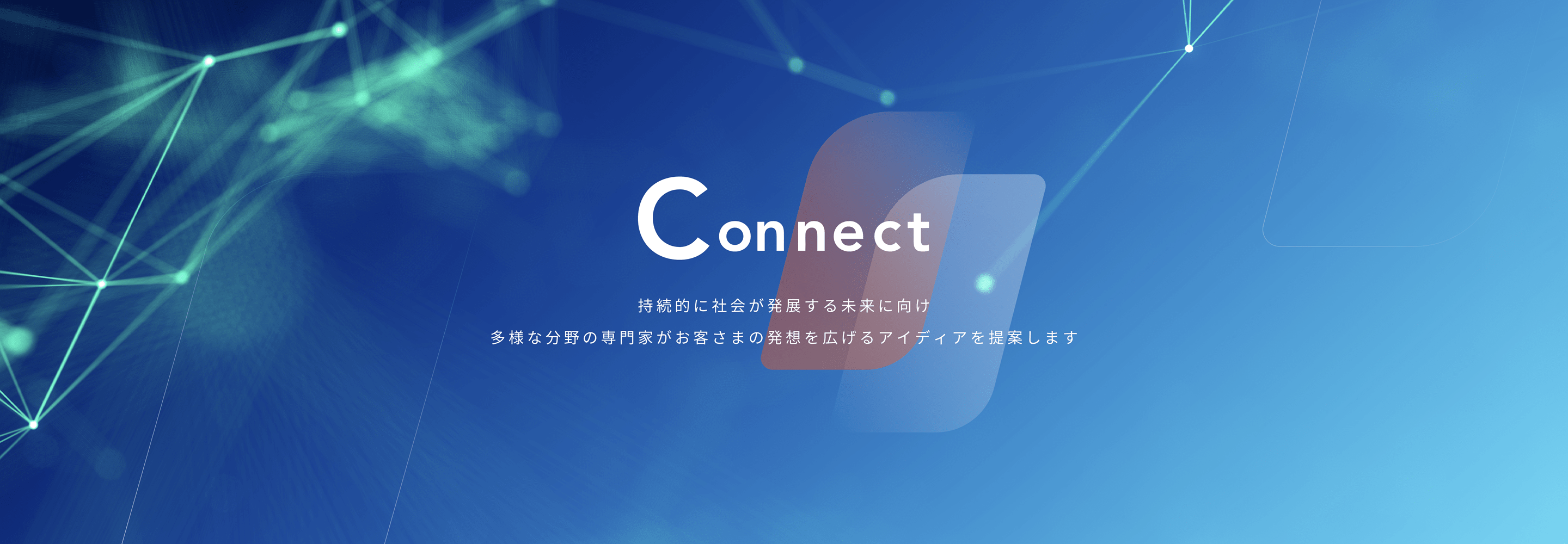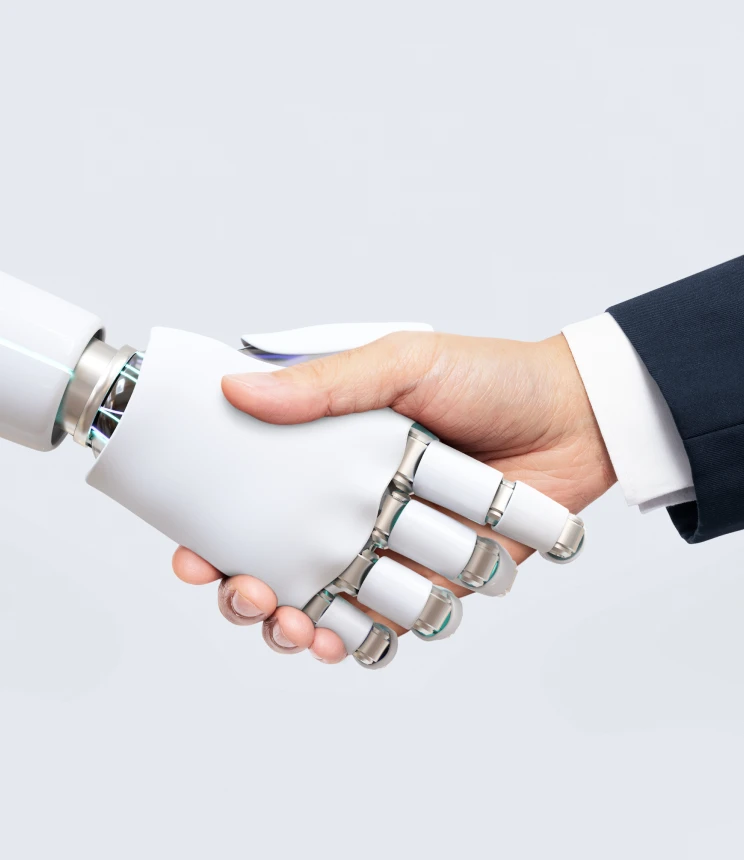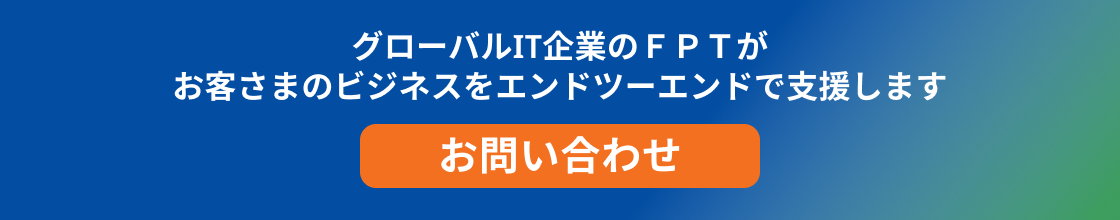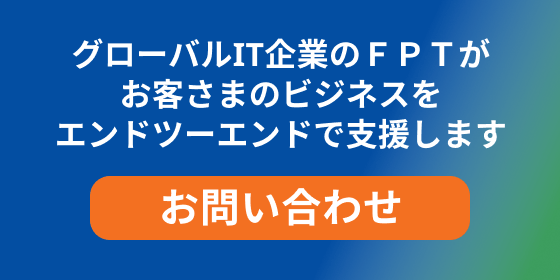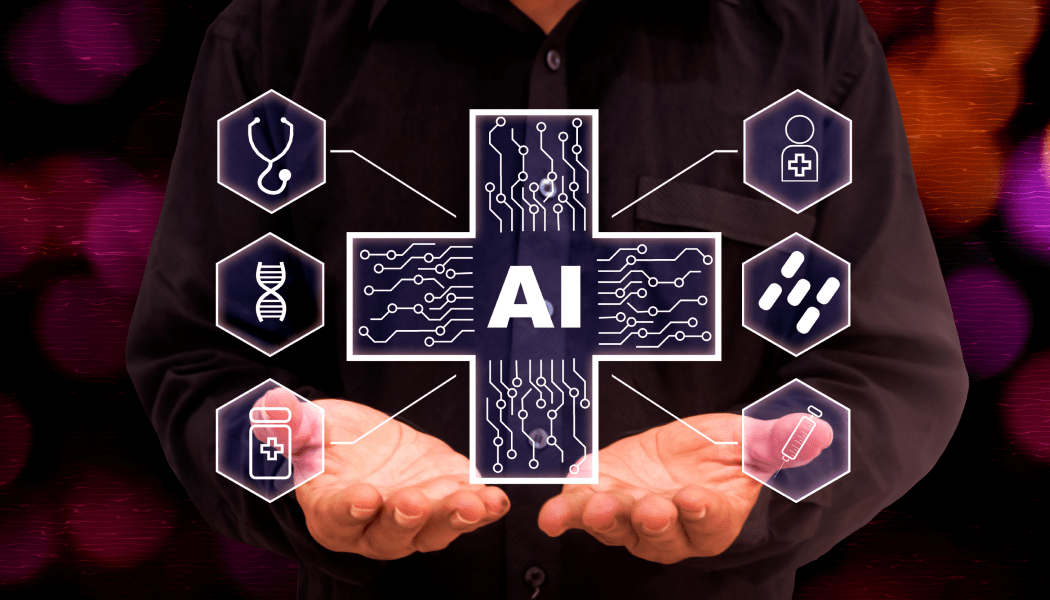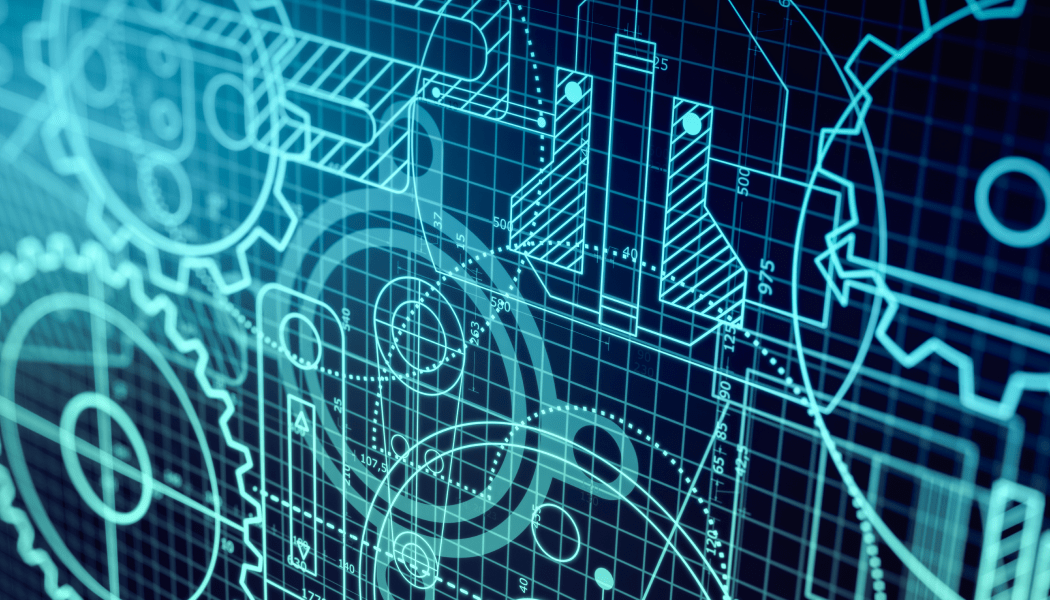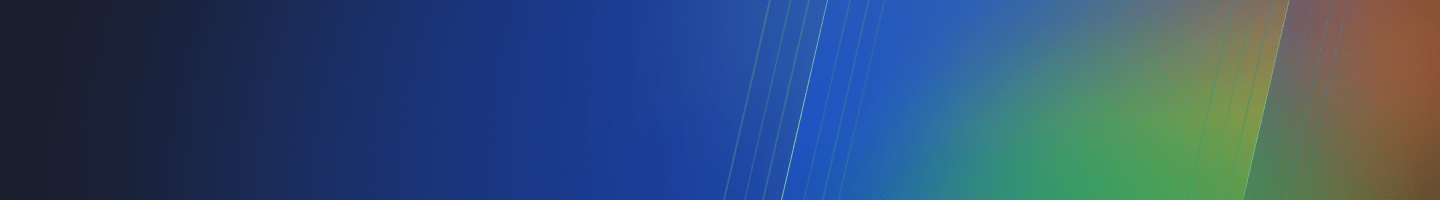目次
RPAツールとは?

RPAとはRobotic Process Automationの略称で、人がPC上で行う繰り返しの作業を、ソフトウェアロボットが代わりに自律的に実行するツールを指します。データ入力や帳票の作成、ウェブからの情報収集など、人がマウスやキーボードを使って行う操作などを自動化できます。
RPAツールができることとは?
RPAツールが得意な作業は、「定型的」作業と呼ばれる単純なPC操作です。たとえば、Excelのデータ集計や帳票作成、ウェブサイトからのスクレイピング、定型メールの送信、さらにはOCR(光学文字認識)を使って紙の書類やPDFから文字情報を抽出することなどです。
また、社内システムやクラウドサービスとの連携によって、データの登録・検索・更新などを自動化し、作業時間の短縮やミスの削減に貢献します。条件に応じた分岐処理や繰り返し操作にも対応しています。
RPAツールはこうした定型的な作業だけでなく、高度な判断が求められる「非定型的」作業の自動化にも対応できるように進化しつつあります。
【種類別】RPAツールの特徴
RPAツールは大きく分けて3つのタイプに分類されます。まず、「デスクトップ型」はPCにインストールするタイプのRPAツールです。導入が手軽なため、中小企業など小規模な法人に向いています。
次に、会社内のサーバーに構築し、クライアントPCからアクセスするタイプのツールが「サーバー型」です。複数の業務を一元管理でき、大企業の全社展開に適しています。
最後に、クラウドに設置されたツールをウェブブラウザから操作できるタイプのRPAツールが「クラウド型」です。サーバーを設置しなくてもよいことから、設備投資を減らすことができます。
| 種類 | 概要 | 主な用途 | 特徴 | 主な導入先 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップ型 | 個々のPCにインストールして利用する | – | 小規模・低価格で導入が容易 | 中小企業 |
| サーバー型 | サーバーに設置し、クライアントPCからアクセスして利用する | 複数業務を横断的に一元管理 | セキュリティリスクが低く、情報漏洩や不正アクセスなどの危険性が低い | 大企業、とくにIT統制に強みを持つ企業 |
| クラウド型 | インターネットを介してクラウド上のツールにアクセスして利用する | – | 運用・管理をベンダーに任せることができる | ブラウザ上の操作で十分な小~中規模の法人や個人 |
RPAツールの活用例
RPAツールは、さまざまな業務プロセスの自動化に活用されています。たとえば、勤怠管理では、従業員の出退勤データを自動的に収集し、給与計算や労働時間の集計を正確かつ迅速に行うことができます。これにより、手作業による入力ミスを防ぎ、労務管理の効率化が図れます。
また、在庫管理においては、複数の販売チャネルや倉庫の在庫情報をリアルタイムで取得・更新し、在庫数の過剰や不足を防ぐことができます。こうすることで、欠品や過剰在庫のリスクを低減し、適切な在庫水準の維持が可能となります。
さらに、経費業務においては、領収書の情報をOCRで読み取り、経費システムへの自動入力を実現します。これにより、精算業務のスピードアップと正確性の向上が期待できます。
RPAツールの料金はどのくらい
RPAツールの導入には、設定費用や機器の購入費用などの初期導入費用に加えて、「ライセンス費用」と呼ばれる月額制あるいは年額制でツールを利用できる権利を購入するのが一般的です。
このほか、業務を自動化するためのシナリオ作成費用や初期設定費、操作研修などの教育費用、継続的な保守費なども必要です。たとえば、クラウド型の場合は比較的導入しやすい価格帯で提供されており、サーバー型ではシステムの規模や要件に応じて大きな投資が必要となるケースもあります。
IPAとは?RPAとの違い
IPA(Intelligent Process Automation)は、従来のRPAをさらに発展させた自動化の仕組みです。
RPAが定型的な作業を対象に、ルールに従って操作を繰り返すのに対し、IPAはAI技術と組み合わせることで非定型的な作業にも対応できます。たとえば、OCRで読み取った文章から内容を要約したり、問い合わせの文面を解析して処理内容を判断したりするなど、文脈に基づく判断を伴う業務の自動化が可能です。
RPAツールを利用するメリット

RPAツールの導入には、単なる作業の効率化を超えた複数のメリットがあります。以下で述べる4つのメリットにより、企業全体の付加価値の向上につながります。
1. コストの削減
RPAツールの最大のメリットのひとつが、業務の省人化によるコスト削減です。これまで人手で行っていた定型業務をツールに任せることで、作業時間を大幅に短縮でき、結果として人件費の抑制につながります。
とくに、データの転記や報告書の作成、定期的なチェック業務などは、RPAによる自動処理に適しており、1人分、あるいはそれ以上の作業負荷を代替することも可能です。
2. ミスの削減
人が手作業で入力や転記を行う場合、どうしても発生してしまうのがヒューマンエラーです。ロボットは、あらかじめ設定した手順通りに正確に処理を実行するため、ミスが起こる可能性を限りなくゼロに近づけられます。
とくに、数値の計算や日付の整合性、複数ファイル間の照合といった、ミスが重大な問題につながる業務においては高い信頼性を発揮します。これにより、業務品質の安定化と社内のチェック工数の削減にもつながります。
3. 顧客への満足度上昇
RPAツールの導入は、顧客満足度の向上にも寄与します。たとえば、配送状況の問い合わせ対応を自動化することで、顧客からの問い合わせに迅速に対応できるようになり、顧客の待ち時間を短縮できます。
また、顧客からの問い合わせメールに対して、あらかじめ用意したテンプレートを用いて自動返信することで、対応のスピードと正確性が向上します。さらに、SNSやレビューサイトからの口コミや評判を自動的に収集・分析することで、顧客の声を迅速に把握し、サービス改善に活かすことができます。
4. 付加価値の上昇
RPAの導入は、企業活動全体の「選択と集中」を可能にします。人が担っていた単純な定型業務をRPAに置き換えることで、商品開発や戦略立案といった付加価値の高い業務に限られた人的リソースへと再配分できるようになります。
これは経済学的に言えば「機会費用の最適化」に近く、労働力を価値創出に直結する領域へ集中させることができるという点で、企業の競争力を高める重要な手段です。
RPAツールを利用するデメリット
RPAツールは業務の効率化に大きく貢献する一方で、導入・運用には注意が必要です。デメリットを回避するため、適切な設計と運用ルールを定めることが求められます。以下では、RPAツールを利用する4つのデメリットを列挙します。
1. システム障害に弱い
RPAツールはクラウドやサーバーといった外部環境に依存しているため、システム障害に弱いというデメリットがあります。たとえば、クラウド型のRPAツールを運用している場合、サーバー障害や通信障害が発生すると、ロボットが一切の処理を行えなくなってしまいます。
こうしたシステム停止に備え、バックアップのワークフローやエラー発生時の対応ルール、最悪時の手作業による代替策など、運用上のリスク対策をあらかじめ整えておくことが不可欠です。
2. 引継ぎ不足によるブラックボックス化
RPAはシナリオという手順設計に基づいて動作しますが、そのシナリオの中身が特定の作成者や外注先に強く依存していると、運用上の大きなリスクとなります。もし担当者が異動や退職をしたり、外注契約が終了したりすれば、誰も中身を理解できず、シナリオが“ブラックボックス化”してしまうのです。
この状態では、エラー発生時の対応や業務変更への柔軟な修正が困難になり、再構築を余儀なくされることもあります。これを防ぐには、設計書やコメント付きのシナリオ、操作マニュアルの整備など、可視化と共有を前提とした運用が欠かせません。
3. 情報漏洩の可能性
RPAツールは業務の自動化において、顧客情報や社内データなど、機密性の高い情報を扱う場面が少なくありません。現代の情報インフラストラクチャは、クラウドサービスやSaaS、外部APIとの接続を前提としており、情報がネットワーク経由で多方向に流れるため、漏洩リスクも複雑化しています。
たとえば、誤ったメール送信先への自動送信、アクセス制御の不備による内部漏洩、ログに個人情報が残るといったかたちで、予期せぬかたちで漏洩する危険があります。こうしたリスクを防ぐには、適切なアクセス管理、ログの監視、暗号化、エラーハンドリングの徹底など、セキュリティ設計を意識した運用が欠かせません。
4. 間違えた指示による作業をしてしまう
RPAは、あらかじめ定義されたシナリオに従って動作します。そのため、シナリオの中に誤った処理手順が含まれていれば、ロボットはそれを疑うことなく、間違った作業を繰り返してしまいます。
シナリオを作るのは人間であるため、たとえIT担当者や外注先のエンジニアであっても、設計ミスや条件の見落としを完全に防ぐことはできません。つまり、「人のミスをそのまま拡大再生産する存在」であるともいえます。こうしたリスクを防ぐには、シナリオのレビュー体制やテストプロセスの整備が極めて重要となります。
RPAツールを上手く使うポイント
RPAツールを導入しただけでは、十分に性能を発揮することはできません。そのため、RPAツールを上手に使いこなすことが重要です。以下に、RPAを使いこなすためのポイントを列挙します。
対象の業務を選定する
RPA導入において最も重要なのは、「RPAをとにかく導入しよう」という導入自体が目的化するのではなく、「この業務を省人化できないか?」という視点から始めることです。
業務改善の一環として、本来は人がやらなくてもよい作業や、繰り返しが多くミスが起こりやすい定型業務を洗い出し、それがルール化できるかどうかを見極めます。たとえば、売上データの集計や請求書の発行などはRPAに適していますが、例外処理が頻繁に発生するため属人化せざるを得ない業務や判断を伴う作業は不向きです。
運用ルールを選定する
RPAを効果的に活用するためには、明確な運用ルールの策定が不可欠です。運用ルールを定めることで、ロボットの誤作動や管理コストの増大といったリスクを回避し、効率的な運用が可能となります。
たとえば、開発する業務の基準や申請手順、運用マニュアルの整備、トラブル発生時の対処法の明文化、そしてロボットの稼働状況や開発者情報を管理する体制の構築が求められます。これらのルールを策定し、定期的に見直すことで、RPAの導入効果を最大限に引き出すことができます。
RPAやAIにより業務プロセスを自動化、ビジネス効率を最大化FPTのハイパーオートメーションサービスについて
【状況別】RPAツールの選び方
RPAツールを選ぶ際には、自社の業務形態や運用体制に合わせた視点が重要となります。「現場主導で使いたいのか」、それとも「IT部門で集中管理したいのか」など状況によって、適したツールのタイプが大きく変わってきます。
現場での利用の場合
RPAは、業務担当者自身が手軽に扱えるノーコード型のツールも多く、現場主導で導入・運用されるケースが増えています。たとえば、請求書の作成や売上報告の集計など、日々のルーチン業務をボタン一つで完了できるようになり、業務負担の軽減とともに、新たな業務改善の発想にもつながります。
ノーコード環境では、プログラミングの知識がなくても操作手順をフローとして組み立てられるため、現場の裁量で自動化ができます。
ITシステム部門での利用の場合
情報システム部門では、より高度な業務の自動化や全社的な展開を視野に入れ、ローコード型のRPAツールを活用することが多くなっています。たとえば、システムログの監視、アカウント管理、API連携によるデータ処理など、業務部門では扱いきれない技術的な領域も、ローコードの柔軟性を活かして自動化できます。
また、IT部門がテンプレートを整備し、現場への展開や運用ルールの標準化を主導することで、属人化を防ぎながら全社でのRPA活用を推進できます。
RPAツールの比較はどこを見ればよい?

RPAツールは各社から多様な製品が登場しており、単純な機能だけでは判断が難しい面もあります。比較する際には、次の点がポイントとなります。
操作のしやすさ
RPAツールの操作性は、導入後の定着率や業務効率に大きく影響します。ノーコードやローコードで操作できるツールは、プログラミングの知識がない現場担当者でも扱いやすく、スムーズな導入ができます。
たとえば、ドラッグ&ドロップでフローを構築できるインターフェースや、直感的な操作が可能なデザインは、ユーザーの負担を軽減します。自社の人材リソースやスキルセット、専門スタッフによるサポートの有無などを考慮し、最適な操作性を持つツールを選定することが重要です。
拡張内容の有無
RPAツールの拡張性は、将来的な業務の変化や拡大に対応するための重要な要素です。たとえば、サードパーティが提供している拡張機能やAPI連携、AI機能の利用など、追加機能を利用できるツールは、基本機能だけでは複雑化したシナリオを簡略化でき、業務の幅を広げることができます。
このため、自社の業務フローや将来的な拡張計画を踏まえ、必要な拡張機能を備えたツールを選ぶことが求められます。
管理面のサービス
RPAツールの管理機能やサポート体制も、選定時の重要なポイントです。RPAツールの稼働状況をリアルタイムで監視できるダッシュボードや、エラー発生時の通知機能、ログの記録と分析機能などは、運用の安定性を高めます。
また、ベンダーによる導入支援やトレーニング、サポート体制の充実度も、運用開始後のスムーズな定着に寄与します。とくに、ITリソースが限られている中小企業にとっては、手厚いサポートが導入成功の鍵となります。
RPAツールの導入手順

RPAツールの導入は、業務の効率化や生産性向上を目指す上で効果的な手段といえるでしょう。導入を成功させるためには、以下の手順を踏むことが推奨されます。
対象業務・内容の選定
RPA導入の出発点は、「どの業務を自動化すべきか」の見極めが重要です。そのために、まず業務フローの棚卸しと現場担当者へのヒアリングを行い、業務の全体像、発生頻度、例外対応の有無などを把握します。
この段階では、業務の定型性やルール化の可否を評価し、RPAに適した業務かどうかを判断します。この過程で得られた情報をもとに、業務要件の整理を行い、自動化候補を明確にします。
シナリオ作成
自動化対象が決まったら、具体的にRPAが行う処理を「操作手順」として設計するフェーズに移ります。ここでは、RPAで操作するアプリケーションや処理条件、例外パターンの扱いなどを詳細に定義します。
シナリオ作成には、内製か外注かでアプローチが異なり、内製ならIT部門と業務担当者が協力し、外注なら仕様書や業務フロー図をもとに要件を開発ベンダーへ伝える必要があります。
テスト導入・動作確認
シナリオが完成したら、ただちに本番導入するのではなく、十分なテスト環境で動作検証を行うことが不可欠です。テストでは、通常ケースだけでなく、想定される例外やエラー入力、境界条件なども含めて検証し、設計通りに処理されるかどうかを確認します。
またファイル構成やシステム接続環境を再現した環境でテストを実施することで、環境依存の不具合のリスクを軽減できます。テスト結果は記録に残し、修正履歴と合わせて管理することで、後のトラブルシュートにも役立ちます。
本導入
テストで十分に動作確認ができたら、本番業務へのRPA導入を進めます。ただし、本導入はゴールではなく、あくまで業務改善のスタート地点といえます。安定稼働を継続するためには、運用状況を定期的にモニタリングし、利用者からのフィードバックを受け取る体制を整えることが重要です。
業務内容やシステム環境は常に変化するため、当初作成したシナリオが徐々に適さなくなることもあります。そうした変化に柔軟に対応するために、導入後も「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」というPDCAサイクルを継続的に回す運用体制が求められます。
RPAやAIにより業務プロセスを自動化、ビジネス効率を最大化FPTのハイパーオートメーションサービスについて
まとめ
本記事では、定型業務を自動化するRPAツールについて、その概要と導入のポイントを解説しました。スターティアレイズ株式会社が2025年1月に公表した「【2024年度版】RPAツール導入に関するアンケート調査結果レポート」によると、大企業の導入率は27.69%、中小企業では8.51%にとどまっており、RPAの普及が進む一方で、全体としてはまだ十分に浸透していないことが明らかになりました。
しかし近年では、非定型業務にも対応可能なAI連携型のIPAが登場し、自動化できる領域が大きく広がりつつあります。こうした背景から、すでにRPAを活用してきた大企業だけでなく、従来は導入を見送っていた中小企業にとっても、RPAの再評価と活用の可能性が広がっていくといえるでしょう。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- ハイパーオートメーション
- 事例紹介: 大規模なテスト自動化RPA
- Akabot - RPA & Hyperautomation Solution for Enterprises
- FPTジャパンは日本で初のRPAプロジェクトを展開
- FPTジャパン 日経BP社主催「RPA / ビジネス AIカンファレンス 2018」にて登壇
関連ブログ:コラム
- オフショア開発でベトナムが選ばれる理由とおすすめの会社の選び方・成功事例を紹介
- ニアショア開発とは?オフショアとの違いやメリットやデメリット、人気の拠点を解説
- オフショア開発とは?導入が進む理由と成功事例を紹介
- デジタライズ、ビジュアライズ、オプティマイズ 建物・施設運用の“見えない非効率”を可視化する――Akilaが描くスマートアセットマネジメントの新常識
- 人材育成や体制構築から開発文化の醸成まで内製化を強力に支援する伴走型サービスを提供