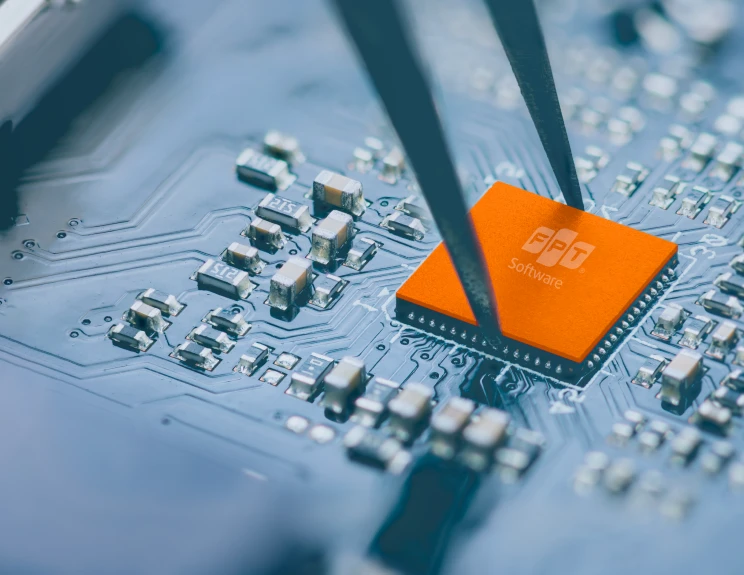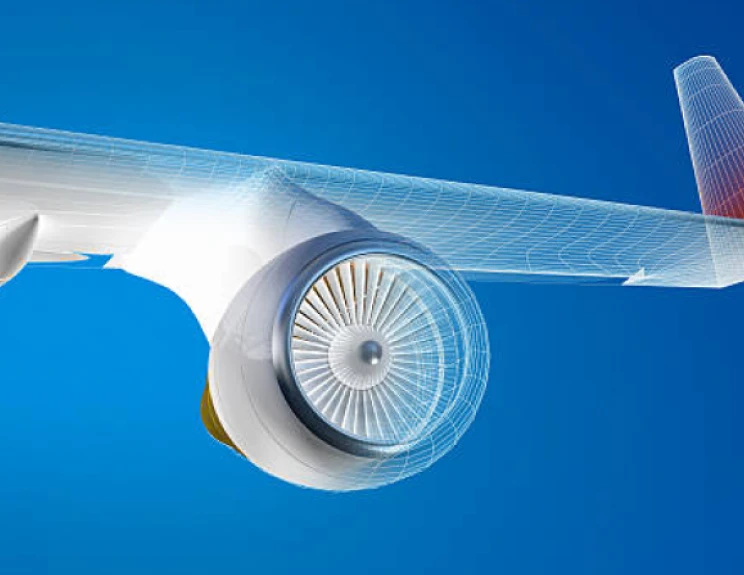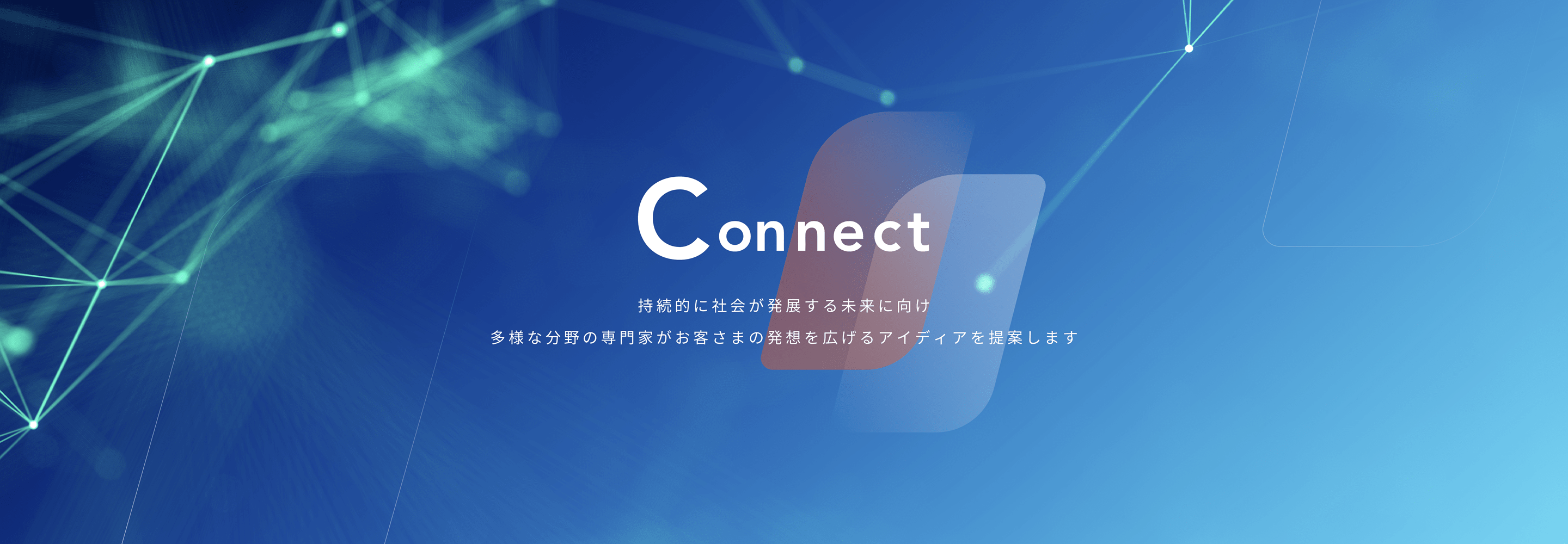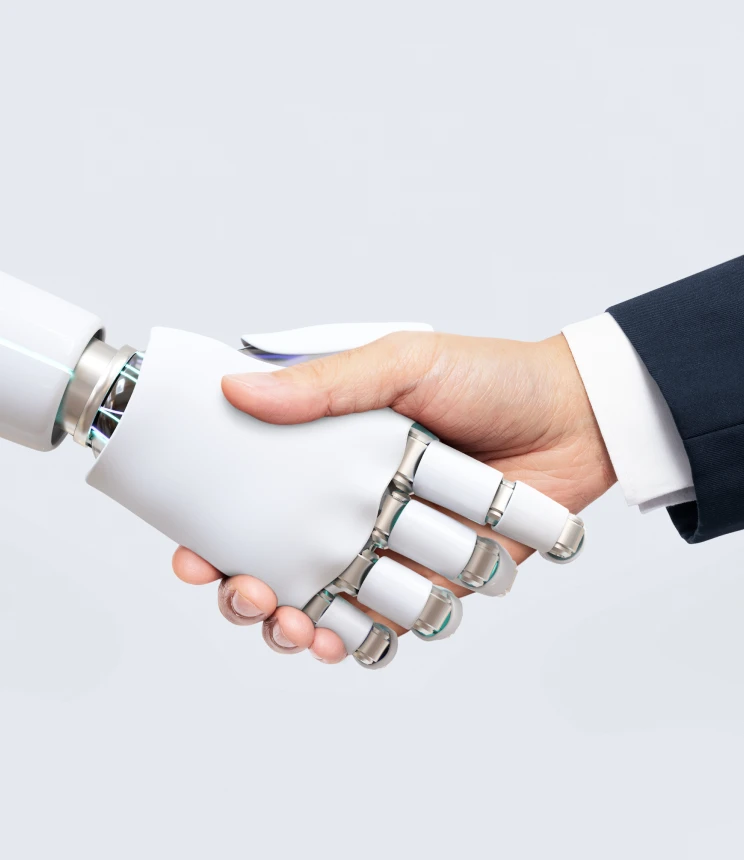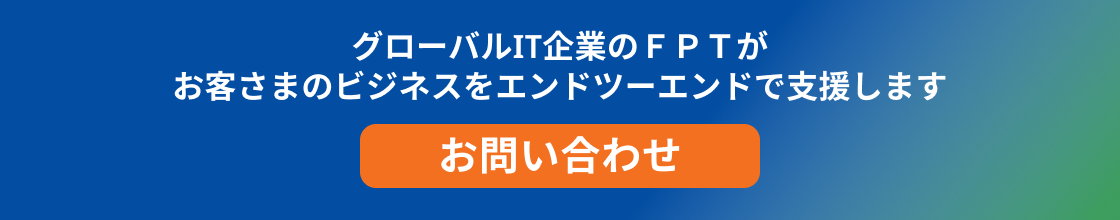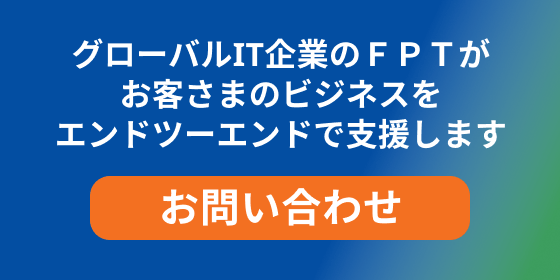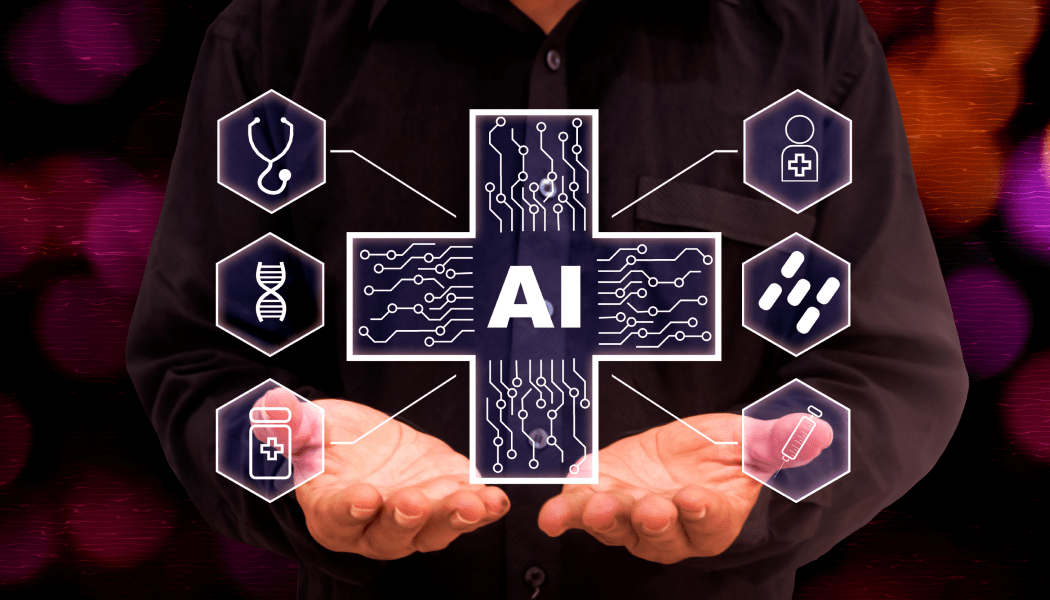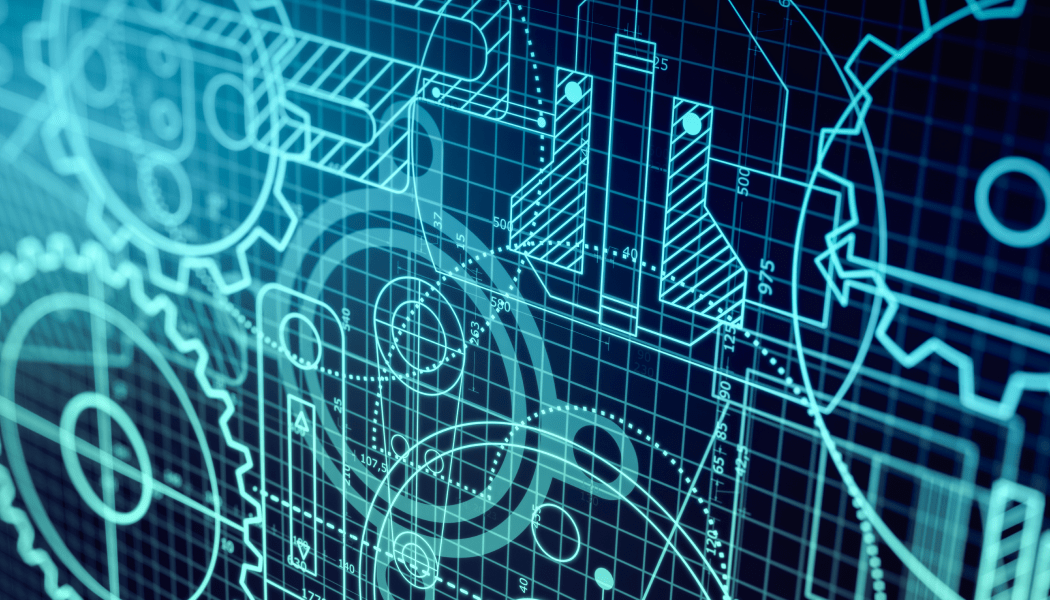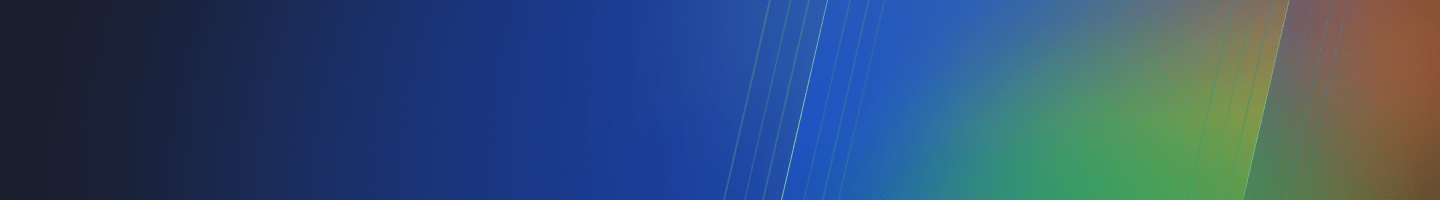目次
クラウドとは何か?

クラウドとは、サーバーやストレージ、ソフトウェアなどをインターネット経由で必要な分だけ利用できる仕組みのことです。サービス提供者がメンテナンスをおこなうため、利用者は常に最新の状態で、場所を問わずアクセスできます。「クラウド(cloud=雲)」という名称は、ネットワーク図でインターネットを雲で表現していたことや、利用者から見えない場所で処理が行われていることに由来します。
NISTが定めるクラウドコンピューティングの定義
NIST(米国国立標準技術研究所)はクラウドコンピューティングを「ネットワーク経由でコンピューティングリソースをオンデマンドで提供するモデル」と定義しています。これにより、利用者は最小限の管理や設定でリソースを迅速に調達・解放できるとされています。
“クラウドコンピューティングは、共用の構成可能なコンピューティングリソース(ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス)の集積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割当てられ提供されるものである。このクラウドモデルは5つの基本的な特徴と3つのサービスモデル、および4つの実装モデルによって構成される。”
従来のシステム「オンプレミス」との違い
クラウドとオンプレミスは、システムの構築・運用方法が大きく異なります。クラウドがインターネット経由でサービスを利用する形態であるのに対し、オンプレミスは自社内にサーバーや機器を設置し、システムを運用する形態です。それぞれにメリット・デメリットがあり、企業のニーズに応じて選択されます。
以下のようにクラウドとオンプレミスの比較についてまとめました。
| 項目 | クラウド | オンプレミス |
|---|---|---|
| 初期費用 | サーバーなどの機器を購入する必要がなく、初期費用を抑えやすい | サーバーやソフトウェアなどの購入が必要なため、初期費用が高額になりやすい |
| 運用・管理 | サービス提供者が運用・管理をおこなうため、自社での管理負担が少なくなる | すべて自社で運用・管理をおこなう必要があり、専門知識を持った人材が必要となる |
| 利用場所 | インターネットに接続できる環境があれば、どこからでも利用可能 | 設置された社内ネットワークなどに接続する必要があり、利用場所が限定されることが多い |
| 拡張性 | 必要なときに必要な分だけリソースを増減でき、柔軟に対応できる | 機器の増設や設定変更に手間がかかり、拡張性に欠ける場合がある |
| セキュリティ | サービス提供者のセキュリティ対策に依存する | 自社のセキュリティポリシーに合わせて、自由に設定できる |
身近なクラウドサービスの例
身近なクラウドサービスの例を以下にまとめます。これらは、インターネットを通じてデータ保存やコミュニケーションなどの機能を提供しています。
| サービスの分類 | サービス概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| クラウドストレージ | オンラインでファイルを保存・共有・管理する | Googleドライブ、iCloud、Dropbox |
| Web会議ツール | オンラインで音声・映像・画面共有を通じて会議をおこなう | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet |
| SNS | 不特定多数の人々と情報を共有し、交流する | X、TikTok、Facebook、Instagram、LINE |
| ビジネスチャット | ビジネスシーンにおいて円滑なコミュニケーションをおこなうためのツール | Slack、Chatwork、Microsoft Teams |
| クラウドEC | インターネット上でECサイトを構築・運用する | Shopify、BASE、STORES |
クラウド誕生の歴史
クラウドは、コンピューターの進化に伴って生じた課題を解決する中で誕生しました。1950年代から1990年頃まではメインフレームによる集中処理が主流でしたが、1990年代にはクライアントサーバー型の分散処理が普及し、システム管理が複雑化しました。2000年代にはWebコンピューティングが登場し、ブラウザ経由でアプリやデータを共有できるようになりましたが、サーバーの乱立により統合管理が困難になる問題も発生します。こうした課題に対する解決策としてクラウドが登場し、仮想化技術の進化により、物理サーバー1台で複数の仮想サーバーを運用できるようになり、リソースの効率的な活用やデータセンターの統合が可能となりました。
クラウドの主な種類【SaaS・PaaS・IaaS】
クラウドサービスは提供する機能の範囲により、大きく3つの種類に分けられます。
- SaaS(サースまたはサーズ)
- PaaS(パース)
- IaaS(イアースまたはアイアース)
これらは、クラウド関連の記事や資料でよく見かける言葉ですが、具体的な違いを知らない方も多いでしょう。パソコンの構造に例えると、「本体(IaaS)」「OSや開発環境(PaaS)」「アプリケーション(SaaS)」に相当し、どの階層までを提供するかによって区別されます。

SaaS(Software as a Service)
SaaSは、従来のパッケージ型ソフトウェアをインターネット経由で利用するサービスです。ユーザーは端末にアプリをインストールせず、Webブラウザからログインするだけで利用できます。提供側がインフラからアプリケーションまで一括管理しており、常に最新の状態が保たれています。複数端末からアクセスや共同作業も容易です。
PaaS(Platform as a Service)
PaaSは、アプリケーション開発に必要なプラットフォームをインターネット経由で提供します。サーバーやOS、ミドルウェア、データベースなどが一式揃っているため、開発者はインフラ構築の手間を省き、プログラミングに専念できます。これにより効率的なアプリ開発が可能です。
IaaS(Infrastructure as a Service)
IaaSは、インフラ基盤をインターネット経由で提供するサービスです。サーバー、ストレージ、ネットワークといったハードウェア部分が提供され、OSやアプリケーションは利用者が自由に構築します。自社で機器を購入・管理する手間やコストを削減できる一方、運用には一定の専門知識が必要です。
クラウドモデルの5つの特徴
クラウドには次の5つの特徴があり、これらが使いやすさや柔軟さの理由となっています。
- オンデマンド・セルフサービス
- 幅広いネットワークシステム
- 複数ユーザーでのリソース共用
- スピーディーな拡張・縮小
- 利用状況の計測可能
ここから詳しく解説します。
1. オンデマンド・セルフサービス
オンデマンド・セルフサービスとは、利用者がサービス提供者を介さずに、必要なときに必要なだけサーバーなどのコンピューティングリソースを自動的に調達・設定できる機能です。オンプレミスと異なり、リソースの増減に面倒な手続きが不要なため、Web上の管理画面からユーザー自身が柔軟かつ迅速に対応でき、業務のスムーズな遂行に役立ちます。
2. 幅広いネットワークシステム
クラウドサービスは、インターネット環境さえあれば、パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスから、いつでもどこでもアクセスできるのが特徴です。これにより、テレワークや出張先でもデータやシステムにアクセス可能となり、チームでの共同作業を円滑に進めることができます。災害時のBCP対策(事業継続計画)としても有効です。
3. 複数ユーザーでのリソースの共用
クラウド事業者のサーバーやストレージなどのリソースは、複数の利用者で共有される仕組みになっています。利用者の需要に応じて動的に割り当てることで、物理・仮想リソースを効率的に活用し、コストを最適化できます。自社でインフラを保有・管理する必要がなくなるため、初期投資を抑えつつ、柔軟なリソースの増減が可能になります。
4. スピーディーな拡張・縮小が可能
クラウドは、必要に応じてサーバー容量やストレージを即座に増減できるため、急なアクセス増加や事業拡大にも柔軟に対応できます。これにより、まるで無制限にリソースがあるかのように利用できます。オンプレミスと異なり、事業の急成長や季節的な需要変動にも即座に対応できるため、ビジネスの柔軟性を高める上で非常に重要な特徴です。
5. サービスの利用状況が計測可能
クラウドを利用すると、リソースの使用量を自動的に測定・管理できるため、利用状況を詳細に把握し、コストを最適化できます。この機能により、利用者は従量課金制のもと、ストレージや処理能力などの利用状況を詳細に把握し、無駄なコストを削減できます。また、サービス提供者とユーザー双方にとって透明性が確保され、適切なコスト管理や予算計画が可能になります。
クラウドのメリット
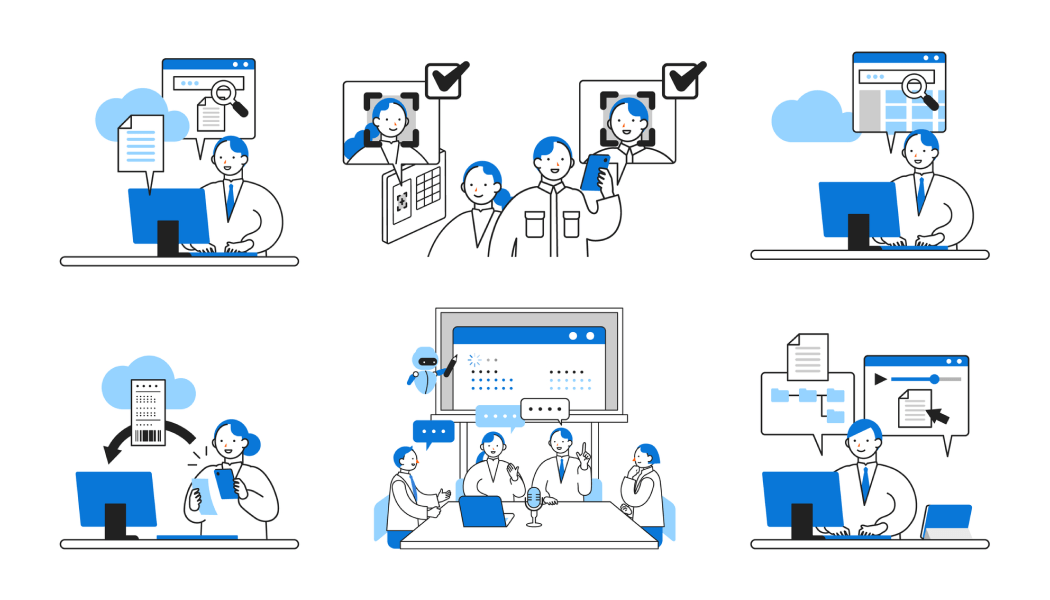
クラウドサービスを導入することで、企業は以下のように様々なメリットを享受できます。
- データへのアクセスの容易性
- 堅牢なセキュリティ対策
- 生産性とコラボレーションの向上
以下に詳しく解説します。
データへのアクセスの容易性
クラウドサービスを利用することで、企業はデータへ容易かつ安全にアクセスできるようになります。インターネット環境さえあれば世界中のどこからでもデータにアクセスできるため、リモートワークや顧客対応が円滑になります。また、クラウドはバックアップ機能を備えるサービスも多くあります。万が一、元のファイルが破損しても、クラウド上に安全に保存されたデータを迅速に復旧できるため、データ損失のリスクを大幅に軽減できるでしょう。
堅牢なセキュリティ対策
堅固なセキュリティ対策を持つクラウドベンダーを選べば、データは暗号化され、専門のデータセンターで24時間体制の厳重管理が行われます。これにより、個別企業では構築が困難な高度なセキュリティ体制を利用できます。ただし、セキュリティ事故の多くは従業員のミスが原因で発生するのも事実です。クラウドを安全に利用するためには、二段階認証の設定やセキュリティポリシーの遵守など、従業員への教育と適切な運用が不可欠です。
生産性とコラボレーションの向上
クラウドサービスを活用することで、デジタルワーカーの生産性とチームのコラボレーションを大きく向上させることが可能です。地理的な制約がなくなるため、遠隔地にいるメンバーとも場所を問わずに共同作業を進めることができます。スマートフォンやPCなど、多様なデバイスから共有ドキュメントやデータにアクセスできるため、リモートワークでも常に高い生産性を維持することができるでしょう。
【関連記事】
⇒「クラウド・オフィス」でリモートワークを実現する方法
FPTのクラウドサービスを支える経験豊富なエキスパート人材の規模と技術力に加え、お客さま支援事例を動画でわかりやすくご紹介しています
クラウドのデメリット
上述したようなメリットがある一方で、クラウドには以下のようなデメリットがあります。
- カスタマイズ性の制約
- セキュリティリスクと対策
- ベンダーへの依存とサービス継続性
ここから詳しく解説します。
カスタマイズ性の制約
クラウドサービスは、標準化された環境を提供するため、自社の業務に合わせた細かなカスタマイズが難しい場合があります。オンプレミスと比べると機能や操作に制限があることが多く、必ずしも高い柔軟性があるとはいえません。しかし、豊富な機能の中から必要なものを選んで設定できるサービスも増えているため、一般的な利用であれば問題になることはほとんどないでしょう。
セキュリティリスクと対策
クラウドはネットワークを介する以上、不正アクセスやヒューマンエラーによる情報漏洩のリスクは避けられません。従業員の誤操作による情報漏洩を防ぐには、二段階認証の導入やセキュリティ教育の徹底など、適切な運用体制の構築が不可欠です。
ベンダーへの依存とサービス継続性
クラウドサービスは、単一のベンダーに過度に依存すると、他のサービスやシステムへの移行が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクが生じます。ベンダーロックインとは、特定事業者の技術や仕様に依存し、他社への乗り換えが技術的・経済的に困難になる状態を指し、システムの柔軟性が損なわれます。さらに、提供元で大規模な障害が発生すれば、自社の業務全体に影響が及ぶでしょう。
また、ネットワーク障害や提供事業者の倒産・サービス終了などにより、サービス自体が利用できなくなる恐れもあります。こうしたリスクを踏まえ、信頼性の高いベンダーを選ぶことが重要です。加えてマルチクラウドや、オンプレミス環境との併用も効果的です。
クラウドの安全性を向上させるためには

クラウドを安全に利用するには、ID管理や従業員のセキュリティ意識向上、適切な事業者選定が不可欠です。これらのリスクと対策を理解し、適切に実行することで、より安全なクラウド運用が可能になります。
ID管理とアクセス権限のリスクと対策
クラウド環境では、人事異動時のID管理の不備による不正アクセスやサイバー攻撃のリスクがあります。対策として、人事システムとの連携によるID管理の自動化や、二段階認証の導入が有効です。また、情報漏洩を防ぐためには、ユーザーごとに必要最低限のアクセス権限を付与する「アクセス権限の細分化」が必要になります。
人的リスクとセキュリティ教育
従業員の誤操作やセキュリティ意識の低さが、クラウド利用における主要なリスク要因です。このリスクを軽減するには、セキュリティポリシーを明確に定め、従業員全員に徹底することが重要です。入社時や定期的な研修を通じて、実際の事例に基づいた教育やシミュレーションをおこなうことで、セキュリティ意識を高め、情報漏洩などのヒューマンエラーを防ぐことができます。
安全なクラウド事業者の選定
クラウドサービスを安全に利用するためには、適切な事業者を選ぶことが不可欠です。クラウド事業者を選ぶ際は、データ暗号化や不正アクセス防止策、バックアップ機能などを確認しましょう。また、クラウドサービス情報開示認定制度やISMSクラウドセキュリティ認証といった第三者機関の認証も、安全性を判断する上で重要な指標となります。
まとめ

クラウドは、インターネット経由でリソースを利用する仕組みで、「オンプレミス」とは異なるシステム運用形態です。SaaS、PaaS、IaaSといった種類があり、それぞれ提供範囲が異なります。メリットとしては、データへのアクセスの容易性や堅牢なセキュリティ対策、生産性とコラボレーションの向上が挙げられますが、カスタマイズ性の制約やセキュリティリスクといったデメリットも存在します。安全なクラウド利用のためには、利用者のセキュリティ意識向上や、信頼できる事業者選びが欠かせません。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
関連ブログ:コラム
- 生成AIの主なツール13選 - 従来のAIとの違いや効果的な使い方を解説
- 人工知能(AI)とは?種類や仕組み、メリット・デメリットを解説
- CRMとは?機能や導入メリット、活用方法と導入事例まで解説
- ランサムウェアとは?被害事例や感染経路、被害防止対策を解説
- ICT(情報通信技術)とは何? IT、IoTとの違いや教育・介護・医療現場での活用例を徹底解説