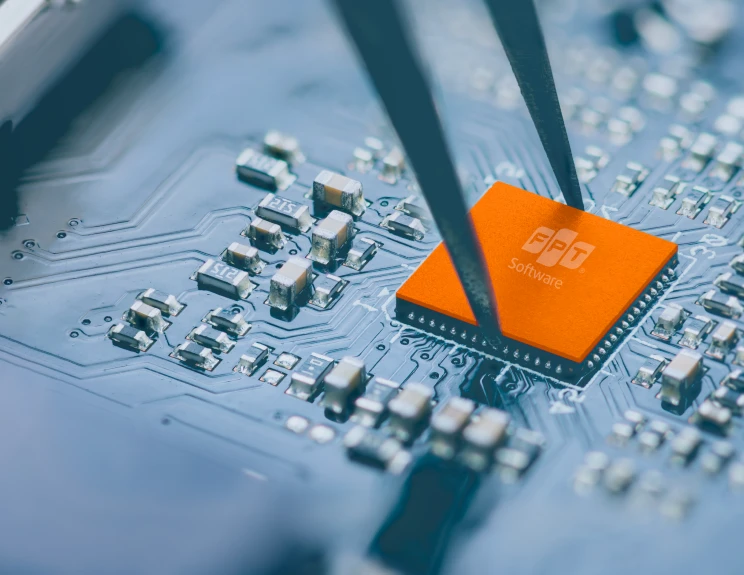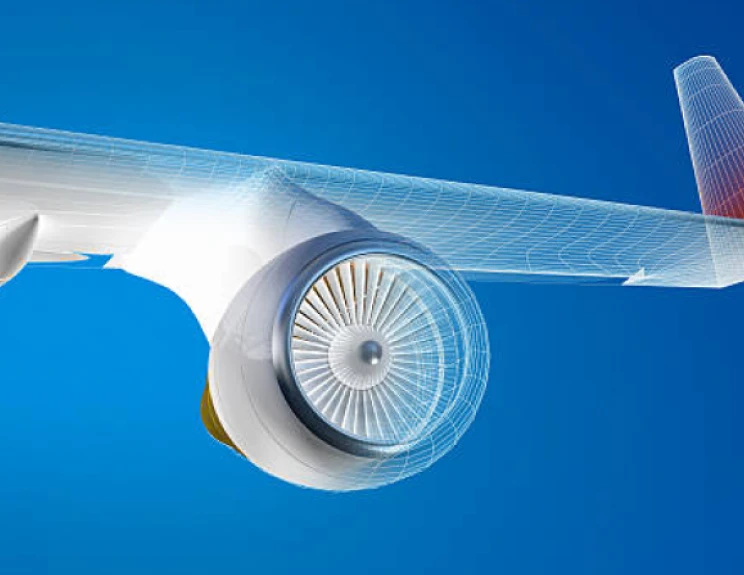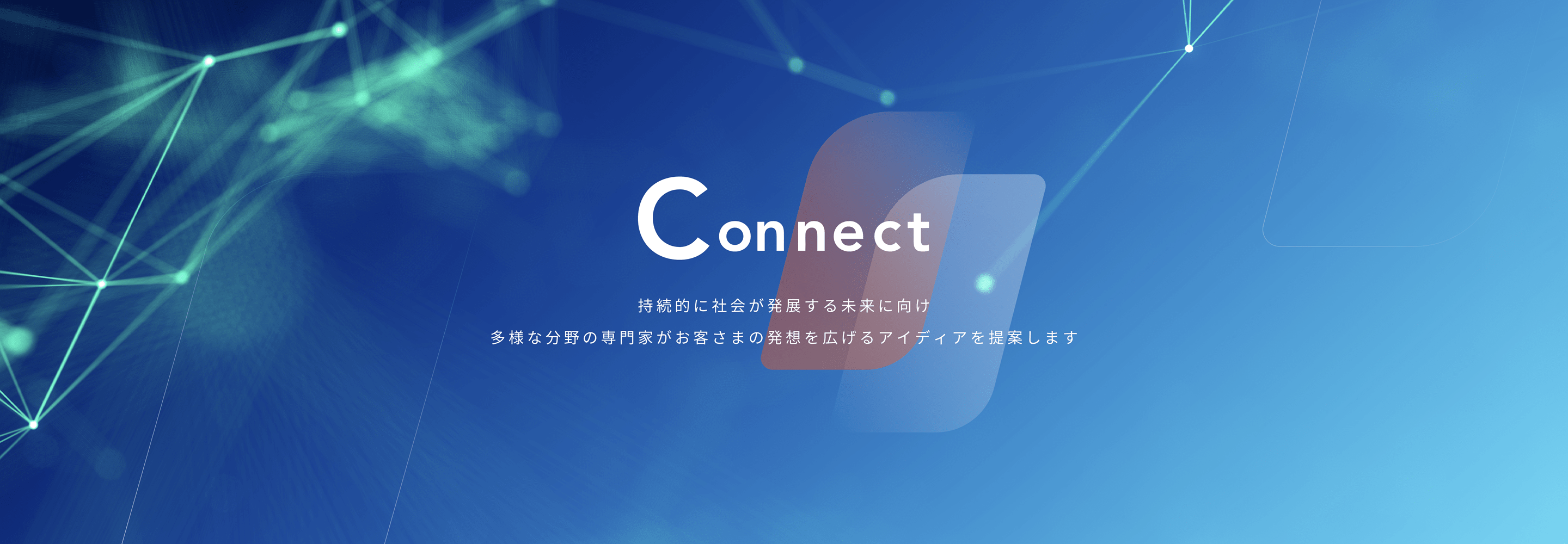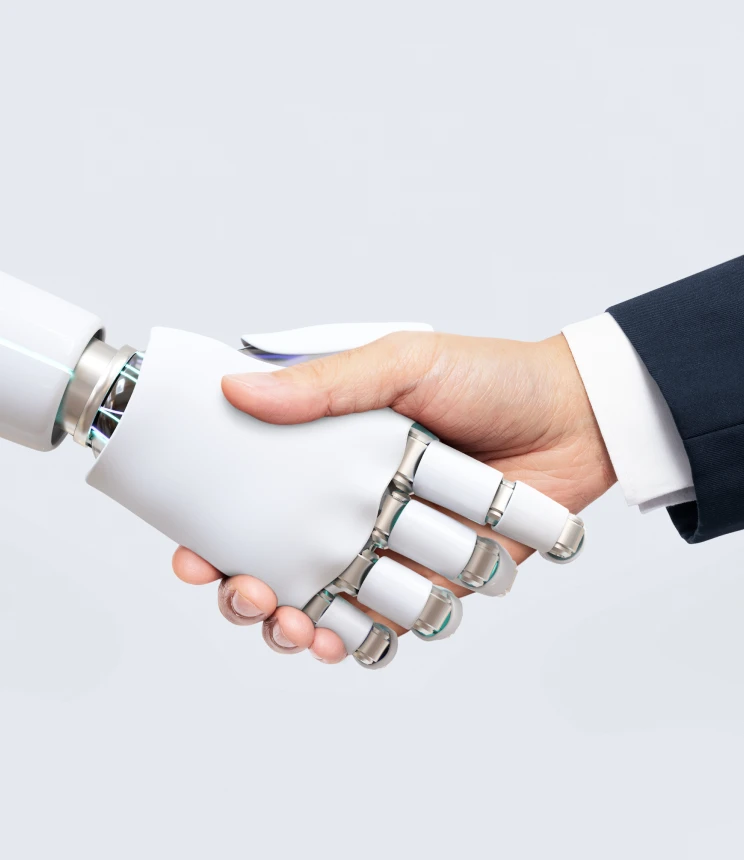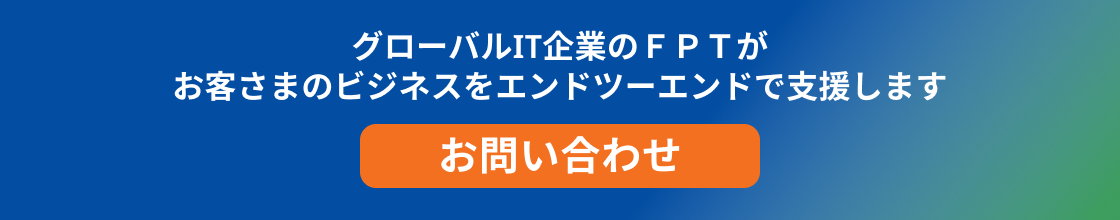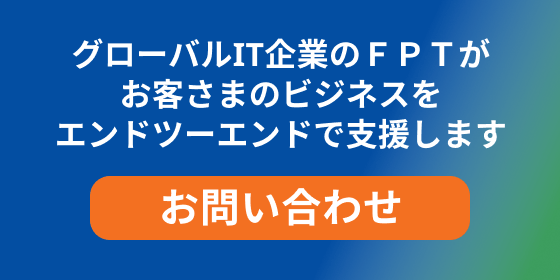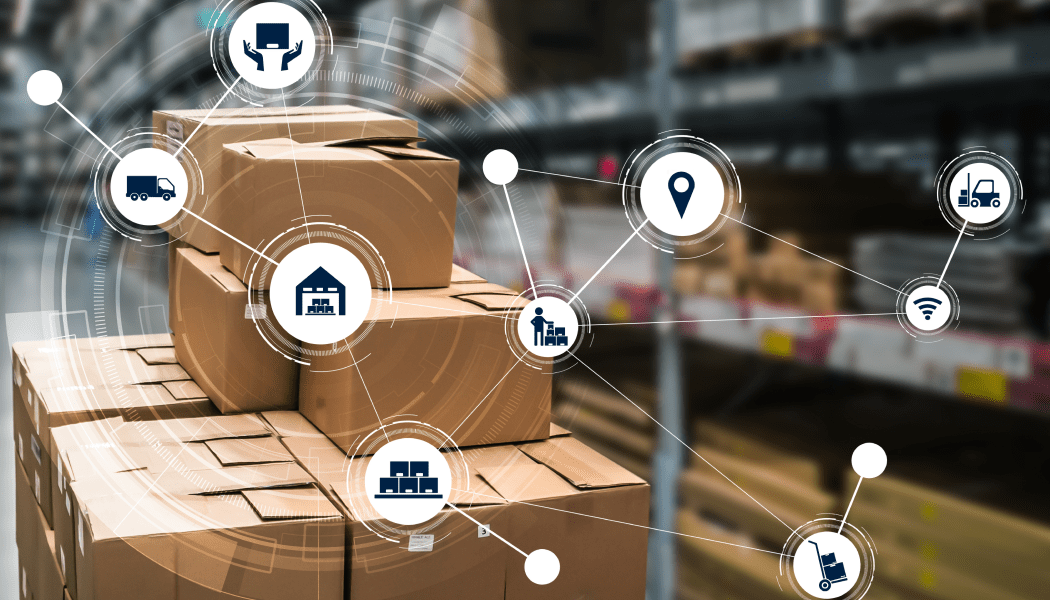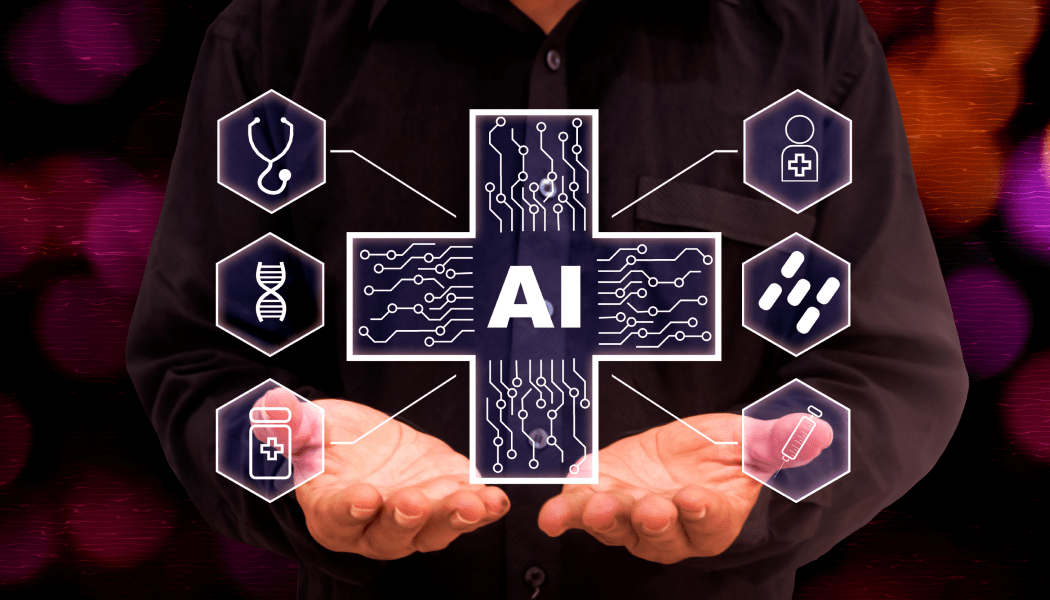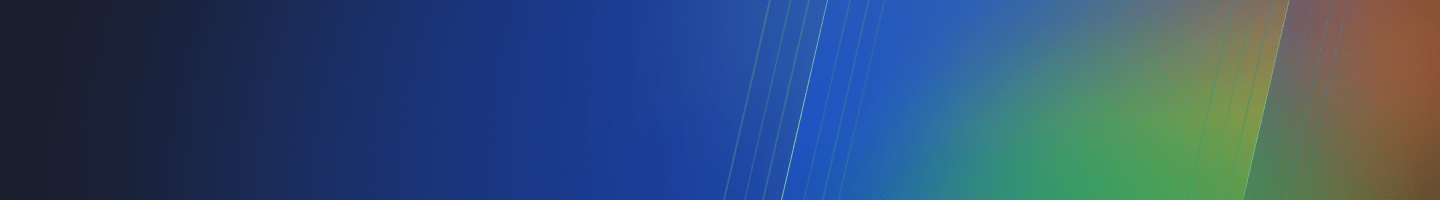目次
マイグレーションとは何か
マイグレーションとは、既存システムやデータを別の環境へ計画的に移行することを指します。部分的な修正やパッチ適用とは異なり、基盤自体を刷新することも含まれるのが特徴です。例えば、長年使っていたオンプレミスのシステムをクラウドへ移行するケースが典型です。マイグレーションには、レガシーマイグレーション、ライブマイグレーション、クラウドマイグレーションなど、複数の手法があり、既存資産を活用することで、短期間かつ低コストで実現できるというメリットがあります。

マイグレーションとリプレース・コンバージョンの違い
リプレースとの違い
マイグレーションは既存のシステムやデータを別の環境へ移行することを指します。一方、リプレースとは、古くなったシステムやサーバーを新しいものに置き換えることです。2つの違いは以下のとおりです。
| 方式 | 概要 | 目的の違い |
|---|---|---|
| マイグレーション | 現行のシステムやデータを別環境へ移す作業 | ・先端技術の導入、セキュリティ強化、運用コストの削減などを実現するため |
| リプレース | 既存システムを新しいものに取り替えること | ・長期的に安全で安定した稼働を実現するため |
コンバージョンとの違い
マイグレーションは、既存システムを新しいプラットフォームへ移すことを意味します。これに対して、コンバージョンはデータやファイルの形式を変更することを指します。2つの違いを以下のようにまとめました。
| 方式 | 概要 | 事例 |
|---|---|---|
| マイグレーション | 構成やプラットフォームを別環境へ移行 | ・WindowsからLinuxへの移行 ・サーバーのハードウェアのアップグレード ・リレーショナルデータベースからNoSQLデータベースへと移行 |
| コンバージョン | データやファイル形式の変更 | ・WordファイルをPDFに変換 ・CSVファイルをXMLファイルに変換 |
マイグレーションの主な手法について
マイグレーションの主な手法には「リライト」「リホスト」「リビルド」「クラウド移行」の4つがあります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
リライト
リライトは、既存アプリケーションの処理内容を変えずに、プログラミング言語を新しいものに書き換え、別のプラットフォームに移行することです。VBAやCOBOLで書かれたものをJAVAに書き換える例などがこれに該当します。アプリケーションが古くなると、保守や運用が難しくなります。リライトによって、これらの問題を解決するだけではなく、セキュリティ強化やコスト削減なども可能です。
リホスト
リホストとは、アプリケーションやプログラミング言語は変更せず、古いハードウェアやOSから新しいプラットフォームに移行する方法です。メインフレームからUNIXサーバーに移行する例がこれに該当します。稼働中のシステム資産を活かしながら、最新の技術基盤へ移行できるため、運用コストの削減が期待できます。また、コードを大幅に修正する必要がないため、処理時間の短縮や、トレーニング工数の低減が見込めます。
リビルド
リビルドとは、既存システムを全面的に再構築する手法です。リライトやリホストのみでは、メインフレーム依存から脱却できない場合に使われます。すべてを作り直す必要があるため、リライトやリホストよりも開発コストと時間を要します。既存システムの課題を根本的に解決できる一方で、要件定義を入念におこなわないと、手戻りが増えてしまう可能性があります。
クラウド移行
クラウド移行とは、オンプレミスからクラウドへ、あるいはクラウド間でシステムやデータを移行することです。別名「SaaS移行」とも呼ばれています。クラウドに移行するメリットは、構築や運用コストの削減に加え、サーバー増強やシステム変更を迅速におこなえることです。さらに、セキュリティ対策やBCP対応をおこないやすくなり、データの管理や活用もしやすくなります。移行を成功させるには、十分な計画と検証時間が必要です。
マイグレーションの主な種類
マイグレーションの主な種類について、以下のようにまとめました。
| 定義 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| レガシーマイグレーション | 複雑化し、ブラックボックス化したレガシーシステムを、新しいシステムへ移行・再構築すること | ・運用コストの削減ができる ・新しい技術・ビジネスモデルに対応できる |
・多くのコストや長い移行期間が必要になる |
| データマイグレーション | 既存システムで管理されているデータ群を別環境へ移行させること | ・データの保護やプライバシー体制が強化され、セキュリティリスクを低減できる ・運用コストを下げられる |
・既存データを新しい環境仕様に適応させ、データの一貫性を確保することが必要である |
| サーバーマイグレーション | 既存サーバーで稼働中のシステムを異なるサーバープラットフォームに移行すること | ・処理性能を高める | ・移行には、綿密な調査と準備が必要 |
| ライブマイグレーション | 仮想マシンを停止させず、稼働したままほかのホストへ移行すること | ・アプリケーションやサービスは停止せず、ユーザーにも意識されない ・システムの保守作業やハードウェアの更新、構成の変更などをおこなえる |
・切り替えの際、一時的にネットワークが遮断される ・高度なスキルが必要 |
| クイックマイグレーション | 仮想マシンを一時停止した状態でほかのホストへ移行すること | ・移行後もOSのシャットダウンや再起動などは不要 ・ソフトウェアの稼働状態を維持したまま移行できる |
・移行元と移行先の環境が大きく異なる場合は利用できない |
マイグレーションの流れ【業務システムをオンプレミス環境からクラウド環境へ移行する場合】
業務システムをオンプレミス環境からクラウド環境へ移行する場合の5つのステップについて解説します。

1. 企画
まず、クラウドの特性を理解し、オンプレミス環境との違いを把握したうえで、クラウドの特性を整理し、活用できる範囲と制約を明確にします。次に使用するクラウドを、AWS、GCP、Microsoft Azureから選び、移行の目的を明確にしてから、ステークホルダーの合意を取ります。全体の方向性について計画を策定したら、承認を得ましょう。
2. 戦略・分析
次に以下の情報について把握し、対象候補となるシステムや移行の順番について分析をおこないます。
▸システム情報
現状の業務システムの情報収集と整理をおこないます。同時に以下の情報についても把握します。
- 要求されるシステムレベル
- 稼働時間
- 利用者数
- システムの重要度
- 主管部門
▸インフラ情報
業務システムのサーバーのOSのバージョン、ミドルウェアを含むサーバー機器やストレージ、ネットワーク機器の情報について整理し、まとめます。
▸クラウド環境の要件
以下のようにクラウド環境の要件をまとめ、BCP(事業継続計画)において必要な要素を明らかにします。
- サービスレベル
- 可用性
- セキュリティ
- 計画停止
- 災害対策
▸クラウドベンダーの選定と移行対象の整理
クラウドベンダーを選定し、移行対象システムと想定リスクを整理したうえで、ロードマップ策定に反映します。
▸コストの概算とロードマップの策定
コストを概算し、移行の方法を検討し、ロードマップを策定します。
▸移行体制
移行プロジェクトには、新システム開発・移行作業・教育支援をそれぞれ担当する三つのチームが必要です。
3. PoC(実証実験)
ロードマップ策定後は、本番移行に先立ちPoCで検証をおこなうことをステークホルダーに周知します。PoC は複数回おこない、不具合を発見して解決していきます。ここでの検証が不十分だと、本番移行後の動作不良につながりかねません。移行を成功させるには、反復検証と修正を徹底します。
4. 設計・移行
PoCで移行の安全性が確認できたら、本番環境への移行準備をおこないます。準備が整い次第、システムの切り替えをおこない、移行担当者から運用担当者に権限を委譲します。
5. 運用・改善
運用開始後は、定期的にデータ収集と分析をおこないます。データから懸念点を把握し、原因を洗い出して改善していきます。月額利用料金を毎月確認し、変動が大きすぎる場合は、利用状況を確認しましょう。定期的な分析をおこない、PDCAを回します。
FPTのレガシーマイグレーションの取り組みや実績、サービス内容を動画でわかりやすくご紹介しています。
マイグレーションをおこなう際の4つの注意点
入念な下準備
マイグレーションでは、綿密な下準備が肝心です。既存システムの設計や運用の仕組みを把握し、問題点を洗い出します。あわせて、次のリサーチをおこないます。
- マイグレーションが必要な範囲
- 移行先の候補となるシステムの使用感
- セキュリティ
準備が不十分だと、新しいシステムが正常に稼働せず、データ不一致によるエラーも発生し、手戻りが増えます。事前調査を踏まえ、自社に合うマイグレーションを選ぶことで、スムーズな運用が可能になるでしょう。
移行可能なシステムの選択
マイグレーションには、さまざまな種類があり、対象や方法によって手間やコストが異なります。データマイグレーションは比較的容易ですが、基幹システムの移行では、プログラミング言語の変更に伴い設計の見直しを必要とすることが多く、難易度が上がります。自社の業務特性やシステム環境に応じて、移行可能なシステムを選びましょう。
従業員やステークホルダーへの周知とサポート
マイグレーションでは、従業員やステークホルダーが混乱しないよう周知し、理解を得ることが重要です。新システムへの切り替えは、作業フローに大きな影響を与えるため、操作方法の説明や研修の機会を設けるなど配慮が必要となります。
アウトソーシングの検討
社内にマイグレーションの専門知識を持つ担当者がいない場合、外部の専門家に依頼するのも有効です。マイグレーションには工程が多く、すべてを社内でおこなうのは困難です。業者を選ぶ際は、必要なスキルやノウハウを持ち、十分な実績がある企業を選定することが重要になります。業者選定では、以下のポイントをチェックしましょう。
- どのような業界とシステムのマイグレーション実績があるのか
- マイグレーションの規模はどの程度か
- 移行後のサポートはどこまで可能か
- メンテナンスの条件は何か
マイグレーションの目的と課題
システムの老朽化対策やセキュリティ強化、故障リスクの回避を目的に、マイグレーションが実施されています。経済産業省はレガシーシステムの放置がもたらす経済損失として「2025年の崖」に警鐘を鳴らしており、その回避手段としてもマイグレーションは有効です。一方で、レガシーシステムがブラックボックス化しているため、データ移行は複雑になり、テストに伴う工数・コストは増え、マイグレーションの専門人材も不足するなどの問題が発生しています。

まとめ
既存システムを別の環境や新しいプラットフォームに移行するマイグレーションは、システムの老朽化対策やセキュリティ強化、故障リスクの回避に有効です。マイグレーションにはレガシーマイグレーションやデータマイグレーションなど、さまざまな領域があり、自社の状況に合う手段を選ぶことが重要です。多工程で専門性が高いマイグレーションをスムーズにおこなうには、実績が豊富な専門業者を選び、マイグレーションを成功させましょう。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- レガシーシステムのモダナイゼーションとアプリケーション開発
- FPTのレガシーモダナイゼーションサービス紹介
- SAP S/4 HANAマイグレーション
- FPTとTRANSWAREが協業関係を強化するための覚書を締結
関連ブログ:コラム
- COBOL言語とは何?特徴や構成、書き方、課題を徹底解説
- オフショア開発で起こりがちな失敗事例と原因、成功させるコツを解説
- オフショアの意味、活用のメリット・デメリット、成功事例を紹介
- CASE - 自動車業界に与える影響と求められる技術革新
- サイバーセキュリティとは-サイバー攻撃の種類と企業が講じるべき対策