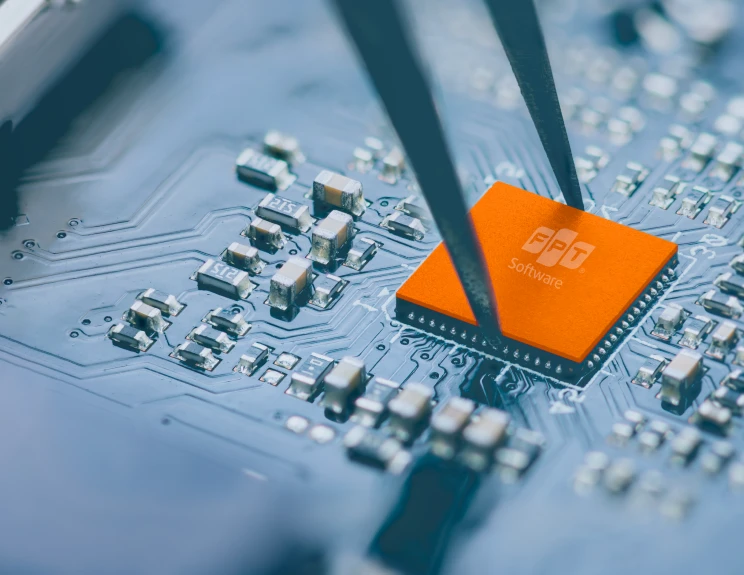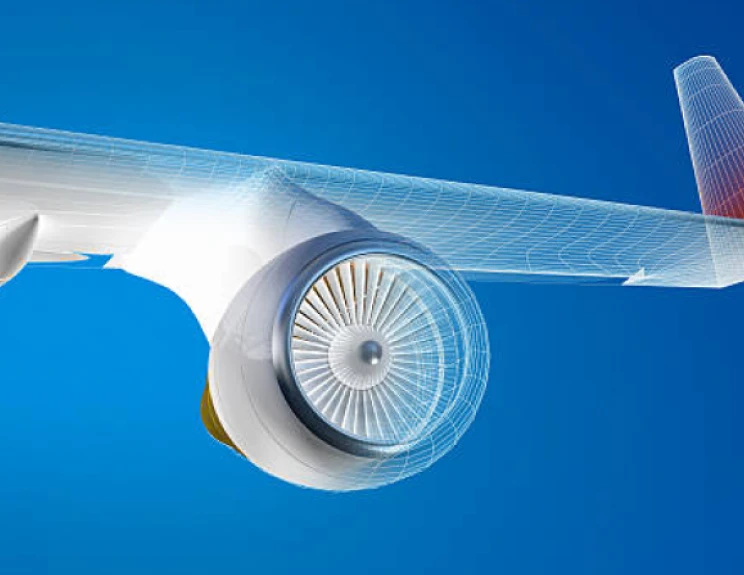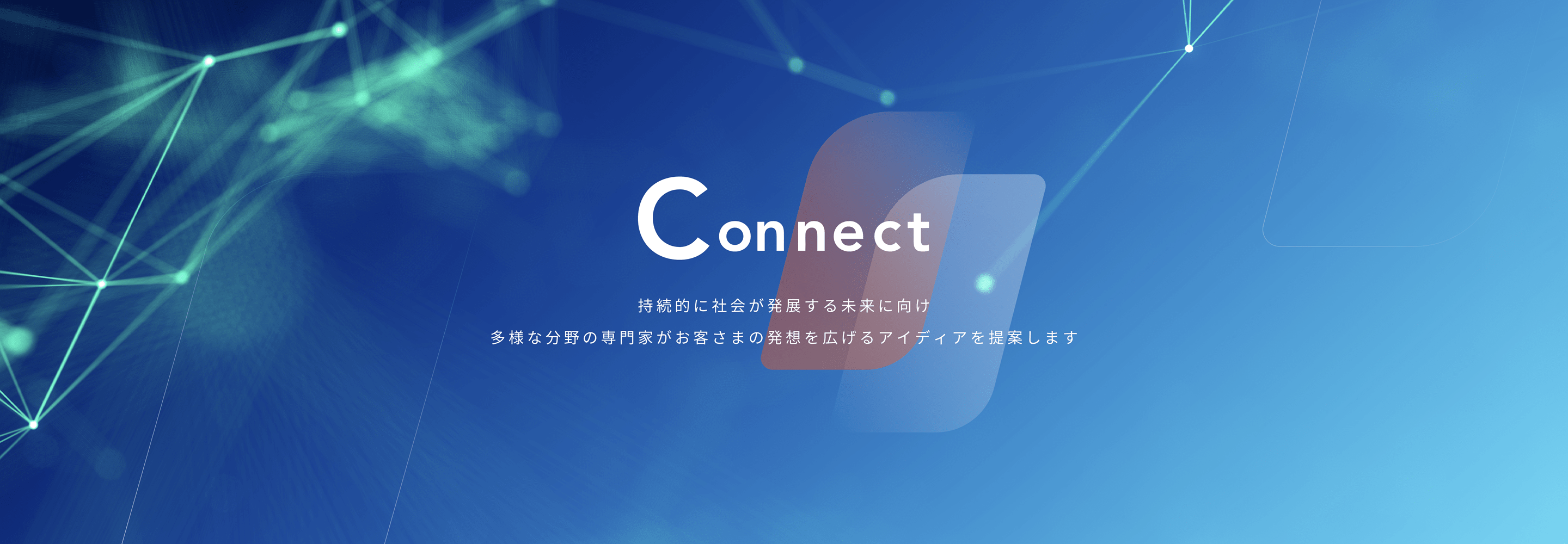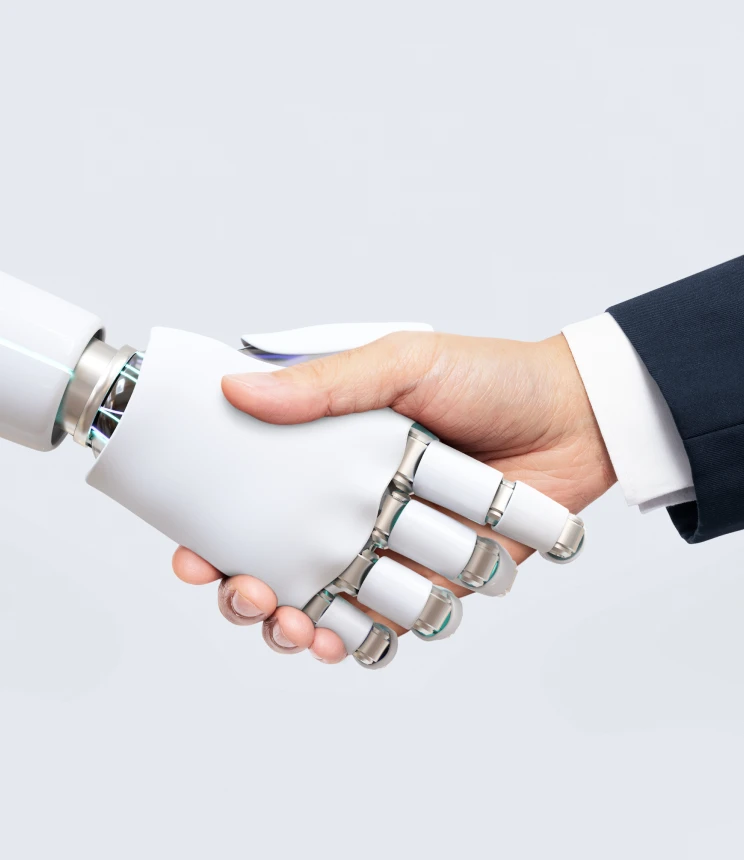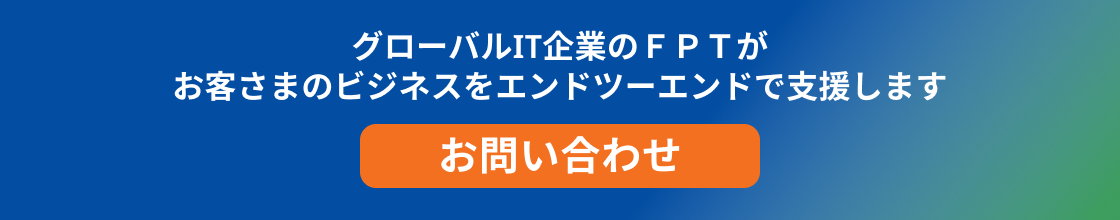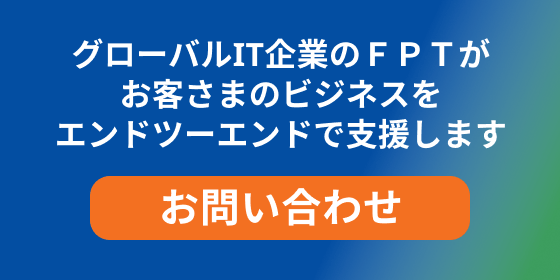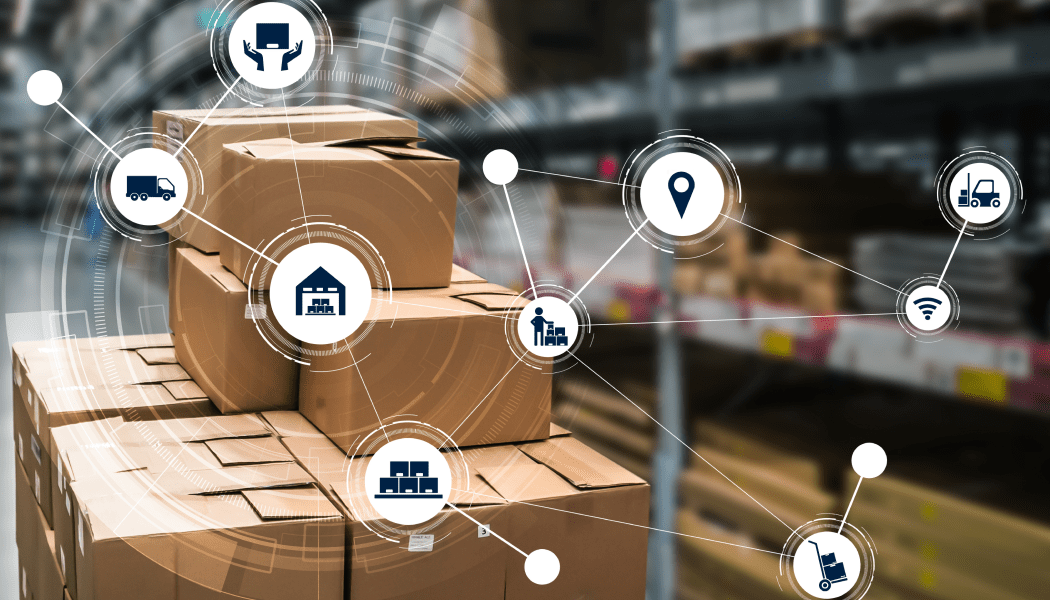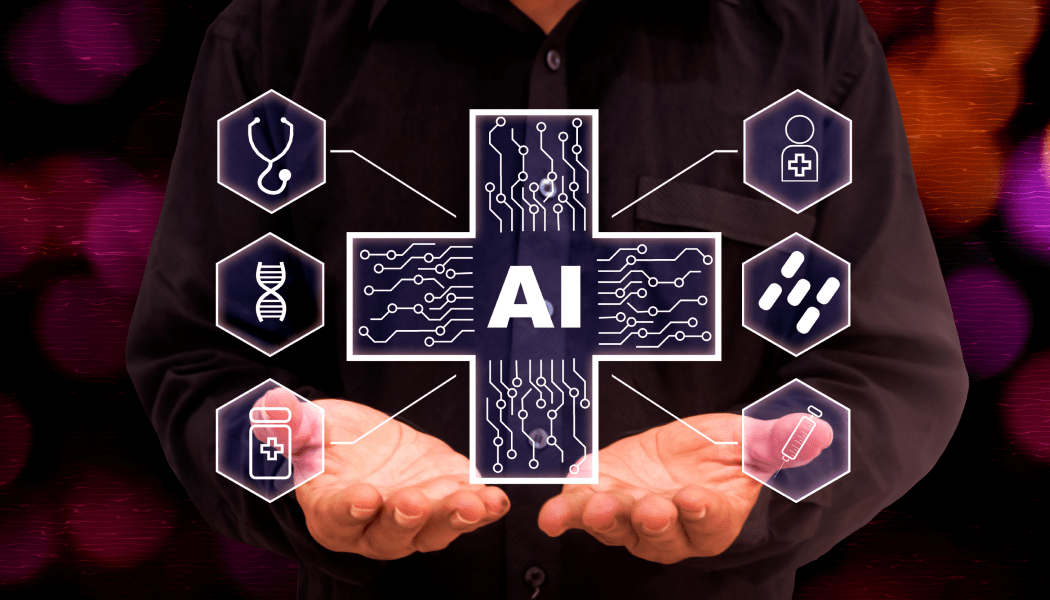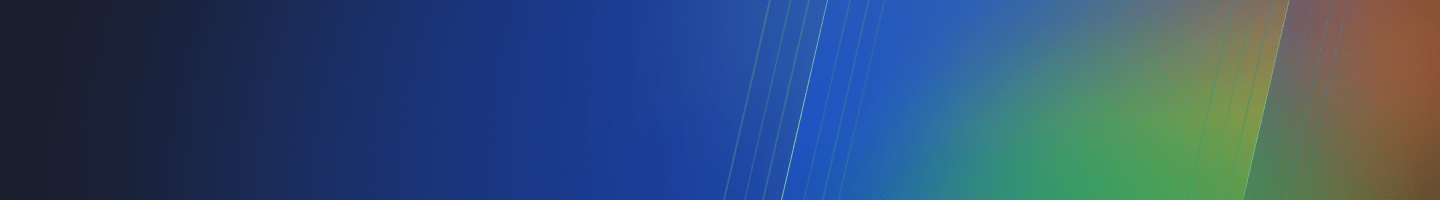目次
SOC(Security Operation Center)とは何か

SOCとはSecurity Operation Centerの略称で、企業や組織の情報システムを24時間365日監視・分析し、セキュリティインシデントの検知から対応までを担う専門組織です。
DDoS攻撃やマルウェア感染、サーバーとの不正な通信や不正なログイン試行、SQLインジェクションやゼロデイ攻撃など、サイバー攻撃は高度化・複雑化しています。こうした多様化したサイバー攻撃に対応するため、SOCはSIEM(セキュリティ情報およびイベント管理)、EDR(エンドポイント検出対応)、SOAR(セキュリティオーケストレーション、自動化および対応)などのツールを活用しています。また、多くのSOCは24時間365日の監視体制を構築しています。
SOCの導入が進む背景
SOCの導入が進む背景には、サイバー攻撃の複雑化や高度化、件数の増加などが挙げられます。
総務省によると、2023年の総観測パケット数は、2015年の約632億パケットの約9.8倍となる約6197億パケットにも及びます。そのうち約3割がIoT機器を狙った攻撃であり、サイバー攻撃の手法は急速に進化しています。こうした高度化する脅威に対応するには、ログ分析をはじめとする高度な専門知識が不可欠となっています。
経済産業省もまた、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を2023年に改訂し、経営者が果たすべき役割を促しています。同ガイドラインでは、セキュリティインシデントに対応する組織の構築が明記されており、経営戦略の観点からもSOCの重要性が高まっています。
SOCの人員構成
SOCの主要な人員構成として、SOCオペレーター(L1アナリスト)、セキュリティアナリスト(L2アナリスト)、SOCエンジニア(L3アナリスト)が挙げられます。
L1アナリストは、アラートの監視や異常検知、初動対応など、一次対応を担います。このため、24時間365日体制でアラートを監視する必要があります。L2アナリストは、L1アナリストから引き継いだアラートに対し、詳細分析や脅威の特定、被害範囲の確認など、二次対応をつかさどります。L3アナリストは、フォレンジック調査やインシデント対応計画の策定など、高度な対応が求められます。
SOCと他のセキュリティ対策の違い

SOCと似た用語として、
- CSIRT
- MDR
が挙げられます。そこで、以下にSOCとCSIRT、MDRの違いを整理します。
CSIRT(Computer Security Incident Response Team)との違い
CSIRTはComputer Security Incident Response Teamの略称であり、セキュリティインシデントが発生後の対応を行います。たとえば、インシデントの影響範囲の特定や被害の最小化、原因の究明、再発防止策の策定などが挙げられます。一方、SOCはセキュリティインシデントの監視・検知を主な役割とし、SIEMなどのツールを活用してリアルタイムでアラートを分析します。
両者はこのように役割分担されていますが、ログ分析や初期対応など、実務上は重複する領域も存在します。
MDR(Managed Detection and Response)との違い
MDRはManaged Detection and Responseの略称で、監視や検知に加えて、封じ込めや復旧支援などの対応まで提供する外部サービスを指します。専門知識のあるエンジニアが自社にいなかったり予算をかけられなかったりする場合には、MDRにSOC業務やCSIRT業務を委託します。
つまり、MDRは監視・検知を担うSOCと、対応・復旧を担うCSIRTの機能を統合し、外部サービスとして提供するソリューションです。
SOCの4つの役割と重要性
SOCの役割として、
- 脅威の監視とセキュリティイベントの検知
- セキュリティインシデントの対応と報告
- 分析・調査によるセキュリティレベルの向上
- SIEMの活用
の4つが挙げられます。そこで、各役割の概要や重要性について解説します。
脅威の監視とセキュリティイベントの検知
SOCには、組織のネットワークやシステムを常時監視し、不審な通信や挙動を早期に発見する役割があります。具体的には、SIEMやEDRといったツールでログやアラートを管理し、相関分析によって異常を見つけます。不審な通信や挙動といったアラートは膨大なため、重要度や緊急性を知識と経験に基づいて見極める必要があります。
この役割の目的は、攻撃の初期段階で兆候を捉え、被害を最小化することです。これにより、潜在的な脅威を迅速に発見し、早期対応につなげることができます。
セキュリティインシデントの対応と報告
検知したインシデントに初動対応し、必要に応じてCSIRTや関連部門に引き継ぐ役割も担っています。具体的には、対応手順に基づいて、隔離・遮断などの緊急措置を実施します。同時に、インシデントの発生日や事象、影響、対応方針などを記録・報告します。
こうしたタスクの目的は、被害の拡大を防ぎ、組織全体での迅速な意思決定を支援することです。これにより、インシデントの影響を最小限に抑え、経営層や規制当局への報告に役立つ証拠を残すことが可能です。
分析・調査によるセキュリティレベルの向上
発生したインシデントやログを詳細に分析・調査し、セキュリティの改善に活用する役割も担っています。分析の対象は、削除されたファイルの復元やログの解析、不正プログラムの特定、アクセス履歴の調査、データ流出経路の特定、攻撃者の絞り込みなど広範に及びます。
この役割の目的は、再発防止策を講じ、検知ルールやシステム設定を最適化することです。これにより、組織全体のセキュリティレベルを継続的に強化し、未知の脅威にも対応できる体制を構築できます。
SIEM(Security Information and Event Management)の活用
SIEMとは、SOCで活用される中心的なツールであり、さまざまなログを一元的に収集、分析、管理できます。たとえば、複数のシステムや機器からのログデータを前処理し、相関分析によって不審な挙動を検知します。
SIEMを活用する目的は、セキュリティインシデントにつながる挙動を検知し、未然に防ぐことです。SIEMを活用することで、攻撃の全体像を把握し、迅速かつ正確な対応につなげられます。また、監視の精度が向上することで、SOCの効率的な運用とコンプライアンス対応が可能になります。
SOCの2種類の運用形態

SOCの運用形態として、自社で行うケースと外部にアウトソースするケースの2種類が挙げられます。そこで、内部SOCと外部SOCの特徴や機能、メリット・デメリットについて解説します。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 内部SOC | ・カスタマイズ性の高さ ・セキュリティに関するノウハウが蓄積 |
・24時間365日体制で多くの人材やコストがかかる ・専門知識を持つ人材の確保や育成が困難 |
| 外部SOC | ・少ない人材で24時間365日の監視が可能 ・ノウハウを持った人材を容易に確保できる |
・外部にログなどの内部情報を渡すことが情報漏洩のリスクにつながる ・自社に応じたカスタマイズが難しい |
内部(自社)SOC
自社のIT部門やセキュリティ部門が自前で運営するのが、内部(自社)SOCです。内部SOCの特徴として、自社のネットワークやサーバー、端末、プライベートクラウドなどを直接監視し、インシデント対応を内製化することが挙げられます。
内部SOCのメリットとして、自社のセキュリティポリシーに合わせて、きめ細かな監視・対応ルールを設定できるなど、カスタマイズ性の高さが挙げられます。また、社内にノウハウが蓄積されることで、組織のセキュリティ文化が長期的に醸成されます。
内部SOCのデメリットとして、24時間365日体制での運用には多くの人材とコストが必要なことが挙げられます。また、専門知識を持つ人材の確保や育成が困難な点も課題となります。
外部(アウトソース)SOC
外部SOCとは、MSSP(マネージドセキュリティサービスプロバイダー)などのベンダーにSOC機能を委託する形態を指します。外部SOCの特徴として、クラウド基盤を通じてログやイベントを収集し、外部の専門家が監視・分析・対応を実施することが挙げられます。
外部SOCのメリットは、24時間365日体制の監視を少ないリソースで実現できることです。このため、大規模な投資が難しい中小企業でも導入しやすくなっています。また、最新のセキュリティノウハウを持つ専門人材を活用できることも大きな利点です。
外部SOCのデメリットは、ログやインシデント情報を外部に提供すること自体がセキュリティリスクとなる点です。また、SOC業務を外部委託するため、自社特有のニーズに応じたカスタマイズが難しいことも課題となります。
FPTのSOCは、業界標準と独自AI技術でお客さまごとに最適化。24時間365日、あらゆる環境・規模に柔軟対応します
SOCの導入を成功させるポイント
「SOCを導入すれば高度なセキュリティ対応が可能になる」という評判だけで安易に導入すると、運用が回らず形骸化する恐れがあります。SOCの導入を成功させるポイントとして、
- 要件定義による目的や範囲の明確化
- IT資産・情報資産の監視システム導入
- セキュリティ人材の採用・育成
- 業務の手順・ルールの見直し
の4点が挙げられます。以下では、これらのポイントについて解説します。
要件定義による目的や範囲の明確化
事前に要件定義を行い、目的と範囲を明確化することが重要です。たとえば、「どの資産を守るのか」や「監視対象は何か」、「対応範囲はどこまでか」を定義することで、無駄のない設計が可能となります。また、ルールの実効性を確保するため、処罰規定を作成しておくとよいでしょう。
要件があいまいなまま導入すると、過剰な監視や不十分な対応に陥るリスクがあります。違反時の対応フローを含めた明確な要件定義により、運用開始後の改善や外部委託時の契約条件を適切に管理できます。
IT資産・情報資産の監視システム導入
PCの操作ログやWeb閲覧履歴、メール送受信履歴など、監視対象の資産を正しく把握し、可視化するために、IT資産・情報資産の監視システムを導入することが挙げられます。こうした監視システムは、ネットワーク機器、サーバー、クラウド、エンドポイント、アプリケーションなどからログを収集できる体制を取る必要があるでしょう。SIEMの導入も、こうしたログの一元管理に貢献します。
一貫した監視体制を取っていないと、サイバー攻撃が見逃される恐れがあります。正確な資産管理と監視体制の基盤を整えることが重要です。
セキュリティ人材の採用・育成
SOCの運用は人材に大きく依存するため、セキュリティ人材の採用や育成が不可欠です。たとえば、L1オペレーターによる24時間365日体制での監視、L2アナリストによる詳細調査、L3アナリストによる高度な分析といった多層的な体制を構築する必要があります。
自社でSOCチームを構築するためには、セキュリティ専門家の採用や若手人材の育成プログラムを計画的に行う必要があります。また、外部研修への参加なども人材育成につながります。仮に外部ベンダーに委託する場合でも、自社側で監視結果を理解できる人材を採用・育成する必要があるでしょう。
業務の手順・ルールの見直し
SOCを導入する前段階として、これまでのセキュリティインシデントの対応業務の手順やルールの見直しが求められます。たとえば、私物デバイスの利用制限やUSBをはじめとする記録媒体の使い方、閲覧権限を付与する範囲の決定など、多くの業務やルールの見直しが必要です。また、すでにセキュリティインシデントの対応が確立されている場合でも、対応マニュアルを定期的に更新し、実際の攻撃事例に対応できるようにしましょう。
手順が不明確だと検知しても対応が遅れ、被害が拡大する恐れがあります。SOCだけでなく、経営層や法務部門を含めたルールを整備することで、組織全体の対応力の向上につながります。
SOCを外部委託する際の選び方

SOCを外部委託する際のベンダーの選び方として、まず必要なサービスを提供しているかどうかを確認します。オンプレミスやクラウド、エンドポイントなど、監視範囲が自社ニーズと合致しているかどうかを見極める必要があります。
次に、サービスの品質を評価します。24時間365日の監視体制が整備されているか、インシデントの検知から通知までの手順が明確化されているかを確認しましょう。また、報告レポートが経営層にも理解しやすい形式で提供されるかも重要なポイントです。
さらに、コストが適切かどうかを総合的に判断する必要があります。SOCは長期契約になる傾向があるため、予算に見合わないコストでは継続的な運用が困難になります。
これらの条件を総合的に比較し、自社にとって最適な外部ベンダーを選定することが、成功の鍵となります。
まとめ
SOCは、単なるサイバー攻撃の複雑化・高度化に対応するための仕組みではありません。企業の機密情報や顧客の個人情報がサイバー攻撃によって漏洩した場合、企業の信頼性を大きく損なうだけでなく、コンプライアンス違反による法的リスクも発生します。セキュリティ人材が不足している現在、SOC運用に必要な専門家を自社だけで確保するのは容易ではありません。そのため、外部の専門サービスの利用は、有効かつ現実的な選択肢となっています。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
関連ブログ:コラム
- 今注目のAIエージェントとは?他のAI技術との違いやビジネス活用事例を解説
- GPUとは?CPUとの違いや種類・性能、選び方までわかりやすく解説
- LLMとは?生成AIやChatGPTとの違い、活用事例をわかりやすく解説
- クラウド(Cloud)とは?種類やサービス例をIT初心者にわかりやすく解説
- 生成AIの主なツール13選 - 従来のAIとの違いや効果的な使い方を解説