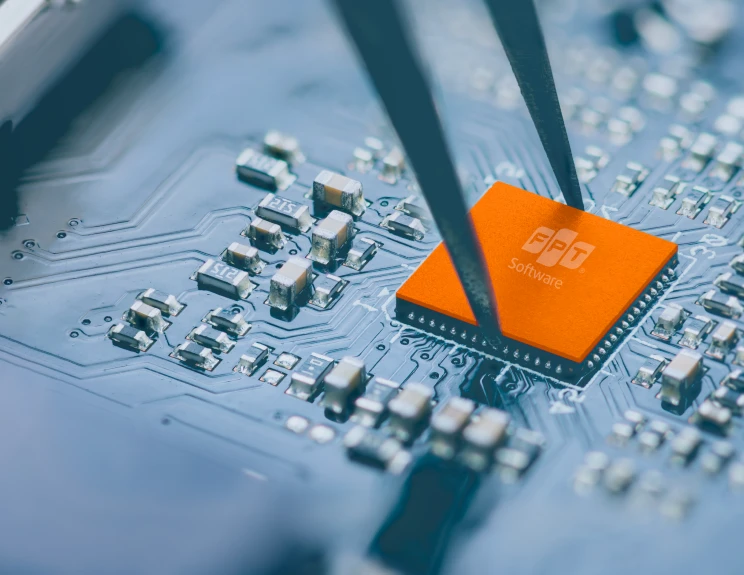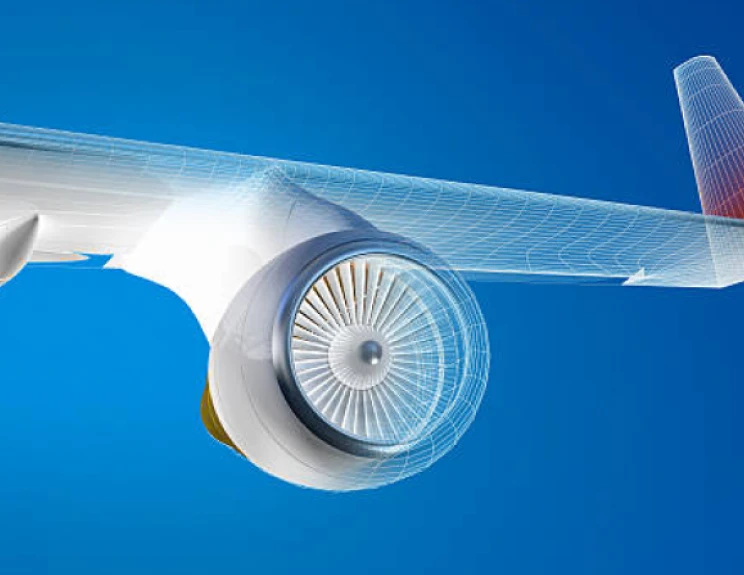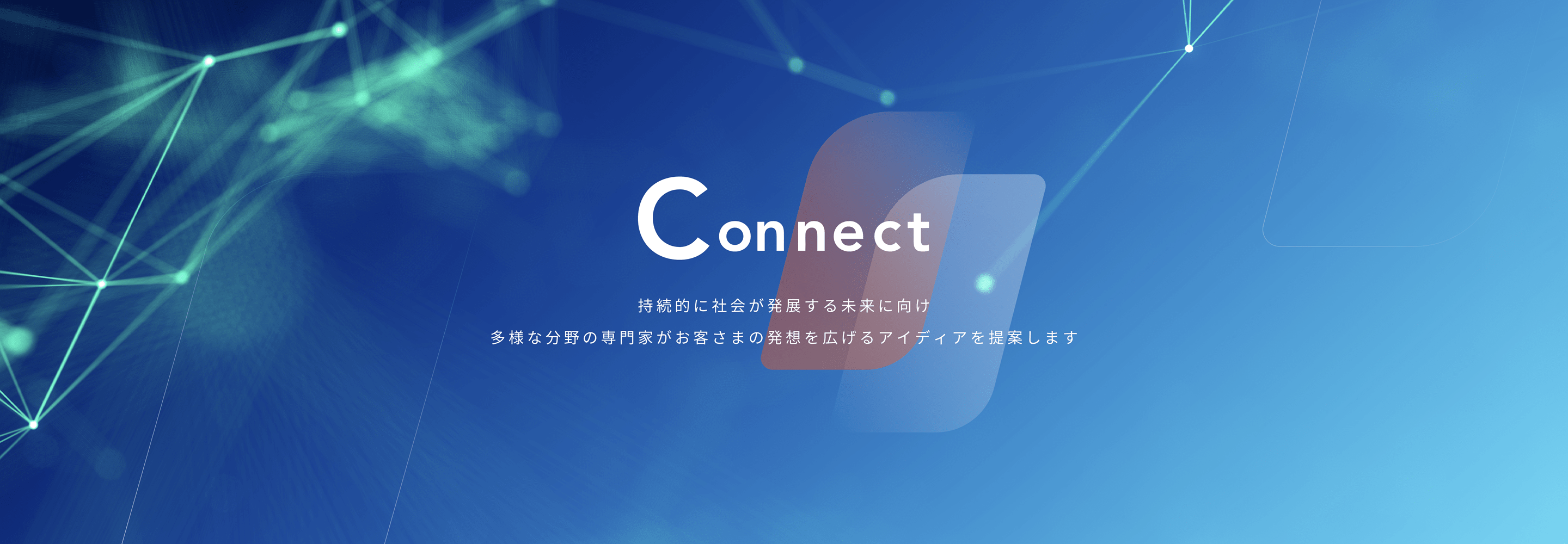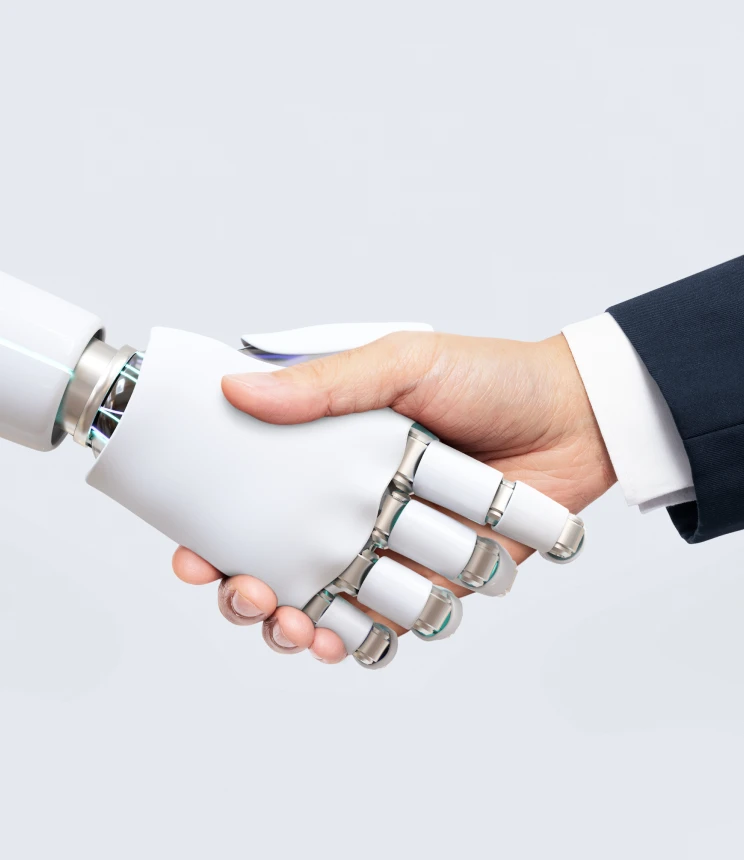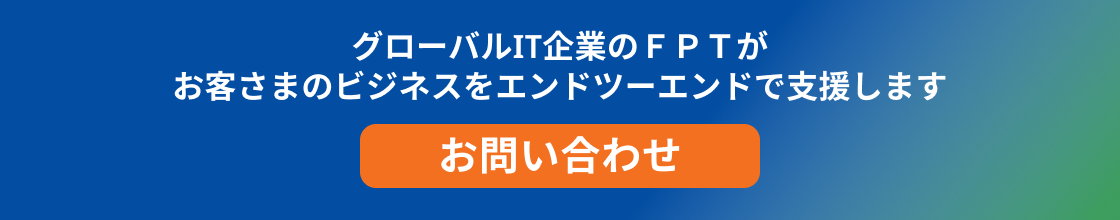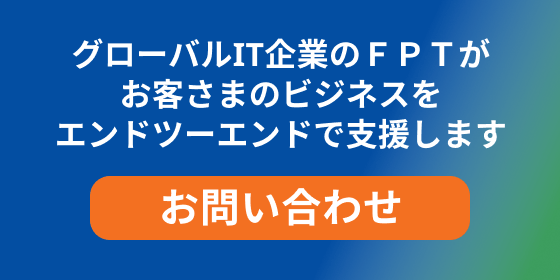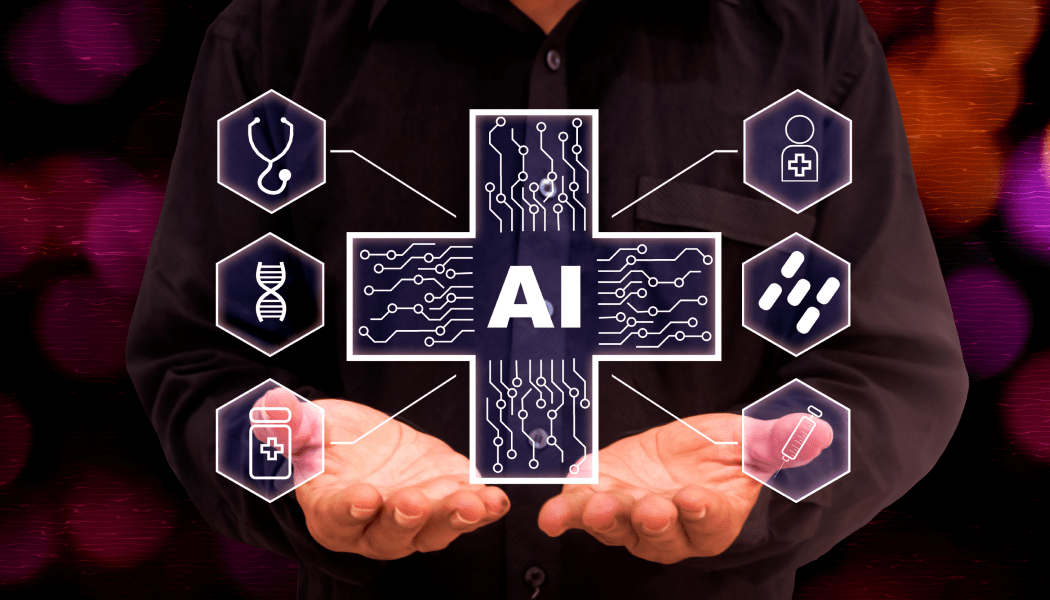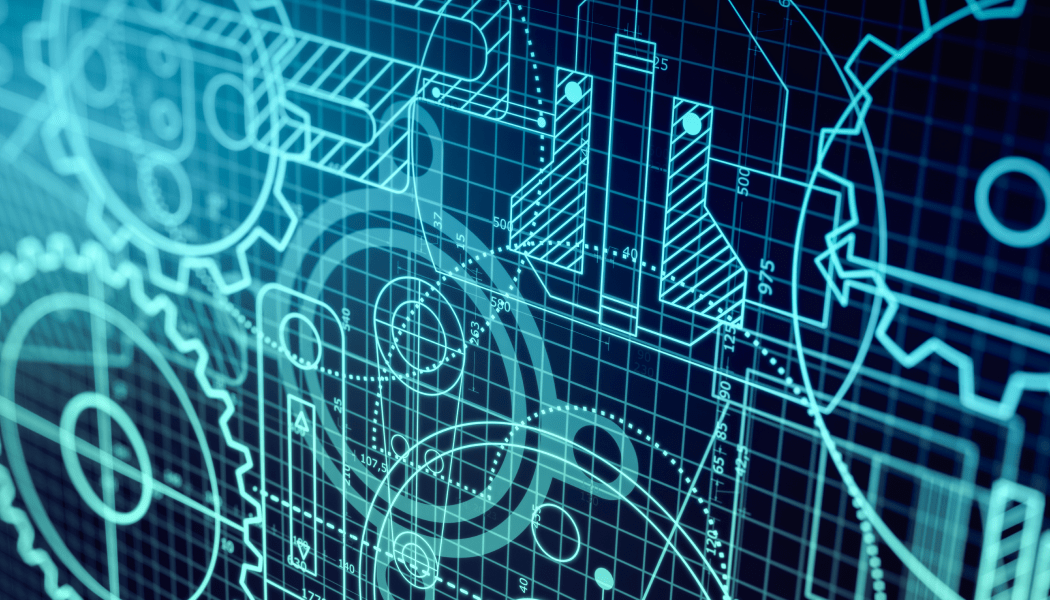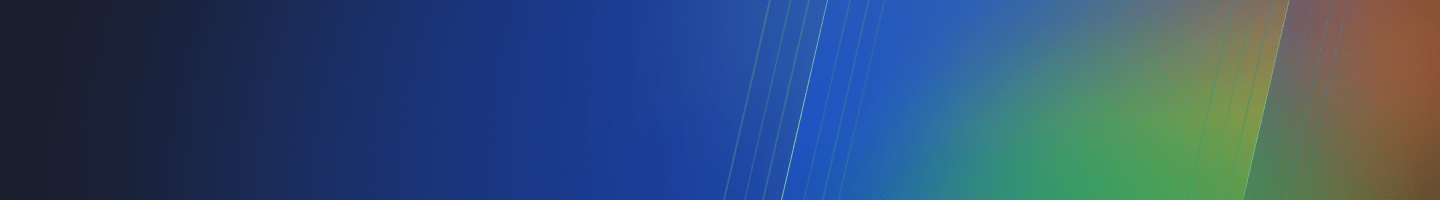目次
GPU(Graphics Processing Unit)とは

GPU(Graphics Processing Unit)とは、コンピューターの描画処理を担当する装置です。複雑な計算処理を同時に大量に行うために設計された半導体チップで、3Dグラフィックスや映像を高速に描画する目的で開発されました。しかし近年では、その強力な並列処理能力を活用してAIや機械学習、科学技術計算などのさまざまな分野で利用が拡大されています。
GPUの最大の特徴は、数百から数千もの計算を同時に処理できることです。これは、GPUに大量のコア(演算ユニット)が搭載されているためで、同じ計算を多くのデータに一度に適用できます。
たとえば、画像や動画の編集、シミュレーションなど、同じ処理を大量に繰り返す作業に特に適しています。このような並列処理能力こそが、GPUの強みなのです。
GPUの登場から現代までの進化
GPUの起源は、1970年代から1980年代に登場したグラフィックコントローラーと呼ばれるデバイスです。当初は2次元画像の簡単な描画を行い、CPUの負荷を軽減する程度の機能でした。1990年代に入ると「IRIS GL」や、その後継として標準化された「OpenGL」などのグラフィックライブラリが登場し、専用ハードウェアと組み合わせて映画産業などで活用されるようになりました。
また、1990年代後半には、MicrosoftのWindowsを搭載したパーソナルコンピューターが普及し始め、3Dグラフィック表示機能を担うハードウェアを想定したグラフィック・アクセラレーターが登場します。2000年代に入ったころ、グラフィック・アクセラレーターが「GPU」と呼ばれるようになり、パソコン用のグラフィックボードに専用チップとして搭載されるようになりました。
その後、GPUはプログラム可能な並列演算装置として進化し、さらに画像処理以外にも科学技術計算や機械学習などに活用されるようになりました。現在では、クラウド上のGPU利用や小型デバイスへの組み込みなども含め、活用シーンが多様化し、グラフィック処理装置の枠を超えた役割を果たす存在になっています。
「CPU」との違い
CPUとGPUは、コンピューターで担う役割や目的が異なります。CPU(Central Processing Unit)は、コンピューターの制御や演算などを行う中枢的な存在です。OSやアプリケーションに必要な処理について、一つ一つの命令を順番に高速で処理するという特徴を持っています。一方GPUは、同種の計算を一斉に実行する並列処理が特徴です。CPUが数個から数十個のコアで処理を行うのに対し、GPUは数百から数千個の演算ユニットで処理をするため高速です。
そもそもGPUは、画像処理やゲーム、アニメーションなど、大量データの同時演算を行う分野で活用する、より専門的な目的のために生み出されました。しかし、現代のPCやサーバーでは、CPUとGPUの両方を活用してシステム全体のパフォーマンスを高める構成が一般的になっています。
GPUが注目されている背景
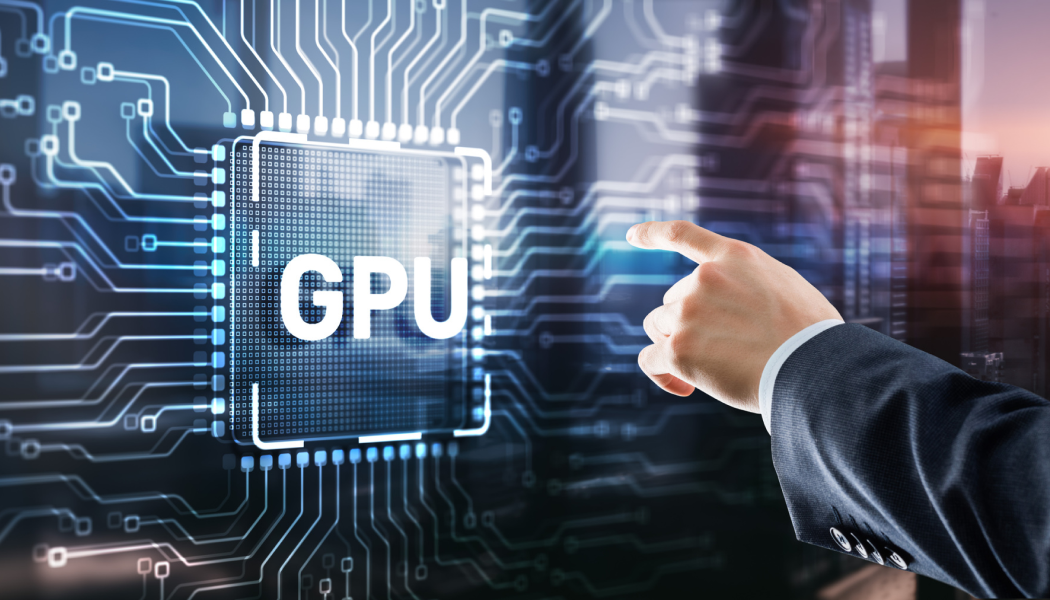
従来、GPUは主にゲームやグラフィック処理の専門チップとして知られていました。しかし近年、その役割は大きく変化しています。ここでは、GPUが注目されている背景について見ていきましょう。
機械学習やディープラーニングとの相性がよい
AIや機械学習の分野では、莫大な計算リソースが必要です。そこで活用されているのが、多数の演算ユニットを持ち、画像認識や自然言語処理などの同種の計算を大量かつ同時に実行できるGPUです。特にディープラーニングでは、大規模なニューラルネットワークの学習に膨大な時間がかかりますが、GPUを活用することで、この処理時間を大幅に短縮できるのです。CPUだけでは現実的ではなかったAIモデルの開発や高度な実験が、GPUの並列処理能力によって可能になりました。このように、機械学習やディープラーニングとの親和性の高さが、GPUが注目される大きな理由となっています。
産業分野での活用拡大
GPUの活用は、IT分野を超えて多様な産業分野へ広がっています。例えば、製造業では、画像解析による自動検査や不良品の早期発見などにGPUが活用されています。また、医療分野では、MRI画像などの医用画像への応用、近年では気象予想や自動運転などの研究開発分野においてもGPUの計算能力が活用されています。このように、産業の現場での成果がGPUの需要をさらに押し上げているのです。
クラウドサービスの発展によるGPU利用の拡大
従来、GPUを活用するためには、高価な専用ハードウェアを自社で調達して管理する必要がありました。しかし近年、AWSや国内クラウドサービスがGPUリソースをインターネット経由で利用できる環境を整えています。クラウドGPUのメリットは、初期投資や保守コストを抑えながら、常に最新で高性能なGPUを活用できる点にあります。これにより、AI開発やシミュレーション、ビッグデータ解析を始めたい企業や研究機関が手軽にGPUを利用できるようになりました。クラウドサービスの普及によるGPU利用範囲の拡大も、GPUが注目される背景の一つです。
GPUの身近な使用例
GPUは、高度な科学計算やAI分野だけではなく、私たちの日常やビジネスの現場でも広く活用されています。ここでは、GPUが実際にどのような場面で活躍しているのかを見ていきましょう。
ゲーム・映像表現での圧倒的な役割
GPUは3Dゲームや映像制作の分野に活用する目的で進化した技術です。PCや家庭用ゲーム機、スマートフォンなどに搭載されているGPUは、きれいな映像や滑らかなアニメーションの描画を実現しています。CGアニメーションや映画のVFX(視覚効果)でもGPUの計算能力は欠かせません。近年では、VRやARといった分野でもGPUの性能が不可欠で、エンターテイメント業界で広く活用されています。
AI・データ分析現場でのGPU活用
AIやデータ分析の現場では、GPUの並列処理性能が不可欠です。ディープラーニングや画像認識、自然言語処理や音声分析など、膨大なデータを同時に学習・解析する作業はCPU単体では時間がかかりますが、GPUを用いることで大幅な効率化が可能になります。ビジネスの現場では、顧客行動の分析や需要予測、AIチャットボットなどにGPUが使われており、サービスの品質向上や迅速な意思決定につながっています。
シミュレーションや研究分野での高性能計算
GPUは科学技術計算やシミュレーションの分野でも活用されています。例えば、気象予測や分子動力学、自動車設計などでは、計算時間を短縮できるのです。また、多くのスーパーコンピューターは、CPUとGPUを組み合わせて大規模な並列計算を実現しています。
ブロックチェーンや暗号資産マイニングへの利用
ビットコインやイーサリアムといった暗号資産や、そのインフラ技術を担うブロックチェーンでもGPUが重要な役割を果たしています。例えば、ビットコインのマイニング(採掘作業)では膨大な計算を高速で解く必要があります。そこで、GPUの並列演算能力が適しているのです。データセンター規模のマイニングファームでも、GPUが活用されています。
※ビットコインのマイニングでは、現在はGPUよりもASIC(特定用途向け集積回路)が主流です。
GPUの3つの種類

GPUは、用途や設計によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、主要な3つのGPUタイプについて見ていきましょう。
1. ディスクリートGPU(dGPU):グラフィックボード
ディスクリートGPU(discrete GPU)は、マザーボードの専用スロットに差し込んで使うグラフィックボードやビデオカードに搭載される独立したGPUを指します。ディスクリートGPUの強みは、演算能力とVRAM容量が大きく、3Dゲームや動画編集、機械学習の学習用サーバーなど、高負荷がかかる用途に適している点です。
また、独立したデバイスであるため、必要に応じて複数枚を搭載して性能向上ができるという特徴もあります。性能を最優先にしたい現場や、高速なデータ処理が求められる作業に選ばれるGPUです。一方、消費電力や発熱量が大きいため、電源や冷却ファンの増設を意識しなければなりません。価格面でも高価な製品が多い点にも注意しましょう。
2. 統合GPU(iGPU):内蔵型
統合GPU(integrated GPU)は、CPUやチップセット内部に一体化したGPUです。ノートPCやタブレット端末など、消費電力やコストを抑えたい場面で採用されています。統合GPUのメリットは、ディスクリートGPUと比べて消費電力が少なく、発熱も抑えられるため、小型・軽量を実現しやすい点です。
ただし、演算能力やVRAM容量はディスクリートGPUに比べて小さく、高解像度映像編集や機械学習のような大規模計算には適していません。ウェブ閲覧や動画視聴といった一般的な作業であれば十分なパフォーマンスを発揮します。
3. 仮想GPU(vGPU):クラウド
仮想GPU(virtual GPU)は、物理的なGPUを仮想化し、複数のユーザーやサーバーがクラウド経由で共有できる技術です。AWSなどが提供するクラウドサービスを利用して、必要なときだけGPUリソースを割り当てる運用が増えています。仮想GPUの最大のメリットは、初期投資や運用管理の負担を減らせる点、そして新しいGPU環境を利用できる点にあります。物理的なハードウェアを導入する必要がないため、拠点間での共同作業や一時的なリソース増強にも対応可能です。
インターネット回線の帯域や速度に左右されることや、クラウドサービスの利用料がかかるといったデメリットはありますが、多くの企業や研究機関での利用も増えています。
高性能なコンピューティングGPUクラウドサービスを提供し、トップレベルのパフォーマンス、柔軟性、スケーラビリティを実現。大規模なAIモデルの開発・運用を加速させます
GPUを選ぶうえで重要なポイント
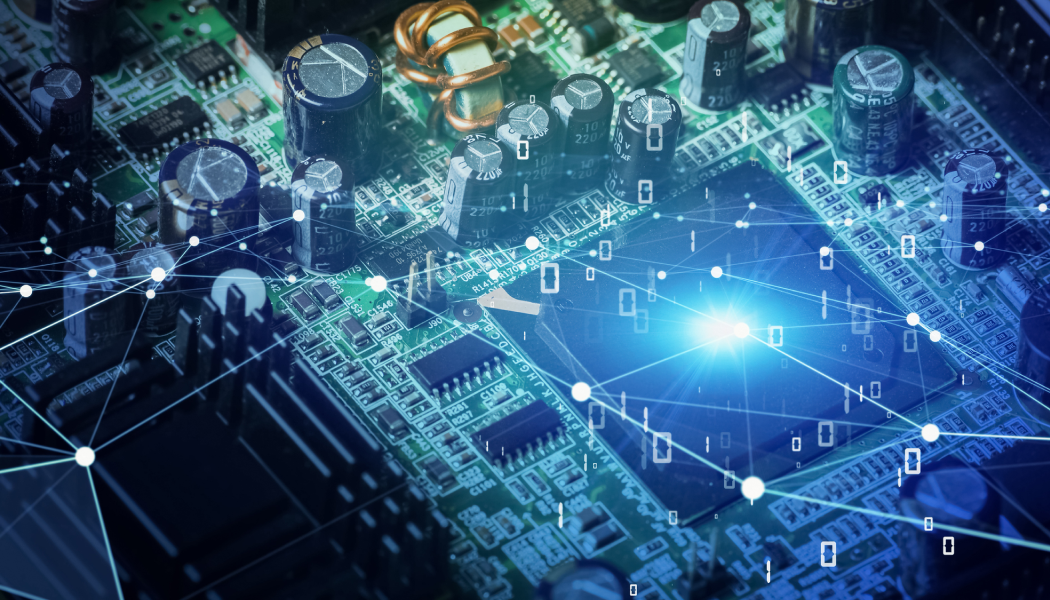
GPUにはさまざまな種類があります。用途やシステム環境によって最適なものを選択しなければなりません。ここでは、GPU選定で確認すべきポイントを見ていきましょう。
VRAM(ビデオメモリ)容量で選ぶ
GPUのVRAM(ビデオメモリ)は、画像やデータを一時的に保存するための専用メモリです。動画編集などで大量のデータを扱う場合、VRAM容量が不足するとパフォーマンスが大きく低下します。VRAMの容量が大きいほど、より大規模で複雑なデータを扱うことができますが、容量に比例して価格も高額になるため、用途に応じた適切な容量を選ぶことが大切です。
例えば、小規模で趣味程度の作業ならば8GB程度、高解像度画像を扱う場合には12GB程度、AI開発現場などの大規模な処理が必要な場合は24GB以上など、基準を明確にしておくとよいでしょう。
メモリ帯域・速度で選ぶ
メモリ帯域幅は、GPUとVRAM間でデータをやり取りする際の「道路の広さ」に例えることができます。帯域幅が広いほど大量のデータを短時間で転送できるため、高解像度映像の処理や複雑な計算がスムーズに実行されます。例えば、リアルタイムレンダリングや科学技術計算など、膨大なデータを頻繁に読み書きする用途では、メモリ帯域も選定基準として重要なポイントになります。
消費電力で選ぶ
GPUは、性能が高いほど消費電力も増大します。ハイエンドのディスクリートGPUやデータセンター向けモデルでは、消費電力が数百Wに達するものもあります。例えば、ノートPCやサーバーを自社に導入する際は、電源ユニットの容量や配線、発熱や冷却設計なども確認することが不可欠です。省エネや静音性を重視する場合は、消費電力の低いモデルを選ぶとよいでしょう。
冷却性能で選ぶ
GPUは冷却性能も必要です。特にハイエンドモデルは動作中の発熱が大きいものもありますので、冷却ファンやヒートシンクなどが重要な役割を果たします。冷却性能が不足すると、処理速度の低下やシステムの強制停止を招く可能性があり、ハードウェア故障の原因になる場合もあります。そのため、GPU選定では冷却性能についてもしっかりと検討しなければなりません。
PCとの相性で選ぶ
GPUは、PC本体やサーバーの筐体に合わせたものを選ぶ必要があります。グラフィックボードのサイズやケースに収まるか、電源やマザーボードの規格に対応しているかなど、物理的な相性の確認が重要です。また、ドライバやOSの互換性、使用するアプリケーションの適合性にも注意しましょう。スペック上の数値だけでなく、システム全体のバランスや拡張性も考慮することが、適切なGPU選定につながります。
GPUの将来性
GPUは、今後もさらなる進化と拡大が期待されています。AIや機械学習、クラウドサービスとの連携やエッジAI向けの軽量GPUなど、用途ごとに最適化された新型GPUの開発も活発です。
また、クラウド型のGPUサービスが普及することにより、小規模な企業や個人の研究者も最先端のリソースを利用できる環境が整うようになりました。今後はGPU同士の連携や分散処理環境の構築も容易になります。これにより、量子コンピューターなどの新しい技術領域でもGPUが重要な役割を担うかもしれません。GPUは、単なる演算装置ではなく、産業や社会を支える基盤としてその存在感を増していくでしょう。
GPUに関するよくある質問
GPUの主要メーカーとその特徴
GPUの主要メーカーとしてはNVIDIA、AMD、Intelの3社がよく知られています。NVIDIAはAI性能に優れ、データセンターで圧倒的なシェアを誇ります。AMDはコストパフォーマンスが高く、ゲーム機やPC向けで幅広く採用されています。IntelはCPUとの連携を強みに、エントリー向け製品に注力しています。用途や予算に応じて、各メーカーの特徴を理解し、最適なGPUを選ぶことが重要です。
GPUとグラフィックボードの違いは?
GPUはグラフィックボードに搭載される半導体チップで、画像や映像の処理を担います。一方、グラフィックボードはGPUに加え、VRAMや冷却ファンなどを備えた拡張カードで、PCに取り付けることで高性能な描画やクリエイティブ作業を可能にします。両者の役割を理解することで、目的に合った製品選びがスムーズになります。
GPUを選ぶ際の注意点は?
GPUを選ぶ際は、モデルや発売時期を確認し、予算と性能のバランスを考慮することが重要です。さらに、前述の『GPUを選ぶうえで重要なポイント』を踏まえて、GPUの数やVRAM容量、冷却性能、消費電力、サイズ、接続端子などもチェックしましょう。事前に仕様と環境を確認し、性能とコストのバランスを見極めることが、失敗しない選定のポイントです。
まとめ
GPUは、従来のグラフィック専用装置という枠を超え、AIや機械学習、データ分析や日常業務にいたるまで、幅広い現場で不可欠な存在となっています。特に、法人の情報システム担当者やAI活用を進める技術者にとって、GPUの特徴や選定ポイントを理解することは、導入効果や運用効率を大きく左右する重要なテーマです。用途や規模、運用コストなども考慮して、自社に合ったGPUを選択しましょう。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- AI(人工知能)サービス
- 事例紹介:実践で活きる生成AIソリューション
- FPTがAIプラットフォーム「FleziPT」を発表し、グローバルな企業変革を加速
- FPTは、企業のAIエージェント活用を支援する「FPT AIXサービス」の提供を開始
- 「FPT AI Factory」が世界の最速スーパーコンピュータTOP500に選出 商用クラウドプロバイダーとして日本第1位を獲得
関連ブログ:コラム
- クラウド(Cloud)とは?種類やサービス例をIT初心者にわかりやすく解説
- CRMとは?機能や導入メリット、活用方法と導入事例まで解説
- ランサムウェアとは?被害事例や感染経路、被害防止対策を解説
- ICT(情報通信技術)とは何? IT、IoTとの違いや教育・介護・医療現場での活用例を徹底解説
- OutSystems(アウトシステムズ)とは?メリット・デメリットや将来性、導入方法まで解説