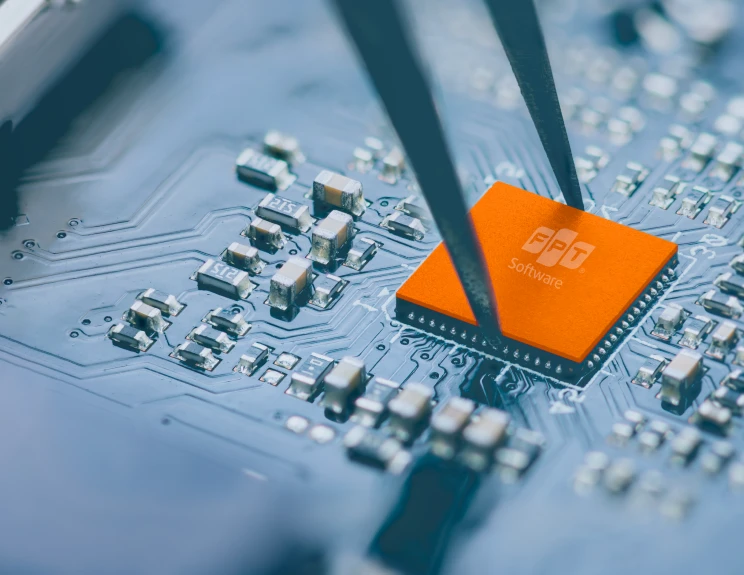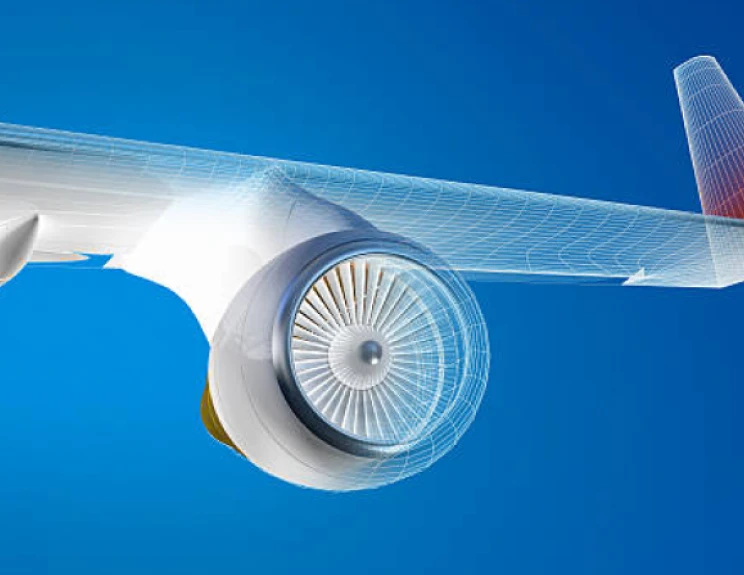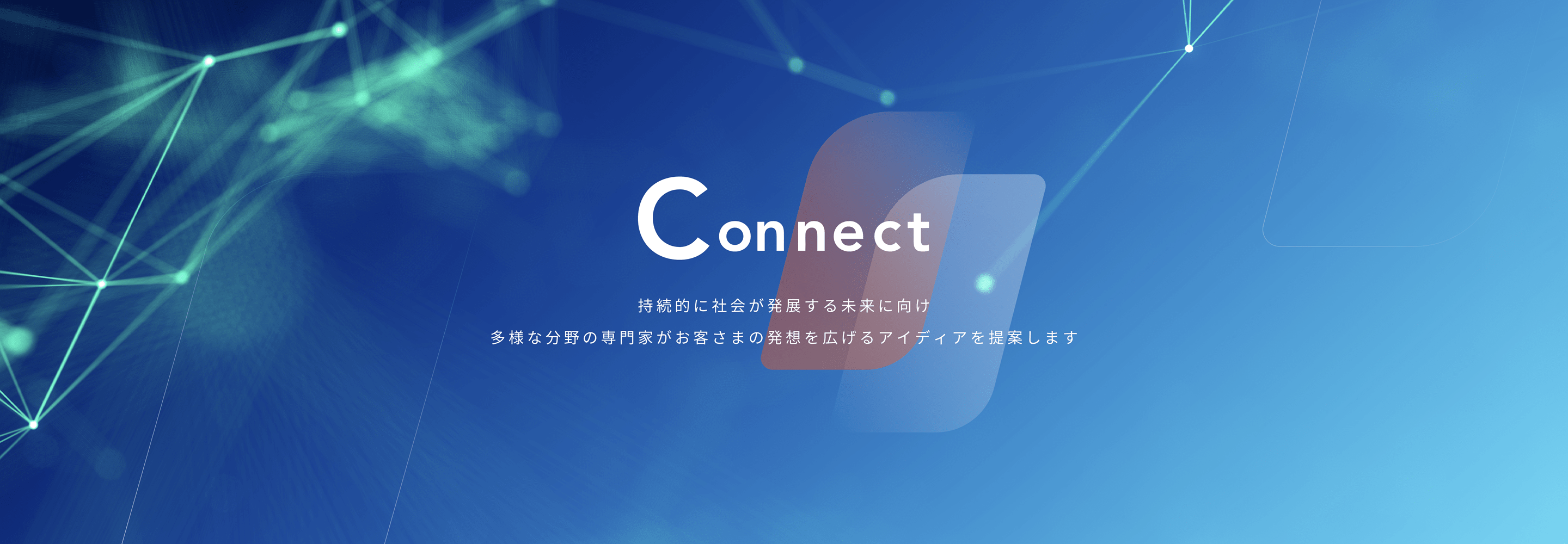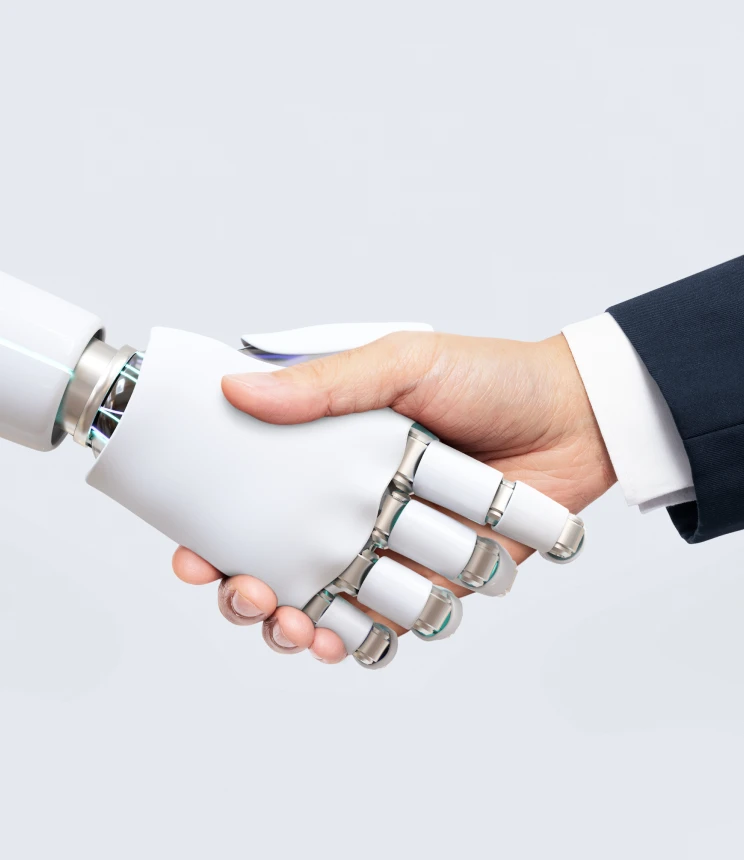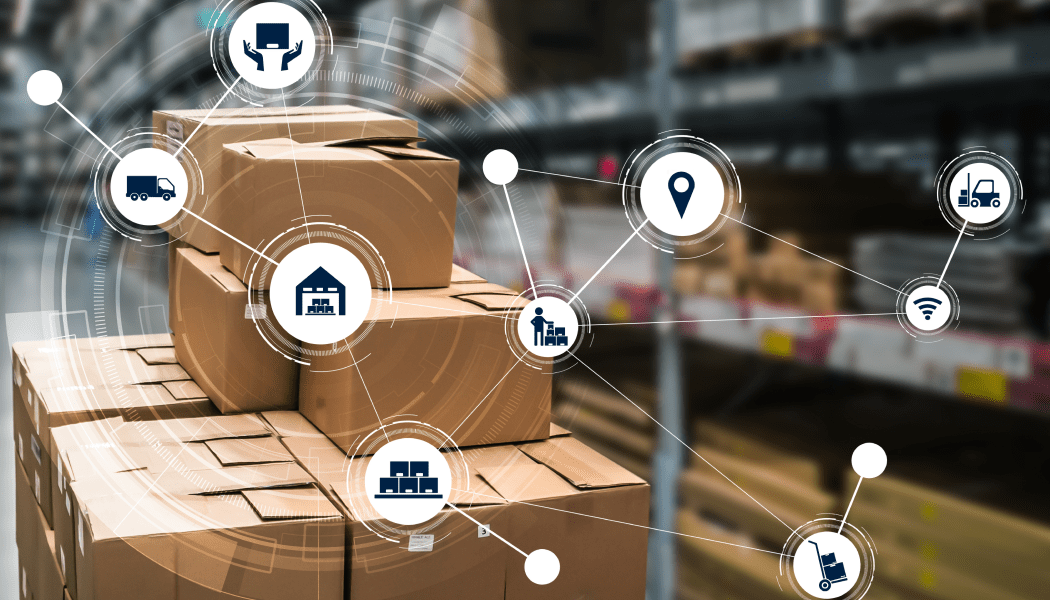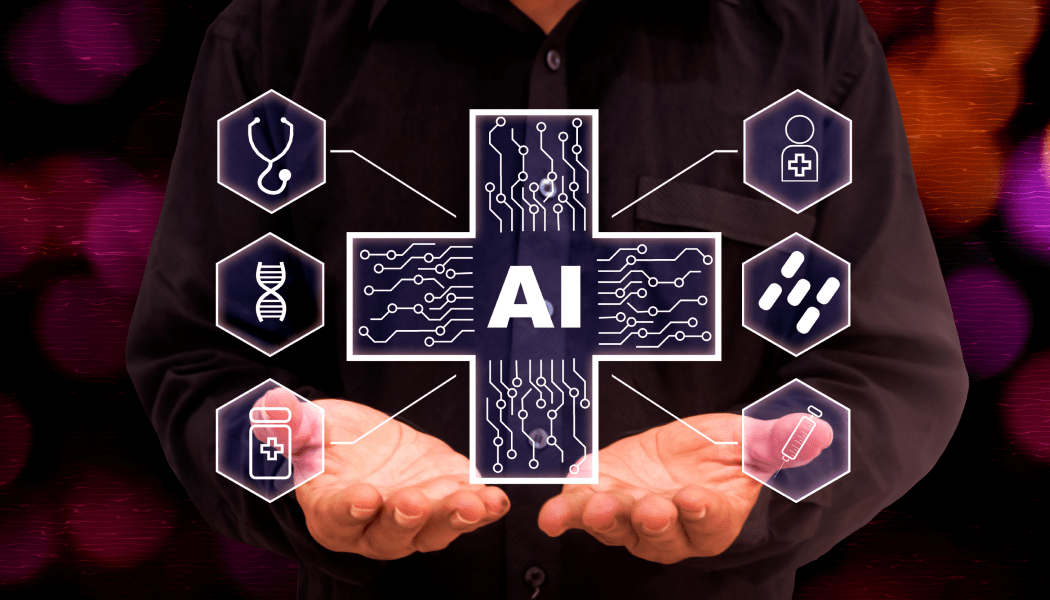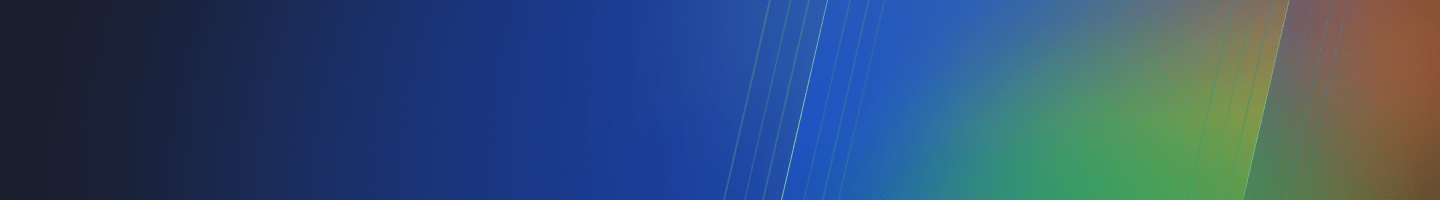厚生労働省が推進する「医療DX令和ビジョン2030」の概要とは
自由民主党の調査部会は2022年5月、医療DXと医療情報の有効活用を進めるための「医療DX令和ビジョン2030」を提言しました。これを受け、厚生労働省が中心となってプロジェクトを推進しています。医療DX令和ビジョン2030を整理すると、次の3つの論点にまとめられます。
- 「全国医療情報プラットフォーム」の整備
- 電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討
- 診療報酬改定DX
そこで、医療DX令和ビジョン2030の3つの論点について詳しく解説します。

(1)「全国医療情報プラットフォーム」の整備
「全国医療情報プラットフォーム」は、「医療DX令和ビジョン2030」※1 で掲げられた、医療DXを推進するための中核的な取り組みの1つです。このプラットフォームでは、国が中心となり、電子カルテや検査・投薬履歴などの医療情報を全国規模で統合する共通基盤を構築します。具体的には、患者IDを基軸に、地域や医療機関の枠を超えてデータを共有し、救急・転院・災害時にも迅速に参照できる体制を整える計画です。また、これらの医療情報には、マイナンバーカードと一体化した健康保険証(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を通じてアクセスできるようになります。
(2)電子カルテ情報の標準化、標準型電子カルテの検討
電子カルテ情報の標準の策定と、それを実現するための標準型電子カルテの検討も掲げられています。従来、各医療機関の電子カルテ形式が異なるため、情報共有の妨げとなっていました。こうした現状を是正し、「HL7 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)」など国際標準に準じた、電子カルテ情報を共通のデータ形式にする標準化に取り組んでいます。
また、電子カルテ情報の標準に基づき、政府は「標準型電子カルテ」と呼ばれるシステムの開発を検討しています。これが実現すれば、異なる医療機関の間でも医療データの相互利用が可能となります。
(3)診療報酬改定DX
診療報酬改定DXとは、これまで医療機関ごとに行っていた改定対応を、可能な限り国側で一元化する取り組みです。その狙いは、関係者の作業負担を軽減・平準化することにあります。
診療報酬は原則2年に一度改定されるため、医療機関やベンダーにはソフトウェアの改修や国の解釈通知への対応が求められます。改定DXでは、算定・請求・審査のプロセスを電子化し、紙ベースでの処理や審査遅延の解消につなげます。さらに、医療データを分析して実態を可視化し、エビデンスに基づく報酬改定のサイクル確立を目指しています。
医療DXが注目される背景
医療DXが注目される背景として、次の3点が挙げられます。
- 少子高齢化と医療需要の増大
- 医療関係者の長時間労働の是正
- コロナ禍で露呈した医療システムの脆弱性
以下では、これらの背景について解説します。
少子高齢化と医療需要の増大
内閣府『令和5年版 高齢社会白書』※2 によれば、65歳以上の人口は3,624万人で、総人口の29.0%を占めています。日本は世界でも高齢化が最も進んでいる国の1つです。これに伴い、慢性疾患や複合疾患の患者が増え、医療需要は一段と拡大しています。
一方で、地方では医師や看護師の不足が深刻化し、現場の負担が常態化しているのが実情です。こうした課題を踏まえ、医療DXを推進してデータ共有や遠隔医療を進め、効率的な医療提供体制を築くことが求められます。
医療関係者の長時間労働の是正
厚生労働省が2023年に公表した「医師の勤務実態について」※3 では、時間外・休日労働が年間換算で1,920時間を超える医師の割合は9.7%でした。また、働き方改革の推進によりその割合は3.6%まで低下しました。しかし、長時間労働の傾向は依然として残っています。この状況を踏まえ、2024年4月施行の「医師の働き方改革に関する法律」※4 だけに頼るのではなく、医療DXの導入・定着も並行して進めることで、医師の負担軽減と長時間労働の是正を着実に図っていく必要があります。
コロナ禍で露呈した医療システムの脆弱性
2020年初頭から始まった新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、全国の病床情報や発熱外来の混雑状況など、医療リソースの可視化が不十分であることが浮き彫りになりました。情報連携が紙やFAX、電話ベースであったことも、対応の迅速化を妨げる一因となりました。こうした反省を踏まえ、平時や有事を問わずリアルタイムで医療データを共有できる全国的な仕組みの整備が求められています。
医療DX推進のご相談ならFPTへ
医療DXを推進するメリット

医療DXを推進するメリットとして、次の4点が挙げられます。
- 患者の利便性と安全性の向上
- 医療従事者の業務効率化と負担軽減
- 医療にかかるコストの削減
- BCP(事業継続計画)の強化
それぞれのメリットを具体的にみていきましょう。
患者の利便性と安全性の向上
全国で診療情報・検査情報・処方情報を参照できるようになれば、検査の重複や薬の飲み合わせによるリスクを防げます。さらに、オンライン診療や遠隔モニタリングの活用により、通院が難しい高齢者や地方在住者でも受診へのハードルが下がります。くわえて、患者自身も健康データを把握・管理できるようになり、病気の予防やセルフケアの向上につながります。
医療従事者の業務効率化と負担軽減
診療情報や検査情報、処方情報などをクラウド連携することで、カルテ記録や照合作業の手間を削減できます。これにより、看護師や事務職は記録や報告の時間を短縮し、患者対応時間の確保にも直結します。また、AIを活用したカルテ作成の自動化により、医師の事務負担を軽減できます。さらに、勤務時間管理やシフトの最適化により、医療従事者の働き方改革の支援が可能です。
医療にかかるコストの削減
医療DXにより、業務の運営や医療材料・薬剤の在庫、経営などにかかるコストの削減が実現します。まず、カルテや紹介状、調剤管理などを紙ベースからクラウドベースに移行することで、印刷費用や紙の保管コストを削減。また、医療機器や薬剤の在庫管理を一元化することで、医療資源を最適な期間・分量で分配することが可能です。さらに、業務効率化により人件費の削減にもつながります。このほか、検査の重複や医療ミスに伴う間接的なコストの削減にも貢献します。
BCP(事業継続計画)の強化
医療DXはBCPの強化をもたらします。BCPとは事業継続計画のことで、自然災害や感染症拡大による機能不全など緊急事態が発生した際に、事業の継続や早期復旧を図るための計画です。医療データを統合的に管理することによって、全国の病床・在庫・搬送データをリアルタイムで可視化。これにより、災害時や感染症拡大時でも、迅速な対応が可能です。こうしたBCPの強化は、社会全体のレジリエンス(回復力)向上につながります。
日本のヘルスケアDXをデジタル技術で後押し テクノロジーで社会課題の解決を目指すベトナムIT最大手FPT
医療DXの具体例
オンライン予約/問診
診療の受付や問診票の記入といった受診手続きをデジタル化することによって、医師のスケジュール管理を円滑にします。これにより、診療時間の無駄を省け、患者の受診時における待ち時間の短縮につながります。また、自然災害や感染症拡大などの緊急時には、医療機関の待合室の混雑緩和にも役立ちます。
オンライン診療・遠隔モニタリング
医師と患者がビデオ通話や専用アプリを通じて、診療・経過観察を行います。たとえば、血圧や血糖値などのバイタルデータをウェアラブル機器から自動送信し、医師がリアルタイムで確認。これにより患者は定期通院の負担を軽減でき、地方や離島の医療アクセス格差を縮小できます。
ビッグデータの分析・活用
医療データには、診療記録や検査記録、投薬履歴など多くの有益な情報が含まれています。こうしたビッグデータを分析・活用することで、疾患の早期発見や新薬の開発、健康管理のサポート、治療方針の個別化などに役立てることが可能です。また、既存業務の効率化や新しい市場の創出にもつながります。
AIを活用した診断支援・画像解析
放射線画像やMRIの画像データをAIが解析し、異常の有無を検出・マーキングできます。具体的には、AIが過去の症例との類似パターンがないかを照合することで、異常を特定。これにより医師の見落としを防ぎ、診断精度とスピードを向上させます。さらに、医療画像をデータベース化しておけば、経験の浅い医師の判断支援にも有効です。
予防医療・PHR(パーソナルヘルスレコード)の活用
健診結果や服薬履歴、運動・睡眠データなどのパーソナルヘルスレコード(PHR)を、アプリで一元管理できます。AIを活用して健康アドバイスを行うアプリで、医療機関とデータを共有すれば、セルフケアの質向上だけでなく、生活習慣病の早期発見や重症化予防にも役立ちます。
医療DXにおける課題

医療DXの課題として、次の3点が挙げられます。
- 人材に関する課題
- コストに関する課題
- セキュリティとデータに関する課題
それぞれの課題について解説します。
人材に関する課題
医療DXはクラウドやAIを活用した高度なソフトウェア技術であるため、医療知識とITスキルを兼ね備えた人材が不可欠です。しかし、現場ではそうした人材が極端に不足しています。また、医師や看護師は本来業務が多忙で、システム導入やデータ運用に関わる余裕がありません。このため、医療DXの人材育成の研修やキャリアパスの整備が急務となっています。デジタルツールの操作や可視化した医療データの理解など、医療関係者のITリテラシーの向上も求められているのです。
コストに関する課題
医療DXには、電子カルテの標準化やクラウド化、セキュリティ対策など多額の初期投資が必要です。また、保守や更新にかかる費用やクラウド利用料などのランニングコストも発生します。そのため、中小規模の診療所や病院では医療システムの新規導入が困難です。その結果、医療機関の間でデジタル格差が生じています。
セキュリティとデータに関する課題
医療情報は機微な個人データであるため、漏洩や不正アクセスへの懸念が大きな課題となっています。とくに、AIを活用したサイバー攻撃など、セキュリティ対策の高度化・複雑化がますます進んでいます。こうした背景から、医療DXのセキュリティ確保やデータ保護は、一般的な企業の事例よりも高度かつ厳密なルールが求められます。
医療DXへの取り組み事例
FPTは、病院や薬局の情報システム、医療機器向けソフトウェアなどを通じて、医療DXを支援しています。当社の強みは、金融や自動車などの部門で培ったセキュアなシステム構築のノウハウを、同じく高いセキュリティが要求される医療DXに応用できる点にあります。
日本の医療システムでは、個々の医療機関が利用しやすいようカスタマイズ性を優先したため、データベース内の医療データの仕様が標準化できていないのが現状です。そこで当社は、医療情報システムに蓄積されたデータを厚生労働省が推奨する新しい標準規格「HL7 FHIR」に変換し、さらにそのデータを活用して、最新のヘルスケアアプリ構築やデータ二次利用ソリューションを提供します。あわせて、医療ビッグデータ基盤として利用が進むデータモデルに変換するプラットフォームも提供し、データ分析のための環境づくりを支援します。
当社は、日本では放射線や臨床検査部門などの診療科で使われる「部門システム」を構築した実績があります。また、ベトナムでは保険調剤薬局チェーンを自社で展開し、薬歴管理やオンライン予約、患者向けスマートフォンアプリを提供しています。
医療DX推進のご相談ならFPTへ
まとめ
医療業界は医療費の圧迫により、経営が赤字化する病院も増加傾向にあります。それにくわえて、少子高齢化による医療人材の不足や高齢患者の増大が医療業務をさらに圧迫しています。こうした背景から医療DXは喫緊の課題であり、医療機関、製薬業界、介護施設などが一丸となって取り組む必要があるのです。医療DXは、単なる医療データのデジタル化にとどまらず、ビッグデータの分析に基づく医療リソースの最適化や患者や個人の医療データへのアクセシビリティ向上にも役立ちます。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
関連ブログ:コラム
- オフショア開発で成果を上げる事業の特徴や成功・失敗事例を解説
- ECU(自動車の組み込みシステム)とは?意味や目的、種類をわかりやすく解説
- マイグレーションとは何?リプレース・コンバージョンとの違いや手法を徹底解説
- COBOL言語とは何?特徴や構成、書き方、課題を徹底解説
- オフショア開発で起こりがちな失敗事例と原因、成功させるコツを解説