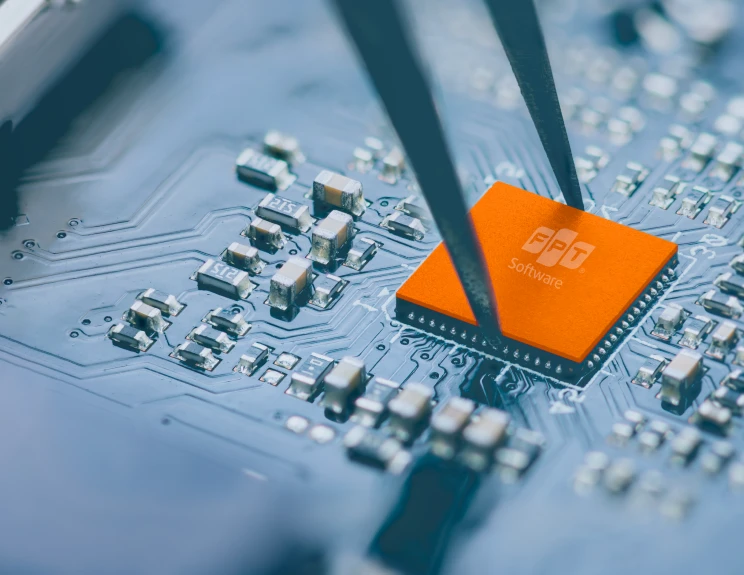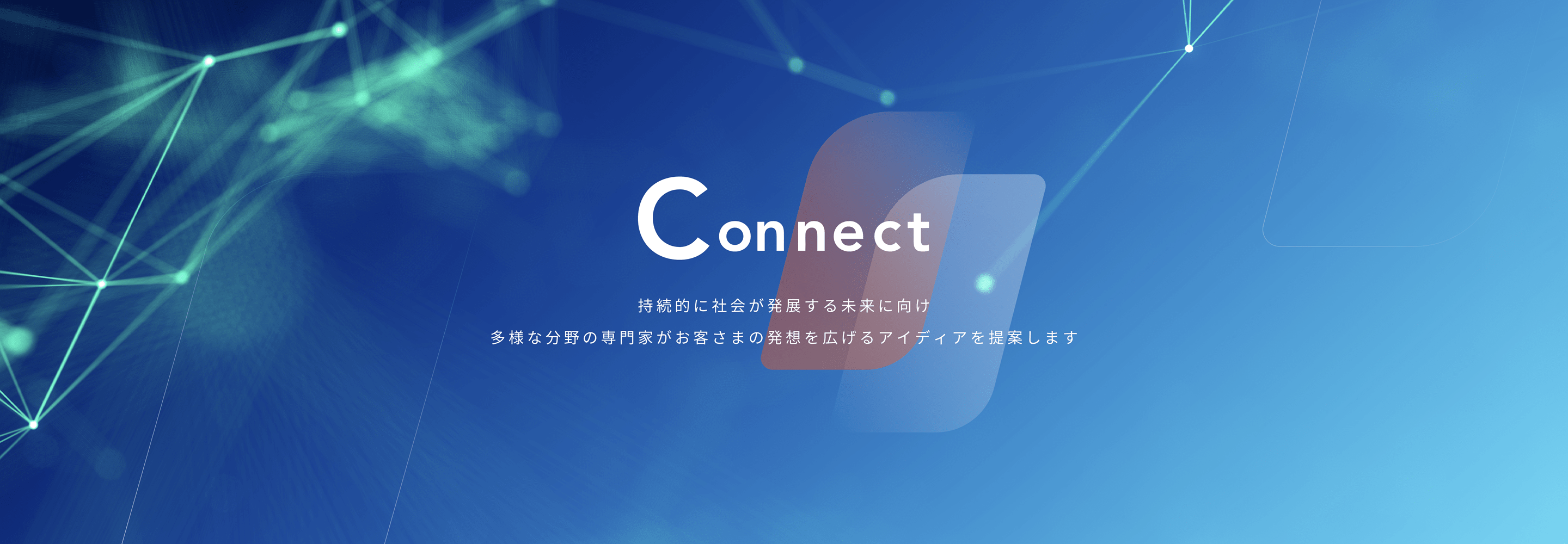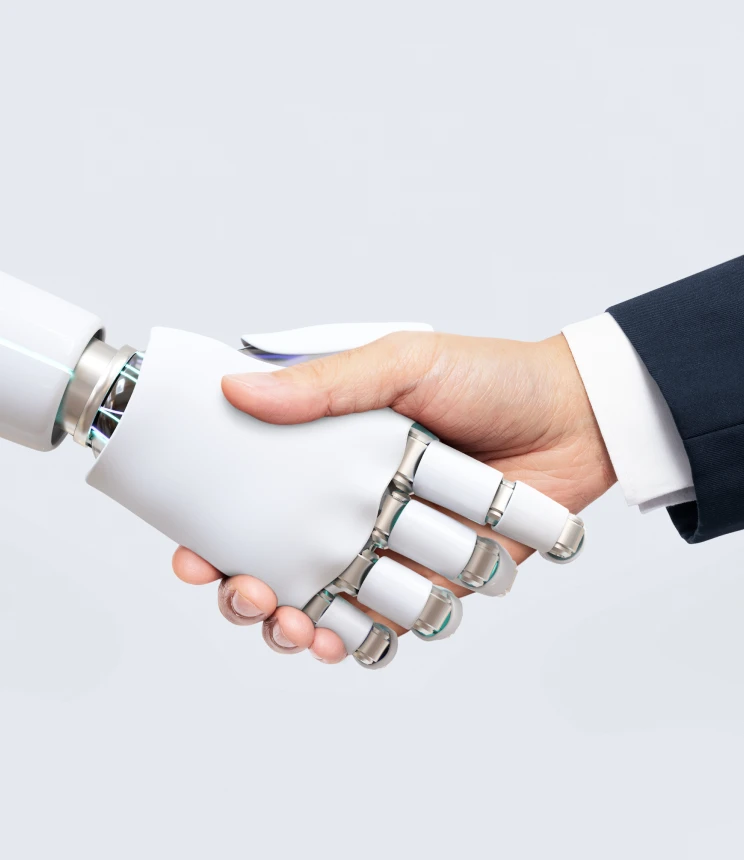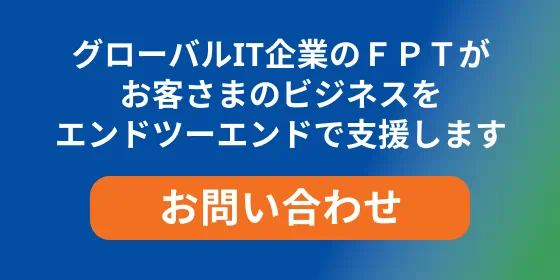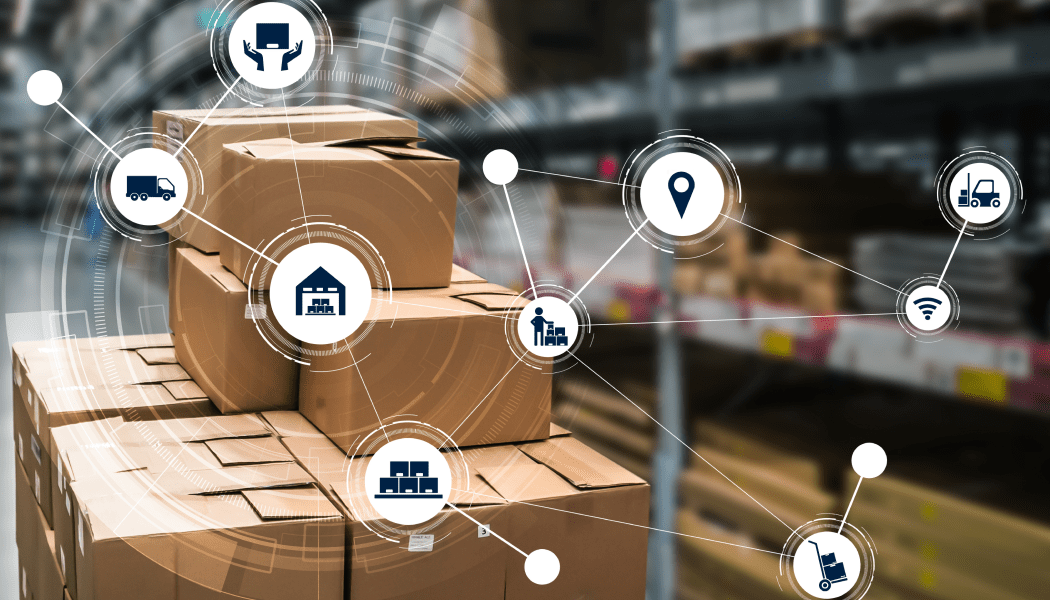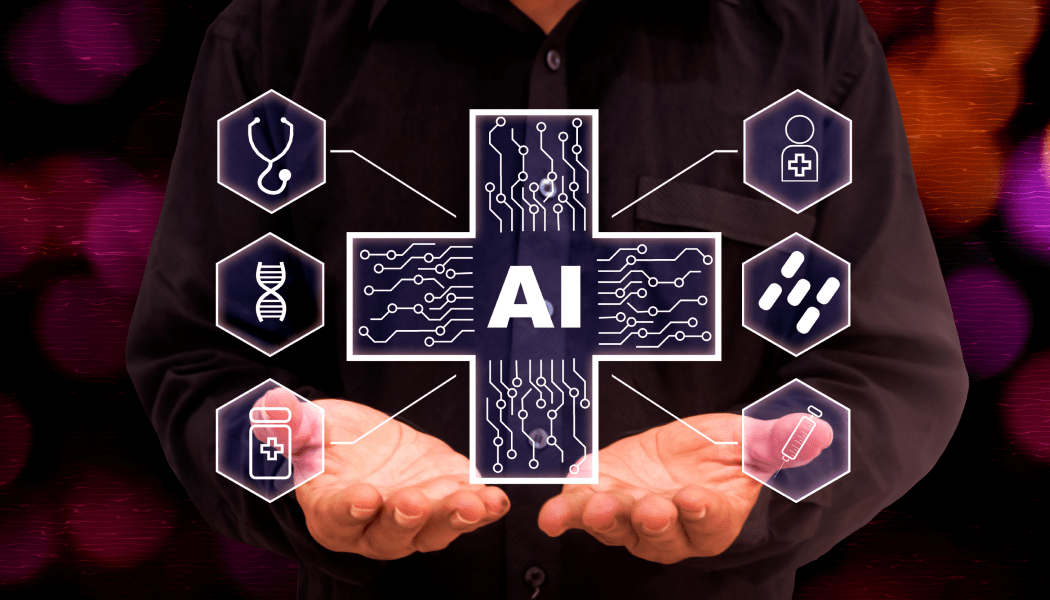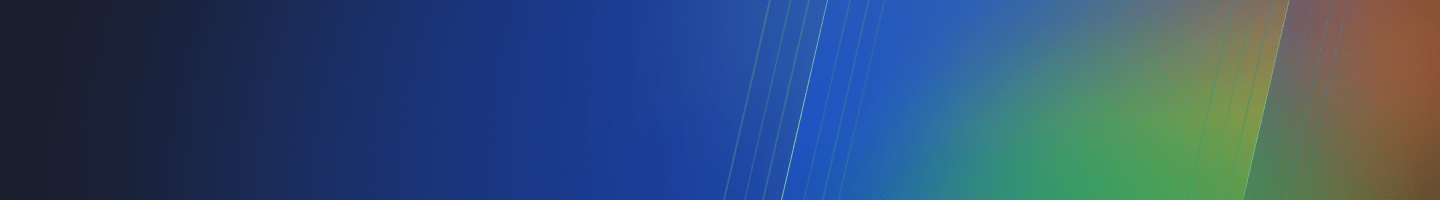ODC(ラボ型開発)とは何か

ODC(ラボ型開発)とは、自社外に専用の開発チームを構築する開発モデルのことです。ODCは「Offshore Development Center」の略称であり、主に海外に拠点を置いて長期的な開発に取り組む組織を構築する手法を指します。
人件費の高騰や最大約79万人のIT人材が不足する「2030年問題」はもちろん、レガシーシステムが更新時期を迎える「2025年の崖」に起因するDX推進の必要性の高まりなど、IT業界が抱えるさまざまな課題を解決する開発手法として注目を集めています。
【関連記事】
⇒2025年の崖とは何?DXが進まない原因や課題、進める方法を解説
ODC(ラボ型開発)と請負型契約の違い
ODCとしばしば混同されるのが、同じく外部のリソースを活用して開発する請負型契約です。両者の違いは契約体系と業務の進め方の2つの軸で理解するとわかりやすいでしょう。まず、ODCは準委任契約の一種であり、契約した期間内の業務(人・時間)に従事して責任を負い対価を得ます。期間内は柔軟にリソースを動かせるため、保守などの継続的なプロジェクトや仕様変更が多いアジャイル開発に適しています。
一方、請負型契約は成果物の完成品を納品して対価を得る契約形態のため、基本的に要件や納期が明確であるウォーターフォール型の単発プロジェクトで多く採用されています。両者の違いを下の表にまとめたのでご確認ください。
ODC(ラボ型開発)と請負型契約の比較
| 比較項目 | ODC(ラボ型開発) | 請負型契約 |
|---|---|---|
| 契約の性質 | 準委任契約 | 請負契約 |
| 支払いの対価 | 稼働した時間・人数」に対して | 「完成した成果物」に対して |
| ベンダーの完成責任 | なし ※善管注意義務はあり |
あり ※完成しないと報酬なし |
| ベンダーの不適合責任 | 原則なし ※期間内の対応のみ |
あり ※納品後のバグ修正義務 |
| 主な開発手法 | アジャイル型 | ウォーターフォール型 |
大まかな違いは上記の通りですが、さらに同じ準委任契約であるSES(システムエンジニアリングサービス)との違いも、ぜひこの機会に理解しておくと、より適切な開発手法を選択できます。両者の違いはリソースの「単位」や「場所」、「目的」などに表れます。
ODC(ラボ型開発)とSES(システムエンジニアリングサービス)の比較
| 比較項目 | ODC(ラボ型開発) | SES(システムエンジニアリングサービス) |
|---|---|---|
| 単位 | 「チーム」単位 | 「個人」単位 |
| 場所 | 主にオフショア(海外)や地方の自社拠点 | 主に発注者のオフィス ※客先常駐 |
| 期間 | 中長期 ※半年〜数年単位 |
短期〜中期 ※1ヶ月単位の更新も多い |
| 目的 | 専属の開発拠点・組織を構築する | 一時的な人手不足や特定スキルの補完 |
| コスト | 比較的安価 ※特にオフショア |
比較的高め ※国内相場 |
| ノウハウ | チーム内に蓄積されやすい | 契約終了と共に個人が離脱し、残りにくい |
ODC(ラボ型開発)のメリット
ODCの代表的なメリットである柔軟性、同一メンバーによる継続開発、MVPの短期間でのリリース、エンジニアの確保のしやすさ、ノウハウの社内蓄積の5点について解説します。
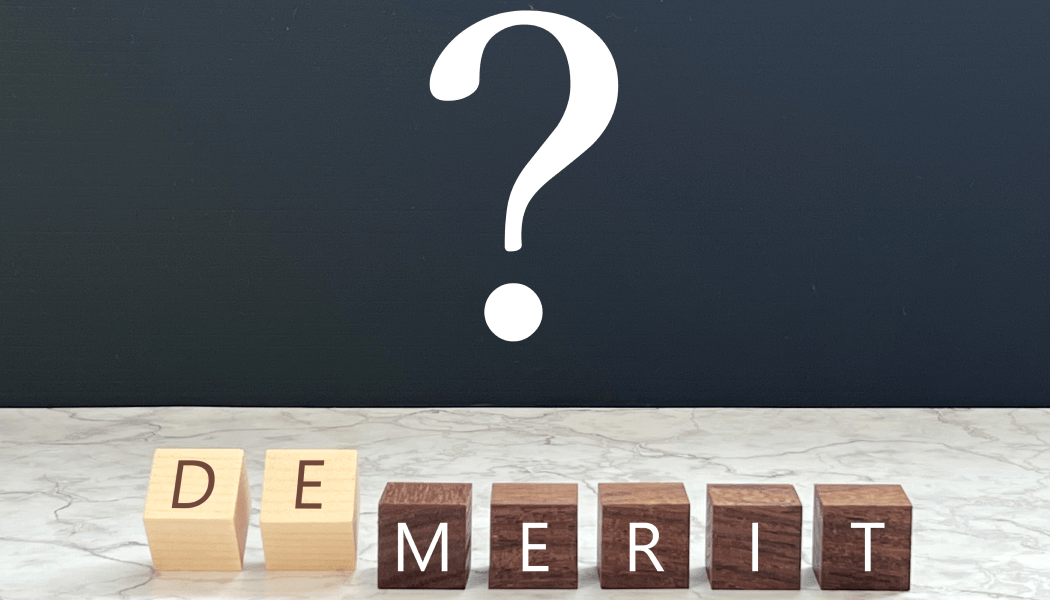
1. 仕様変更への高い柔軟性
前述の通り、ODCの特に大きなメリットは仕様変更に柔軟に対応できる点です。基本的に請負型契約であれば、決まった仕様書に沿って開発を進めるため、途中の変更には改めて見積書や契約書のやり取りが発生してしまいます。さらに工数が増えるたびに追加費用が発生するため、社内調整が必要になるケースもあるでしょう。一方、ODCは契約期間内であれば開発機能の優先順位の変更、開発方針の転換(ピボット)などもスムーズに行いやすいという特徴があります。
また、ODCは外部リソースでありながら「自社の専用チーム」なので指揮系統が直接的であり、ベンダーの担当者などを介さずにプロジェクトを進められるのも大きなメリットです。柔軟な開発体制を整備できれば、変化の激しい市場に即応しやすくなるほか、開発途中で判明した不要機能のカットなどによる開発コストの最適化も図りやすくなります。このようにODCによる開発体制を構築できれば、自社のリソースだけでは得にくいメリットを享受でき、競争力の強化につなげられるでしょう。
2. 同一チームメンバーによる継続的な開発
ODCは契約期間内であれば、エンジニアチームの時間と技術を専有できるため、継続的に開発しやすい環境を作りやすいのも大きなメリットです。同じチームで継続開発する利点は多く、コミュニケーションコストの削減や開発環境の慣れによる開発スピードの向上に加え、チームの責任感の醸成やPDCAサイクルの共有による品質向上やトラブルの抑制も期待できます。さらに請負型契約のようにプロジェクトごとにリソースを確保する必要がなくなるのも、発注者の手間の削減につながるでしょう。
3. MVPの短期間リリース
ODCが適している開発手法は、アジャイル開発だけではありません。最小限の機能を搭載した製品をリリースし、ユーザーのフィードバックを反映して改善を繰り返すMVP(Minimum Viable Product)開発にも適しています。MVP開発は開発費用の抑制や損失リスクの低減、早期投入による市場シェアの確保など、特に新規プロジェクトやスタートアップにとって魅力的なメリットといえます。
4. エンジニアリソースの安定確保
2030年にはITの人材不足分が最大79万人にも達するとされる「2030年問題」が大きな課題になっている昨今、一定期間、安定してリソースを確保できるのは大きなメリットです。また、ODCは多くの場合、海外のエンジニアでチームを構成するため、自社の求める技術力を持ち、かつ人件費を比較的安く抑えられる人材を安定確保できるのは非常に大きな魅力といえます。安定してエンジニアを確保できれば、中長期的なタスクや幅広いプロジェクトを任せられるほか、採用・教育コストの削減にもつながるでしょう。
5. チーム内に蓄積される開発ノウハウ
上記のように安定してエンジニアを確保でき、同じチームメンバーで継続的に仕事をする中で、組織としてのノウハウ・ナレッジが蓄積しやすいのもODCならではのメリットです。PDCAを回すことで得られる定量的なデータの共有はもちろん、成功・失敗体験といったマニュアル化が難しい暗黙知を積み重ねることもできます。技術、ドメイン、関係性といったノウハウは、コミュニケーションが円滑になるほか、業務遂行体制の最適化、引き継ぎリスクの低減といった多くの経営的メリットにつながります。
ODC(ラボ型開発)のデメリット
ODCには数多くのメリットがある一方、独自のデメリットも存在します。そのなかでも特に知っておきたい、短期・単発プロジェクトには不向きであること、クライアントのマネジメント負担が大きいこと、成果物への責任が曖昧になりがちであることの3点について解説します。
1. 短期・単発プロジェクトにおける費用対効果の課題
ODCには長期的な開発には多くのメリットがある一方、短期・単発プロジェクトには不向きな傾向があります。まず、ODCはゼロからチームを構築する必要があるため、採用・人選のほか、セキュリティ設定などの環境構築といった各種コストの負担が大きく、短期・単発プロジェクトでは費用対効果が得られない場合があります。さらに、ODCはリソースが稼働していない時間も月額費用が発生するため、成果物に対して責任を持つ請負型契約の方がコストパフォーマンスに優れるケースも少なくありません。
また、短期・単発プロジェクトは長期プロジェクトと比較して、要件定義や仕様が固定的で、アジャイル開発の必要性が低いことから、あえてODCを選択するメリットは小さいといえるでしょう。
2. クライアントの大きなマネジメント負担
ODCを導入するうえで特にクライアント(発注者)の負担が大きくなるのが、導入時期の管理コスト(マネジメントコスト)です。例えば、海外の開発チームに向けた仕様書の作成には、言語の壁を乗り越えるため、画面の挙動やボタン配置などを詳細に言語化する必要があります。さらに、共有後も正しく仕様書を理解できているかをチェックする工数も発生するため、国内で開発する場合よりもコミュニケーションコストが増えてしまうのは避けられません。
また、ODCは時間に対して費用を支払うため、チームや個々の進捗管理、タスク配分はクライアントの責任となるのが一般的です。そのため、優先順位や作業の指示を細かく行う必要があり、日々のマイクロマネジメントの負担はもちろん、最終的な成果物の品質に対する責任もクライアント側にあることを事前に理解しておく必要があります。
さらに前述したODCのメリットを生かしたチームを作り上げるためには、クライアントによる手厚い教育が必要不可欠です。自社のビジネスモデルや商習慣、業務の進め方などの理解を深めるための工数も重要なマネジメント施策の一つといえるでしょう。加えて、国や言語の壁を超えたチームの一体感の醸成も、離脱リスクの抑制といった観点から求められます。この点からも定期的な面談を実施するといったコミュニケーションコストが発生します。
ODCには上記のようなさまざまなコミュニケーションやマネジメント施策が重要になります。自社にODCを成功に導ける人材やナレッジがあるか、またゼロから構築できる環境が作れるのかが大切になるでしょう。
3. 曖昧になりがちな成果物への責任
前述の通り、一般的な請負型契約は成果物に責任を負うため、期限内に完成しなければ、基本的にクライアントは報酬を支払う必要はありません。さらに、バグなどの瑕疵があった場合は、受託者側が修正する責任があります。一方、ODCは請負型契約のように特定の機能を開発するといった成果物に対する明確な責任がありません。そのため、万が一、期間内に完了しなかった場合やバグなどが発生した場合は、双方の責任が宙に浮いてしまうリスクがあります。
上記のように開発が計画通りに進まなかった場合でも、ベンダー側には報酬を支払う必要があるため、責任は指示したクライアント側にあると見なされるケースも少なくありません。バグのほかにも、ODCのコアメンバーの退職によるプロジェクトの停滞、セキュリティや著作権侵害のインシデントなど、責任の所在が曖昧になってしまうケースはさまざまです。成果物に対する責任が曖昧になりやすいというデメリットは、ODCのメリットである自由で柔軟な開発手法の裏返しであるともいえるでしょう。ODCの利点を最大限に生かすための取り組みはもちろん、注意点をあらかじめ理解し、グレーゾーンの発生を抑えたチームビルディングやプロジェクトマネジメントが重要になるでしょう。
ODC(ラボ型開発)の導入における3つのポイント

ODCのメリットを最大化し、リスクを低減させるためには、ODCに適したプロジェクト・チーム、ブリッジSEと開発環境、明確な評価とルールの構築といったポイントを押さえて導入・運用することが重要です。それぞれについて詳しく解説します。
1. ODCに適したプロジェクト・チームの選定
自社のビジネスモデルや開発環境がODCに適していれば、導入して得られるメリットは多くあります。具体的には、アジャイル開発を採用していて仕様変更が頻発するプロジェクトや、開発後も中長期的な保守や運用、追加の開発が見込まれるケースなどが挙げられます。また、コード規約やテストコード、CI/CDなど、ODCに応用できる開発プロセスがすでに標準化されている環境が構築されているケースもメリットが大きい現場といえるでしょう。
一方、短納期のプロジェクトや仕様が固定されており柔軟性が求められないプロジェクトなどは、請負型契約が適しているといえるでしょう。加えて、新しい技術や法規制など特殊な知識、技能が求められるプロジェクトも、教育コストが大きいためODCに適していないと考えられます。
2. 自社に適したブリッジSEと開発環境の構築
ブリッジSE(ブリッジシステムエンジニア)は、オフショア開発におけるクライアントと委託先(ベンダー)のパイプ役を担うシステムエンジニアのことです。ODCにおいても、要件・仕様の適正な翻訳、コミュニケーションの円滑化、プロジェクト・リスク・品質の管理から商習慣の調整まで、幅広い役割を担っています。そのため、ブリッジSEの能力が、ODCプロジェクトの成否を大きく左右するといっても過言ではありません。日本語能力や文脈を読み解く力、ITスキルと経験、プロジェクト管理ツールの習熟度、商習慣への理解などをチェックしましょう。
一方、クライアント側がブリッジSEに頼りすぎると属人化のリスクが高まります。ブリッジSEの暗黙知をドキュメントなどで共有するほか、関係者が集まる場を設けるなどしてブリッジSEに依存しないチーム作りも求められます。
3. 明確な評価制度とルールを作る
ODCでは、海外の開発チームが自社のために機能する環境を構築することが大切です。そのためにはODCに適した定量・定性的な評価制度を導入し、月次の評価とクライアントからのフィードバックを繰り返して改善を図る必要があります。具体的な指標は以下が挙げられます。
| 評価項目 | 具体的な指標(例) |
|---|---|
| 生産性 | ・チケット消化数 ・ストーリーポイント完了数 |
| 品質 | ・バグ検出率 ・手戻り発生率 ・コードレビュー指摘数 |
| 自発性 | ・改善提案の回数 ・ドキュメントの更新頻度 |
| スキル | ・新技術の習得 ・日本語能力の向上 |
また、時差を踏まえた迅速なレスポンス、定例会を実施するといったコミュニケーションルールのほか、開発・納品に関するルール、ソースコード管理などのセキュリティ・情報管理ルールといった各種ルールを明文化し、徹底する必要があるでしょう。
まとめ
ODCを正しく導入し、運用できれば、コストパフォーマンスに優れ、柔軟で安定性の高い開発体制を構築することができます。一方、海外の開発拠点とのコミュニケーションやマネジメントの負担など、導入には注意点が多くあるため、ベンダー選びがODCの成功に直結します。開発実績やブリッジSEのレベル、採用力、セキュリティ体制などの観点から自社に適したベンダーを選定し、良好なパートナーシップを築くことが大切です。

この記事の監修者・著者:FPTコンテンツ制作チーム
FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →
関連リンク
- FPTとアテックがベトナムにおけるODC設立に基本合意
- FPTジャパンホールディングスは凸版印刷株式会社とODC(Offshore Development Center)を設立。安定したIT人材の供給とグローバルでのITサービスの提供を目指す
- FPTジャパンホールディングスは東邦ガスグループとODCを設立し、安定したIT人材の供給とデジタルサービス創出を促進
関連ブログ:コラム
- 物流DXとは何?業界の現状や課題、取り組みの具体例を徹底解説
- 医療AIの現状と導入の課題、メリット・デメリットを徹底解説
- 2025年の崖とは何?DX化が進まない原因や課題、進める方法を解説
- リバースエンジニアリングの手法や目的、活用のメリットやリスクを徹底解説
- ADAS(先進運転支援システム)とは?ADとの違いと今後の展望について