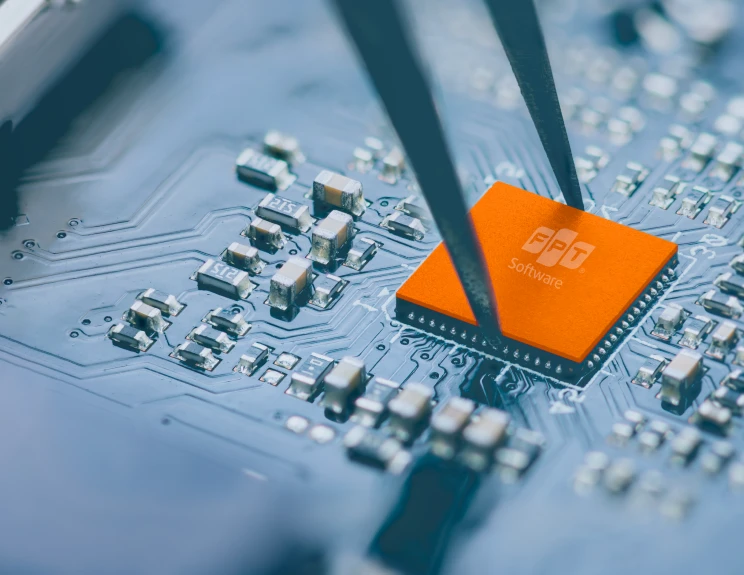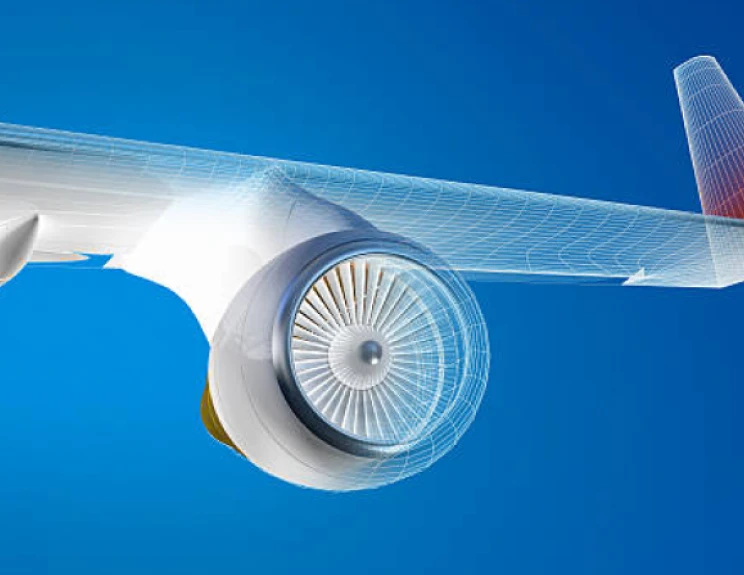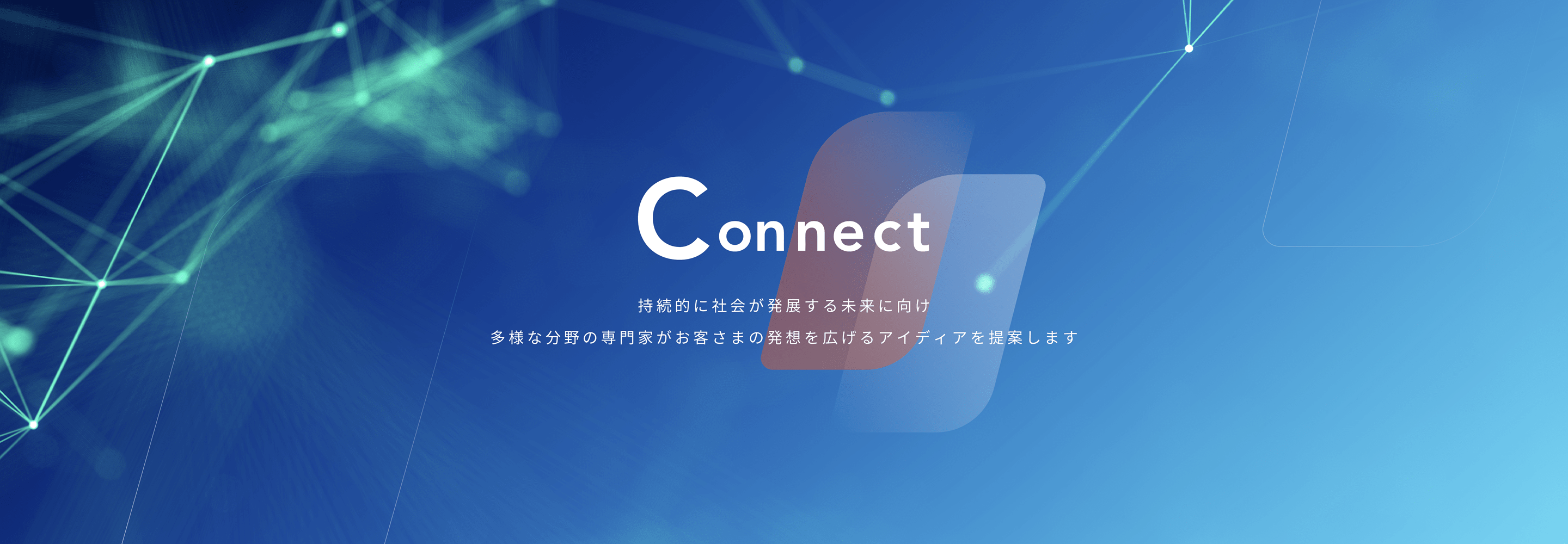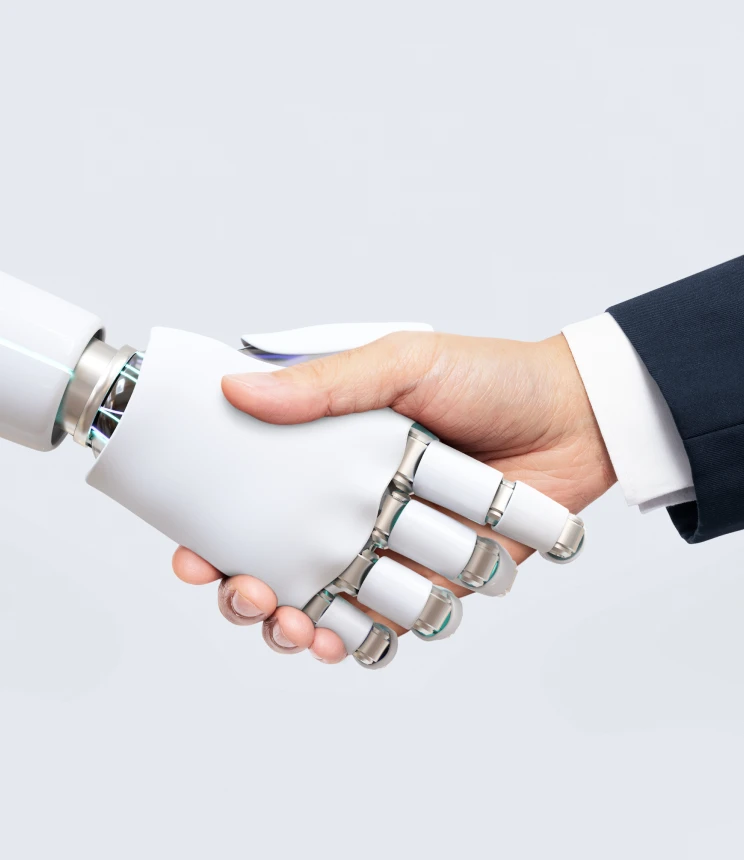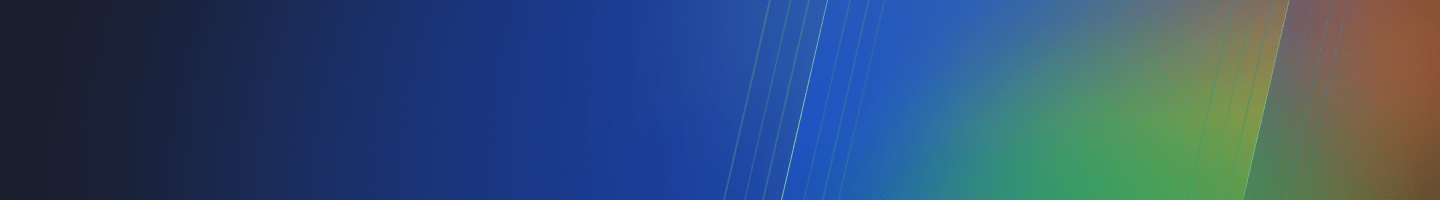近年、中国市場における日系企業の事業環境は大きく変化しています。日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部が2024年11月28日に発表した「海外進出日系企業実態調査|アジア・オセアニア編 」には、中国に進出する日系企業が直面している最新の課題や、各地域の動向が詳細にまとめられています。本記事では、この最新調査データをもとに、中国市場の現状や地域ごとの特徴を分析し、それがオフショア開発環境にどのような影響を与えているのか、そして日系企業が今後取るべきIT戦略について分かりやすく解説します。
営業利益と景況感に広がる格差
2024年の営業利益見込みは、アジア・オセアニア地域全体として黒字割合が前年調査より3.4ポイント上昇し65.8%となり、回復傾向を示しました。この好調の最大の要因は「現地市場での需要増加」であり、改善理由として47.4%の企業がこれを挙げています。
この回復基調とは対照的に、中国では、2024年の営業利益の黒字割合は2013年以降で最低水準に落ち込み58.4%となりました。また、同年のDI値は-17.7ポイントと大幅なマイナスを記録しました。見通しが悪化した最大の理由を「現地市場での需要減少」として66.7%の企業が指摘しています。これは地域全体平均の53.3%を大きく上回る数値です。さらに、「他社との競合激化」を挙げる企業も49.8%に達し、内需の冷え込みと熾烈な競争という二重苦に直面している実態が明らかになりました。こうした厳しい業績見通しは、企業のIT投資戦略にも直接影響します。新規投資への慎重論が高まる一方で、既存システムの運用コスト削減や、より費用対効果の高い開発手法としてオフショア開発への関心が高まる可能性があります。
(出典:日本貿易振興機構(ジェトロ) 調査部 2024年度「海外進出日系企業実態調査|アジア・オセアニア編 」P6~14)
二極化する事業拡大意欲
今後の事業展開に対する意欲にも、景況感の差が色濃く反映されています。今後1~2年で事業を「拡大する」と回答した企業の割合は、アジア・オセアニア地域全体では43.8%の企業が拡大意欲を示しています。
その一方で、中国での事業拡大意欲は21.7%と、調査開始以来の過去最低を更新しました。64.6%が「現状維持」と回答するなか、「縮小」(12.3%)や「第三国(地域)へ移転、撤退」(1.4%)を選択する企業の割合も他国に比べて高く、中国市場に対する慎重な姿勢が際立っており、市場の成熟や競争環境の変化が企業の成長戦略に影響を与えています。事業拡大への慎重な姿勢は、大規模な新規システム開発プロジェクトの減少に繋がるかもしれません。その一方で、現状維持や事業効率化を目指す動きの中で、既存システムの保守・運用(AMO)や、コスト最適化を目的としたオフショア開発の活用がより一層重要になると考えられます。
(出典:同P17)
厳しさを増す中国の競争環境
中国市場の厳しさは、競争環境の変化に関するデータからも裏付けられます。5年前(2019年)と比較した主力製品・サービスの市場シェアについて、中国では「縮小した」と回答した企業が41.9%に上り、「増加した」(29.2%)を大幅に上回りました。
さらに深刻なのは、競争相手の増加です。中国では、競合相手の数が5年前に比べて「増加した」と回答した企業の割合が60.4%に達し、他国・地域を圧倒しています。競争相手としては「地場企業」を挙げる声が96.7%と、ほぼ全ての企業が意識しており、現地企業の台頭が日系企業の事業を圧迫している構図が鮮明になりました。最大の競争相手と考える理由として、中国企業は「コスト競争力」(84.7%)に加え、「意思決定の早さ」(55.8%)が強みとして認識されています。 これは、中国企業が国内市場だけでなく、海外市場においても競争力を高めていることを示唆しています。地場企業との厳しい競争に打ち勝つためには、DXによる業務効率化や新たな顧客体験の創出が不可欠です。しかし、国内のIT人材不足が深刻化するなか、スピーディーかつ高品質な開発を実現するためのパートナーとして、オフショア開発企業の役割がますます重要になっています。
(出典:同P23~28)
加速するサプライチェーンの再構築
世界的なインフレに伴うコスト上昇や、コロナ禍で露呈したサプライチェーンの脆弱性を受け、企業の調達戦略は見直しを迫られています。製造業の71.5%が直近5年間で「新しい調達先の開拓」を実施したと回答しており、サプライヤーや調達国・地域の分散化を進める動きが活発化しています。
こうしたなか、特に、日本や中国からASEANへの生産移管が顕著で、移管先としてはベトナムが24.8%と最多となりました。その理由としては、「コスト競争力の向上」と並び、「チャイナリスクの回避」が挙げられており、地政学的リスクや予測不能な政策変更を念頭に置いた「チャイナ・プラスワン」の動きが加速していることを示しています。 中国では現地調達率は60.1%と高い水準を維持しています。そのため、企業はコストや効率性だけでなく、より多角的な視点からサプライチェーンの最適化を図る必要に迫られています。そしてこの「チャイナ・プラスワン」の考え方は、オフショア開発における開発拠点の選定においても極めて重要な視点となります。
(同P40~46)
FPTのベストショア活用について
こうした中国市場の変化と「チャイナ・プラスワン」の流れを受け、IT開発の現場ではどのような戦略が求められるのでしょうか。その一つの答えが、FPTが提唱する「グローバルベストショア」です。 「グローバルベストショア」は、日本企業のIT人材不足という課題を解決するための世界戦略です。これは、オンショア(顧客国内)、ニアショア(国内の遠隔地)、オフショア(海外)を最適に組み合わせ、複数の地域から企業のシステム開発を支援する手法を指します。このモデルにより、技術力の高い人材を確保しながらコストを抑制し、地政学リスクに備えることができます。
日本企業には、日本国内でのオンサイト支援、沖縄拠点によるニアショア、ベトナムなどによるオフショアを組み合わせて提供します。このモデルを強化するため、2024年には日本語IT人材が豊富な中国・大連に新拠点を開設しました。これにより、日本企業が最上流、大連が上流、ベトナムが下流といった役割分担でリソースを有効活用し、日本企業がより戦略的な上流工程に集中できるよう支援します。
FPTのグローバルベストショアは、単なるコスト削減を目的としたオフショア開発とは一線を画します。レガシーシステムへの対応支援や、日本企業の東南アジア市場への進出サポートなど、多様な価値を提供することを目指しており、日本企業と共創を前提としたエコシステムを構築し、共に成長していくための戦略です。
参考URL:「グローバルベストショア」で日本企業のDXを支援 ベトナムIT最大手FPT、人材需要に応える世界戦略とは
まとめ
今回の調査結果は、中国における日系企業の事業環境が、大きな転換点を迎えていることを示しています。中国は内需の減速と過酷な競争環境により、もはや「世界の工場」「巨大市場」という言葉だけでは語れない、複雑な市場へと変貌しました。日系企業は、各市場のダイナミックな変化を的確に捉え、事業ポートフォリオやサプライチェーン戦略を柔軟かつ大胆に見直していくことが不可欠です。そしてその動きは、オフショア開発戦略にも直結します。中国市場のリスクをヘッジしつつ、ベトナムをはじめとする多様なリソースを活用する「チャイナ・プラスワン」の視点を取り入れた開発体制の構築が、今後の持続的な成長に向けた鍵となるでしょう。

FPTコンテンツ制作チームは、ITソリューションやデジタル技術に関する情報を発信しています。業界動向や技術トピックについて、記事の制作を行っています。
監修者・著者の詳しい情報はこちら →